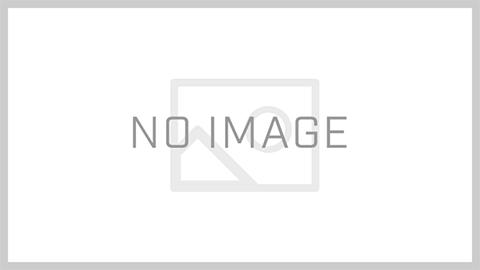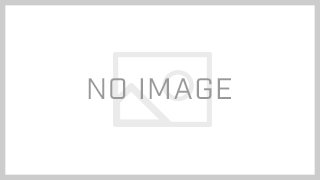過去問は厚労省ホームページより引用しております。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics_150873_139_140.html
第69回臨床微生物学PM68~78
問題 68 薬剤感受性検査でスキップ現象が認められたため再検査を行った。初回と再検査の微量液体希釈法の結果(別冊 No.14)を別に示す。
最小発育阻止濃度(MIC 値)[μg/mL]はどれか。

- 0.5
- 1
- 4
- 8
- >8
解説
★スキップ現象
- 薬剤希釈系列中に不連続な発育が認められること
1管のスキップは無視するが図のように0.5、1と2管以上のスキップが生じた場合は、判
定を保留して再検査を行う。
その結果再検値ではスキップ現象は認めず、最終的に発育を阻止した最小の薬剤希釈濃度8μg/mLがMIC値となる。
答え4
問題 69 初尿を用いて検索を行うのはどれか。
- Candida albicans
- Escherichia coli
- Neisseria gonorrhoeae
- Pseudomonas aeruginosa
- Streptococcus agalactiae
解説:細菌検査における採尿のポイントです。
★一般的な尿路感染症
- 初尿は捨て、中間尿を採る
★尿道炎
- 初尿を採る。
Neisseria gonorrhoeae(ナイセリア ゴノレエ:淋菌)や
Chlamydia trachomatis(クラミジア トラコマティス)が主な起因菌となる。
初尿は中間尿と比べて、尿道分泌物や尿道内の上皮細胞を多く含んでいるため検査に適している。
答え3
問題 70 ブドウ糖発酵菌はどれか。2 つ選べ。
- Aeromonas hydrophila
- Burkholderia cepacia
- Pseudomonas aeruginosa
- Stenotrophomonas maltophilia
- Yersinia pestis
解説:ブドウ糖発酵菌は腸内細菌科に多く見られ臨床的意義も高いため、覚えておきましょう。
★ブドウ糖発酵菌3細菌科
好気・嫌気の双方で良好に発育するため、通性菌または通性嫌気性菌とも 呼ばれる菌類
- 腸内細菌科(Yersinia pestis,Escherichia coli など)
- ビブリオ科(Family Vibrionaseae)
- エロモナス科(Family Aeromonadaceae)
答え1と5
問題 71 Salmonella enterica subsp. enterica serovarTyphi について正しいのはどれか。2 つ選べ。
- 乳糖を分解する.
- インドールテストが陰性である.
- リジン脱炭酸試験が陽性である.
- オキシダーゼテストが陽性である.
- TSI 寒天培地でブドウ糖からのガスを産生する.
解説:Salmonella enterica subsp. enterica serovarTyphi(チフス菌)についての問題です。字が小さく見にくいですがまとめておりますので参考にしてください。

表よりチフス菌は
- オキシダーゼテストは陰性
- TSI寒天培地でブドウ糖からのガス非産生
- 乳糖と白糖は非分解
- インドールテストは陰性
- リジン脱炭酸反応は陽性
- 硫化水素は産生量は少ないが陽性
答え2と3
問題 72 肺炎が疑われた患者の喀痰の Gram 染色標本(別冊 No.15)を別に示す。分離菌はブドウ糖を発酵し、オキシダーゼ試験と運動性は陰性であった。考えられるのはどれか。

- Acinetobacter baumannii
- Klebsiella pneumoniae
- Mycoplasma pneumoniae
- Pseudomonas aeruginosa
- Streptococcus pneumoniae
解説:グラム染色像には赤色に染まる(紫に染まらない)桿菌様の細菌が観察できる。
- グラム陽性(紫色)
- グラム陰性(赤色)
写真の細菌には菌体の周囲に莢膜が観察できる
- 莢膜を持つ細菌⇒グラム陰性桿菌
- Acinetobacter baumannii(アシネトバクター バウマニ)ブドウ糖非発酵のグラム陰性桿菌
- Klebsiella pneumoniae(クレブシエラ ニューモニア:肺炎桿菌)ブドウ糖発酵菌、運動性(-)
- Mycoplasma pneumoniae(マイコプラズマニューモニア)細胞壁がないのでグラム染色に不染
- Pseudomonas aeruginosa(シュードモナス エルギノーザ:緑膿菌)ブドウ糖非発酵のグラム陰性桿菌
- Streptococcus pneumoniae(ストレプトッコッカス ニューモニア:肺炎球菌)グラム陽性球菌
答え2
問題 73 真菌について正しいのはどれか。
- Aspergillus fumigatus は大分生子を形成する
- Candida glabrata は仮性菌糸を形成する
- Cryptococcus neoformans は厚膜胞子を形成する
- Exophiala dermatitidis は黒色コロニーを形成する
- Mucor 属は菌糸に隔壁を形成する
解説:設問を正しい形に直し、補足説明します。
- Aspergillus fumigatus(アスペルギルス フミガーツス):多数の小分子を連鎖状に形成する
- Candida glabrata(カンジダ グラブラータ)は酵母形のみ形成する
Candida albicans(カンジダ アルビカンス)は酵母細胞、菌糸、仮性菌糸のすべての形態をとる - Cryptococcus neoformans(クリプトコッカス ネオフォルマンス)は細胞壁の外側に多糖体で構成される厚い莢膜を有する
- Exophiala dermatitidis(エクソフィアラ・デルマチチヂス)は黒色コロニーを形成する(正しい)
Fonsecaea 属(フォンセケア属)、Phialophora 属(フィアロフォラ属)も黒色コロニーを形成する
※細胞壁にメラニン色素を含有する真菌は黒褐色の集落を作るため『黒色真菌』と呼ばれている。 - Mucor 属(ムコール属)は無隔壁の真性菌糸
答え4
問題 74 検査が有用でないのはどれか。
- 結核を疑う患者の喀痰抗酸菌培養検査
- 感染性心内膜炎を疑う患者の血液培養検査
- 尿路感染症を疑う患者の尿中レジオネラ抗原検査
- クリプトコックス髄膜炎を疑う患者の髄液中グルクロノキシロマンナン抗原検査
- 抗菌薬関連下痢症を疑う患者の糞便中 Clostridi-oides difficile トキシン抗原検査
解説:設問におけるそれぞれの検査意義を知っていると解くことができます。
- 結核を疑う患者の喀痰抗酸菌培養検査
⇒喀痰培養、抗酸菌検査を出します - 感染性心内膜炎を疑う患者の血液培養検査
⇒心内膜炎の起炎菌を同定するために血液培養を出します - 尿路感染症を疑う患者の尿中レジオネラ抗原検査
⇒尿中レジオネラ抗原、肺炎球菌はそれぞれ肺炎の補助診療検査となります
レジオネラはリポ多糖体(LPS)を主成分とする可溶性の特異抗原を検出
肺炎球菌は莢膜多糖抗原を検出する
検査法:イムノクロマト法 - クリプトコックス髄膜炎を疑う患者の髄液中グルクロノキシロマンナン抗原検査(C.neoformansの莢膜多糖体)
⇒髄液や血液でも検査を行う - 抗菌薬関連下痢症を疑う患者の糞便中 Clostridi-oides difficile トキシン抗原検査(クロストリジウムディフィシル)
⇒抗生物質の投与に続発する下痢症や大腸炎、偽膜性大腸炎の主要な原因菌
抗生物質の投与によって他の菌が死滅するとこの菌だけが生き残り異常増殖(菌交代現象)し、毒素を産生することもある
答え3
問題 75 蛋白合成阻害薬はどれか。2 つ選べ。
- アミカシン
- ダプトマイシン
- バンコマイシン
- ミノサイクリン
- シプロフロキサシン
解説:抗菌薬の系統の問題です。作用機序で覚えていると楽勝です。
★蛋白合成阻害薬
- アミドグリコシド系(アミカシン)
- テトラサイクリン系(ミノサイクリン)
- マクロライド系
- クロラムフェニコール
- リネゾリト
など
- ダプトマイシン ⇒ 細胞質膜合成阻害薬
- バンコマイシン ⇒ 細胞壁合成阻害薬
- シプロフロキサシン ⇒ 核酸合成阻害薬
答え1と4
問題 76 Mycobacterium 属について正しいのはどれか。
- M. leprae は小川培地で発育する
- M. avium は硝酸塩還元試験陽性である
- M. marinum の至適発育温度は 37℃である
- M. fortuitum は培養 7 日目には肉眼的に観察できる
- M. tuberculosis と M. bovis は市販の結核菌検出用 PCR 試薬で鑑別できる
解説:抗酸菌についての問題です。Mycobacterium属菌は結核菌群と非結核性抗酸菌(NTM)、培養不能なM. lepraeに大別されます。
まず設問①のM.lepraeですが、培養不能なので小川培地で発育しません。
そして⑤の結核菌群であるM. tuberculosis とM. bovis は市販のPCR試薬では鑑別できません。
非結核性抗酸菌(NTM)は発育速度によってM. fortuitum やM. abscessusのような迅速発育菌(1週間以内に発育)とM. aviumやM. marinumなどの遅発育菌に分類されます。M. aviumは硝酸塩還元試験陰性で、M.marinum は至適発育温度が30℃近辺(28~30℃)となっています。
答え4
問題 77 選択分離培地と目的菌の組合せで正しいのはどれか。2 つ選べ。
- BBE 寒天培地 Neisseria meningitidis
- CCFA 寒天培地 Bacteroides fragilis
- CIN 寒天培地 Yersinia enterocolitica
- NAC 寒天培地 Pseudomonas aeruginosa
- Thayer-Martin 寒天培地 Clostridioides difficile
解説:選択分離培地と目的菌のよく出る問題です。
正しい形に直してみます。
★選択分離培地と目的菌
- BBE寒天培地 Bacteroides fragilis
- CCFA寒天培地 Clostridioides difficile
- CIN寒天培地 Yersinia enterocolitica
- NAC寒天培地 Pseudomonas aeruginosa
- Thayer-Martin寒天培地 Neisseria gonorrhoeae
答え3と4
問題 78 消毒用エタノールに対して抵抗性を示すのはどれか。
- B 型肝炎ウイルス
- インフルエンザウイルス
- ノロウイルス
- ヒト免疫不全ウイルス
- ヘルペスウイルス
解説:エタノール濃度をあらかじめ70~80%に調整した消毒用エタノールは多くのウイルスや細菌に有効とされる。一部の細菌やウイルスには無効となる。
現場でも知識が無いとノロウイルスに汚染された環境をアルコールで清掃し、その結果エアロゾルとなり感染してしまうことがあるので気をつけましょう。
★エタノールに抵抗性を持つ細菌やウイルス
- エンベローブを持たないウイルス(ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルス、A型肝炎ウイルスなど)
- 有芽胞菌(Clostridium difficile,Bacillus cereusなど)
答え3