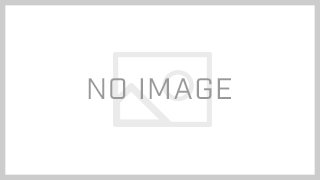★この記事には、尿沈渣のルーチンを行うにあたり必須の成分を下記の内容で解説しています。勉強した内容以外にも僕の主観もあるので、あくまで参考程度に留めてください。
- 細胞の形態
- 鑑別ポイント
- 陽性(カウント)基準
- 再検基準や注意点
- 類似する成分
- 補足事項
★また、無料で見れる尿沈渣検査J-STAGEアトラスのリンクを貼っておきますので、写真も見つつ参考にしてみてください。
- 僕が勤めている病院のやり方であったり、教科書の内容と外れた表記もあるかもしれません
- あくまで新米臨床検査技師向けの尿沈渣のコツを伝えるのが本記事の目的ですので参考程度にお願いします。
- 中級者以上の方には物足りない内容となっています。
おススメの尿沈渣の参考書籍1選(というかコレ1拓)
尿沈渣の検査を始めて5年、もし五年前の自分にアドバイスできるならこう言います。
「教材をケチるな、経験も大切だけど教材も大切」だと。
一番おススメの教材「そこが知りたい尿沈渣検査」のレビューはこちら
この事実に気付くまで少々の時間がかかりました。僕の職場はアトラスがあるのでそれに甘えていました。アトラスと経験でどうにかなると思っていましたが、甘かったです。
やはり、専門的な考え方が重要なので、教材は熟読すべきでした。
尿沈査のルーチン
注)教科書の表現は固く、わかりづらかったので、なるべく柔らかい表現をするようにしています。
- 尿カップにある尿をよく混ぜる(沈殿物を浮遊させる)
- 遠沈管に10mL程分注する(尿量が少ない場合はコメントを付ける)
- スイング型遠心機で500Gで5分間遠心する(1500rpmで5分)
- デカント法もしくはアスピレーターを用いて上清を捨て、沈渣成分が200μLになるようにする
- スポイト等で沈査成分をよく混ぜる
- スライドグラスに無染色とS染色の2パターン滴下(約15μL)し、カバーガラスを載せる(尿沈渣部分と染色液の割合は4:1)
- 弱拡大(100倍)で全体を見る
- 強拡大(400倍)で1視野ずつ見る(最低10視野~30視野)
- 無染色の鏡検結果を報告する
★上表⑦、⑧の鏡検時のコツ
- 弱拡大(100倍)のS染色で全体を観察し、円柱や細胞の確認を行う
- 気になる細胞はS染色の強拡大(400倍)で観察する
- 全体の雰囲気を掴んでから無染色で鏡検を行う
- 円柱類の見落としが気になれば再度S染色で確認を行う
S染色では、沈渣成分の希釈や溶血などがあるため、あくまで上皮の鑑別や円柱の見落としのカバー程度に使いましょう
検査結果の記載
強拡大(400倍)で鏡検し、1視野100個まで算定するのが基本。
1視野を1/4に分割し、25個以上細胞があれば100個以上とカウントしても良し。
(施設の基準に合うようにしてください)
沈渣成分の報告方法は、各施設により多少異なるはずなので、JCCLSの記載法を参考までに載せておきます。

尿沈渣を見る前に
尿沈渣を見る上で、1番のキーとなるのが尿の外観と尿一般結果です。
加えて、診療科、性別や年齢も加味することで、顕微鏡を見ずともすでに尿沈渣の結果がうっすら見えてきます。
- 血尿
- 膿尿
- 結晶がありそう
などなど
しかし、これでは結果の捏造になってしまうので、当然ながらしっかりと見ていきます(笑)
顕微鏡で沈渣を見てみる
- 顕微鏡の使い方(コンデンサ、開口絞り、視野絞り)
- 尿一般の潜血、たんぱく、糖などを事前にしっかり把握しておく
- 混濁やにおいも確認する(細菌尿だと嫌でもにおいはわかります)
- 女性は扁平上皮多め=常在菌の可能性あり
- 男性(中年以上の潜血は注意)
などなど
顕微鏡の使い方ですが、尿沈査の場合は、開口絞りは8~9割絞ります。(暗め)明るいと細菌などを見落とします。
また、視野絞りに関しては、見やすい明るさに調節しましょう。
患者の属性(年齢、性別)と尿一般の検査結果はしっかり把握しておきましょう。
また、検体の出どころ(受診している科)がわかるのであれば、そこにもヒントが隠れています。
- 泌尿器はもちろん腎臓内科などでは異常細胞が出現している可能性がUP
- 乳幼児の小児の高熱による脱水などで、尿細管上皮の出現率UP
尿沈渣を見るにあたって最低限鑑別が必要なもの
- 赤血球
- 白血球
- 扁平上皮
- 尿路上皮(移行上皮)
- 尿細管上皮
- 細菌
- 真菌
- 円柱類
- 結晶類
★異型細胞は、鑑別が難しいため怪しいと思ったら先輩技師や上司に相談しましょう。また、医師に報告し細胞診を出してもらうのも手です。
異型細胞は、背景に赤血球を認めることも多く細胞も色んな高さでピントが合うのが特徴です。(癌などで異常上皮が重なり、それが剥がれ落ちるため)
僕がこれらの細胞で、沈査を初めて見た時や、研修期間時に悩んだ事や鑑別の助けになったポイント等を紹介していこうと思います。
各細胞の紹介と鑑別点など
赤血球
★赤血球の形態と特徴
- 正常は、無核で細胞の両面がくぼんだ円盤形
- 平均直径は7.5μm
- 酸性で球状化、アルカリ性で扁平化
- 下記の通り浸透圧やpHで形状は変化する
- 高浸透圧、低pH(酸性尿)で委縮して金平糖状になる
- 低浸透圧、高pH(アルカリ性尿)で膨化し、ゴースト状となる
赤血球鑑別のポイント
- 上部尿路出血(糸球体性血尿)では標的状、コブ状、ドーナツ状、小型状などの大小不同及び多形態を示す【dysmorphicRBC:変形赤血球】が出現する
- 下部尿路出血(非糸球体性血尿)では金平糖状やゴースト状などの形態を示し、【isomorphicRBC:均一赤血球】が出現する
- しかし、非糸球体性RBCでも、コブ状の形態を示すことはある。その際はコブを見ずに観察すると、均一な赤血球である(大きさや形)
★糸球体型RBCと非糸球体型RBCの鑑別は臨床でも重要だし、各種サーベイのフォト問題でも必ず出題されるよ
陽性基準
- 5個以上/HPF(400倍)
再検基準
- 尿定性との乖離
- ヘモグロビン尿やミオグロビン尿で乖離することもある(尿定性+、沈渣-など)
類似する成分
- 酵母様真菌
- シュウ酸カルシウム結晶
- 精子の頭部
- 脂肪球
- レシチン顆粒
- 気泡
補足事項
- RBCは10%酢酸で溶血して、見えなくなる
- 非糸球体性RBCの出現する病態は尿路感染、高カルシウム尿症、ナットクラッカー現象、出血性膀胱炎などがある
- 糸球体性RBCの出現の時には「変形赤血球を認めます」とコメントする検査室もある(最初は鑑別が難しいので先輩、経験者に相談しよう)
- 中年以降の男性で血尿がある場合は異形細胞に注意
白血球
白血球の形態と特徴
- 好中球(尿中白血球の約95%)
- 大きさは12~15μm(RBCより大きい)
- 尿中WBCは、球状~円形、類円形
- 生細胞の場合、球状、棒状、糸状、乳頭状、コブ状、アメーバ状など多彩な形態を呈する
- 輝細胞ではブラウン管運動をする顆粒もある
- 死細胞は、尿の浸透圧やpHの影響で委縮状や膨化状を呈する
白血球の鑑別のポイント
- S染色で核は青~紫色、細胞質は赤紫色~青紫色に染まる
- 生細胞は染まりにくく、死細胞は染まりやすい(輝細胞など)
陽性基準
- 5個以上/HPF
注意点
- 10個以上/HPFの時に細菌、真菌などの炎症があるか(膿尿)
類似する成分
- 膣トリコモナス
- 尿細管上皮
鑑別方法
- 新鮮な尿の場合トリコモナスは鞭毛で動いている
- 尿細管上皮は核が分葉していないし、細胞質がギラギラ、ザラザラしている
補足事項
- 鑑別が難しい場合は5~10%酢酸を加えてると核が明瞭化されてわかりやすい
- 円柱内の細胞は特に鑑別が難しい(気がする)ので、一緒に出ている背景の細胞を観察しましょう。
扁平上皮

扁平上皮の形態と特徴
- 大部分は外尿道口の粘膜に由来する
- 女性では子宮膣部外陰部由来も含まれる
- 正常でも出現するが、ホルモン療法、感染症、腫瘍によっても出現する
- 組織像は基底膜に対して細胞が水平で多層的に配列し、基底膜側から深層細胞、中層細胞、表層細胞で構成されている
深層~中層型細胞
- 単体でばらついて出現する
- 大きさは20~70μm
- 辺縁構造は曲線状で明瞭
- 形は円形~類円(丸っぽい)
- 表面構造は均質状
- 細胞質は厚く豊富なグリコーゲンを含有し、灰白色~灰色
- 核は中心性に位置し、中層型細胞では白血球大10~15μmで網状クロマチンを呈する
表層型細胞
- 表層型はもっともよく観察される
- 単体でばらついて出現、もしくは集塊状に出現する
- 大きさは60~100μm
- 辺縁構造は多稜状で明瞭
- 形は不定形
- 表面構造は均質状で細胞質は薄く灰白色調でしわを有することがある
- 核は中心性に位置し、赤血球大10μmで濃縮状
- S染色で深層型~中層型細胞は染色性が不良
(染まっても淡桃色に染まる程度) - 核は不染なことが多い
- 表層型は染色性が良好(上の写真参照)
陽性基準
- なし(日常的に観察される)
注意点
- 女性でWBCが濃染細胞として数多く出現し、中層型細胞が固まって散見される場合は、真菌感染やトリコモナスの寄生の可能性があるため、注意深く観察する(丸っぽい細胞がたくさん出ているときは注意)
類似する成分と鑑別方法
★類似する尿沈渣成分
- 特殊型(円形)尿細管上皮細胞
- 尿路上皮細胞
- 扁平上皮癌細胞
★鑑別方法
- 扁平上皮はペらぺら薄い感じ
- 扁平上皮細胞は無染色で灰白色、辺縁構造が曲線状で明瞭、表面構造が厚みのある均質状を呈すること
- 扁平上皮癌細胞との鑑別は、細胞量が少ないこと、ヘビ・オタマジャクシ状の細胞形を呈するが、異常角化した奇妙な細胞が認められないこと
- N/C比の増大とクロマチンの増大が認められない
尿路上皮


尿路上皮細胞の形態と特徴
- 腎盂、尿管、膀胱、尿道の前立腺部に由来する
- 尿路における感染症、結石症、腫瘍やカテーテル挿入で出現する
- 組織の部位によって層形成が異なる
- 腎乳頭の表面:1~2層、腎盂:2~3層、尿管:4~5層、膀胱粘膜:5~6層の多列上皮となっている
深層~中層細胞
- 単体でばらついて出現~集塊状に出現する
- 大きさは15~60μm
- 辺縁は角状で明瞭
- 表面構造は漆喰状および細顆粒状でザラザラした感じ
- 細胞質は黄色~灰白色
- 核はやや大きく1~2核で偏在性に位置している(多核)
表層細胞型
- 単体でばらついて出現することが多い
- 大きさは60~150μm
- 辺縁構造は角状で明瞭
- 形は丸みのある洋梨~紡錘形
- 表面構造は漆喰状や細顆粒状でザラザラした感じ
- 細胞質は黄色
- 核は1~3核、時に多核を示し中心性~偏在性に位置する
- 最外層には細胞質が広く、傘を広げたような形態を示すアンブレラ細胞を認めることもある
反応性尿路上皮
- 単体でばらついて出現~集塊状に出現する
- 大きさは15~60μm
- 辺縁は角状で明瞭
- 表面構造は漆喰状および細顆粒状でザラザラしている
- 細胞質は黄色~灰白色
- 核は他の層と比べるとN/C比は増大し、核小体も明瞭となる
- クロマチンの増量はなくどの細胞も同様な染色性を示す。変性を伴っていることもある
染色性
S染色で染色性は良好
- 核は青色に染まる
- 細胞質は赤紫色~濃桃色に染まる
陽性基準
- 1個以上/HPF
注意点
- 多数の白血球、細菌、塩類、結晶を認めた場合は尿路の感染症や結石症が考えられるため再度注意深く確認する
- 集塊状で出現したときは、カテーテル尿の可能性がある
類似する成分と鑑別方法
★類似する成分
- 尿細管上皮
- 扁平上皮
- 尿路上皮癌細胞
★鑑別方法
- 尿路上皮は無染色で黄色、辺縁構造が角状で明瞭、表面構造が漆喰状を示すことから尿細管上皮、扁平上皮と鑑別することはできる
- 尿路上皮がん細胞との鑑別は、細胞量が少ないこと、N/C比の増大とクロマチンの増量が認められないことで可能
- 尿路上皮細胞は、尿路感染症、前立腺肥大症による影響、結石症及び体外衝撃波破砕術による影響、腫瘍、カテーテル挿入に伴う機械的損傷によって認められる
尿細管上皮

尿細管上皮細胞の形態と特徴
- 腎臓の皮質と一部髄質に存在する近位尿細管からヘンレの係蹄、遠位尿細管、集合管、腎乳頭までの内腔の上皮層に由来する(教科書等で確認してください)
- 近位尿細管から集合管まで見られ、単層の立方上皮で構成されている。
ヘンレ係蹄の細い部分(薄壁尿細管)は単層扁平上皮、遠位尿細管の一部は円柱上皮で構成されている - 近位尿細管は、尿細管のうち最も長く1/2を占めている
遠位尿細管は短く1/3 - 遠位尿細管の上皮は近位尿細管の上皮に比べ多数の核がある。
※刷子縁はないが微絨毛がみられる - 基本形(よく見るもの)と特殊な形状のものに分けて観察するのがいい
- 患者の背景も加味して観察すると見落としも減るかもしれない。(小児の発熱に伴う脱水時など)
※刷子縁(さっしえん)とは小腸の吸収上皮細胞および腎臓の近位尿細管細胞の上部に存在する長さや太さが不揃いの微絨毛が密に形成されている領域
基本型の尿細管上皮
- 単独かつ散在性に出現する
- 大きさは10~35μm(大きいとWBCの2~3倍)
- 形状は不定形
鋸歯型(きょしじょう:のこぎりの歯の様にギザギザしたもの)
- 単独かつ散在性に出現
- 鋸歯型はよく観察される尿細管上皮
- 辺縁は鋸歯状で、表面はゴツゴツした不規則な顆粒構造をしている(ザラザラ、ギラギラしている)
- 細胞質は黄色で、核は偏在している
- ミトコンドリア顆粒が豊富なため、大部分は近位尿細管由来とされているする。
棘突起・アメーバ偽足型(きょくとっき:突出した様子をしめすこと)
- 単独かつ散在性に出現
- 辺縁は棘状や樹枝状に分岐したアメーバ偽足状
- 表面構造は細顆粒状で細胞質は黄色調
- 核は偏在している
- ミトコンドリア顆粒が豊富なため、大部分は近位尿細管由来とされている
角柱・角錘台形型
- 単独かつ散在性に出現
- 内腔面が短く、基底膜面側が長くなっている
- 立体感が強く、側面側は角柱型、正面像は角錘台形型を示す
- 辺縁は角状で、基底膜側は不明瞭になりやすい
- 表面構造は均質状で、微細顆粒状
- 細胞質は黄色~灰白色
- 核は濃縮状で、基底膜側に位置することが多く偏在性である
- 小型で細胞表面が均質状なので、遠位尿細管やヘンレの係蹄由来とされている
- ミトコンドリア顆粒が豊富なものは近位尿細管由来ともされている
特殊型
- 平面的な小集塊で出現することが多い
- 辺縁構造は明瞭で、曲線状
- 表面構造は網目状で細胞質は薄く灰白色
- 核はやや大型で、核小体が目立つ場合もある
- N/C比の増大やクロマチンの増量は見られない
- 近位、遠位の尿細管細胞上皮由来の再生上皮と考えられている
オタマジャクシ・ヘビ型、繊維型
- 平面~やや重積構造で、束状や放射状の集塊で出現
- 円柱に付着して観察される
- 辺縁は淡い線状で不明瞭である
- 表面構造は均質状で、細胞質は薄い黄色~灰白色
- リポフスチン顆粒を認めることもある
- 核はやや大型で、深層の尿路上皮に類似しているが細胞質にねじれやしわがあること、集塊の場合は細胞境界が不明瞭であることなどから鑑別はできる
※リポフスチン顆粒:黄褐色顆粒状の色素で、蛋白質と脂質から成る複合体
空砲変性円柱・顆粒円柱型
- 単独かつ散在性に出現
- 辺縁構造は明瞭
- 表面構造は均質~細顆粒状
- 細胞質は黄色~灰白色で大小の空砲を有する
- 高度の尿障害で出現
細菌鑑別のポイント・コツ

由来
- 外尿道口付近の常在菌、腸内細菌、膣内のデーデルライン桿菌に由来する
健常者でも少数は認められることもある - 尿路感染症のときは、細菌数の増加と多数のWBCとともに出現する
1/3は大腸菌(Escherichia coli) - 尿の外観は白濁した黄色を呈することが多い(膿尿)
- 刺激臭もしばしばある
形態
- 散在性~集塊で出現する
- 大きさは菌種によって異なる
類似する沈渣成分と鑑別方法
★類似する成分
無晶性塩類
★鑑別方法
- 細菌は大きさや形が整っていることが多い
- 光沢がない
- グラム染色をしてもわかりやすい
- 結晶は溶解させても良い
臨床的意義
- 尿路感染症で認められる
- 細菌尿の基準は随時尿で105CFU/mL以上、カテ尿で104CFU/mL以上
- 大腸菌が大半を占め、腸球菌や緑膿菌などが多く出現する
真菌鑑別のポイント・コツ

由来
- ほとんどは子宮膣部のカンジダに由来する
- 稀にアスペルギルスや空中に存在する真菌も出現する
形態
- 散在性~集塊で出現する
- 大きさは3~6μm
- カンジダは円形~楕円形を示し、出芽や仮性菌糸をを認めることもある
- アスペルギルスはホウキのような形状をとる(菌糸の分岐がカンジダは90度だが、アスペルギルスは45度)
※アスペルギルスは見たことないです(珍しい?)
類似する成分と鑑別方法
★類似する成分
RBC
※大量の酵母様真菌が出現して、RBCが数個の場合大変見にくいです。頑張って鏡検しましょう笑
下の写真も酵母様真菌とRBCが出現しています(背景が汚くて申し訳ない)

★鑑別方法
- 酵母様真菌は酢酸で溶解しない(酢酸の滴下がわかりやすいかも)
- RBCに比べ、楕円みが強い
- 酵母様真菌は独特の光沢感がある(慣れてきたらわかります)(
臨床的意義
- カンジダは膣自浄作用の低下や糖尿病、抗生物質の投与、妊娠時などに出現する
- 入院患者は抗生剤投与もあり、免疫も低下していることからよく見られる
円柱
円柱とは
- 各種円柱は、原尿流圧の減少、尿浸透圧の上昇、アルブミン濃度の上昇、pHの低下によって遠位より下部の尿細管で分泌されるTamm-Horsfallムコタンパクとアルブミンがゲル化して形成されたもの
- 組織中の各円柱は、尿細管腔全体に詰まった状態で認められ、原尿流圧の上昇、正常化によって尿中に出現する
- 尿中では白血球より幅が広く並行する二辺を有し、辺縁が明瞭な円柱状を呈する
円柱の判別基準
- ガラス円柱に細胞成分が封入されている場合、3個以上封入されている場合をその細胞成分名の円柱とし、2個以下のものはガラス円柱とする
- 顆粒成分が含まれる場合、顆粒成分が1/3以上封入されているものを顆粒円柱とし、1/3未満のものはガラス円柱とする
- 基質内に卵円形脂肪体が1個封入された場合、卵円形脂肪体は脂肪顆粒を3個以上含有しているため脂肪円柱とする
- ガラス円柱に類似した一方の先端が細く有尾状を呈するものや(類円柱)、長楕円形で平行な部分をもたいない不完全な円柱様物質の中にはガラス円柱とするものもある
- 基質内に細胞成分が2種類以上、かつ3個以上封入されている場合、その各々の成分名の円柱とする
- 顆粒円柱に細胞成分が混在する場合、細胞成分が3個以上あれば細胞成分を優先し、その細胞円柱とする
- 顆粒成分とろう様成分が混在する場合はろう様成分を優先し、ろう様円柱とする
- 円柱の幅が60µmを超えた場合、その各種円柱と同時に幅広円柱とする
幅の計測は、WBC(大きさ約10µmを比較対象として、6個以上の場合を幅広円柱とする
※メーカーサーベイなどで円柱のフォトサーベイもあるのでやってみるといいですよ。(僕はアー〇レイさんのをしています)
ガラス円柱の形態
- 基本構造は均質無構造であるが、内部構造がしわ状、切れ込み、螺旋状、一方の先端が細い有尾状、長楕円形で平行な部分を持たない不完全な形態を呈する場合もある
- 無染色では灰白色を呈する
染色性
S染色で染色性は良好で淡青色~濃青色に染まる
※水色っぽいです(基本の円柱となるのでしっかり鑑別できるようにしましょう)
注意点
- 尿蛋白が陽性の時に出現しやすいので注意して観察する
- 尿蛋白-でも出現することはある
類似する沈査成分との鑑別方法
★類似する沈渣成分
- アーチファクト
- 繊維
★鑑別方法
- アーチファクトはカバーガラスのズレで生じるため、平行かつ同じ方向性になる
- 繊維は人工的で規則正しい穴状の構造がある
※いずれも人工的、機械的な感じがします
硝子円柱の臨床的意義
- 健常者でも少数は認められる
- 激しい運動後、ショック時、高血圧症患者、腎血流低下した場合に出現する
補足
- Tamm-Horsfallムコタンパク濃度によって基質の厚みが薄くなることがあり、無染色標本では見落としやすい
- なるべくS染色で確認をする(尿4:S染色1)で滴下すれば、1.25増しが無染色となるはず
上皮円柱の形態
硝子円柱内に尿細管上皮を3個以上含むもの、または辺縁部に付着している円柱
染色性
円柱内の尿細管上皮はS染色で染色性は良好で核は青色調に、細胞質は赤紫色調に染色される
陽性基準
1個以上/WF
注意点
上皮円柱を認め、尿細管上皮を認めない場合は再確認
※尿細管上皮が主に封入されるため、基本的には一緒に出現します
類似する沈査成分と鑑別方法
★類似する成分
白血球円柱
★鑑別方法
- 白血球円柱内の白血球は核は分葉(好中球)または膨化状(単球)で、細胞質は薄く辺縁構造が不明瞭
- 背景に出現している細胞と比較してみる
臨床的意義
- 健常者でも数個は見るので、少量なら意義はなさそう?
- 虚血による尿細管壊死、薬剤などの腎毒性物質による尿細管障害、肝腎症候群などによって認められる
補足
全ての上皮円柱は尿中に排出されるか尿細管腔に形成された円柱を排除するため、尿細管上皮細胞は剥離することでネフロンへの障害を防御する。この状態が円柱の辺縁に尿細管上皮細胞が付着した上皮円柱
顆粒円柱の形態
- 硝子円柱内に封入された有形成分(大部分は尿細管上皮)が変性し、祖~
微細な顆粒状を呈する - 無染色で灰白色~黄色調を呈する
- S染色で染色性は良好で赤紫色~濃赤紫色、または濃青紫色に染色される
陽性基準
1個以上/WF
注意点
顆粒円柱を認め、尿細管上皮を認めない場合は再確認
※尿細管上皮由来が多いため
類似する沈査成分と鑑別方法
★類似する成分
食物残渣
★鑑別方法
- 食物残渣は顆粒円柱状物質が薄い膜に包み込まれた二重構造で認められる
- 背景に出現している多数の細菌も参考になる
臨床的意義
慢性糸球体腎炎などの腎実質に障害がある場合に出現する
※中等症以上の腎障害の時によく見る気がします。腎臓内科で多く見ます。
ろう様円柱の形態と特徴
- 基質が厚く辺縁が明瞭で、切れ込み、屈曲状、いくら状を呈する
- 無染色で灰白色~黄色を呈する
染色性
S染色で染色性は良好で淡赤紫色~濃赤紫色または濃青紫色に染色される
陽性基準
1個以上/WF
注意点
ろう様円柱を認め、卵円形脂肪体や脂肪円柱を認めない場合は再確認する
※ネフローゼなどの重度の腎障害の時に出現しますが、「ネフローゼ症候群という診断が無い場合は検査室によってはろう様円柱を取る事自体しない」施設もあるかもしれません。取る際は要確認です。
類似する沈査成分と鑑別方法
★類似する成分
化学繊維
★鑑別方法
化学繊維は人工的な硬い素材感があり、二辺が幾何学的に並行
ろう様円柱はのっぺりした感じがある
臨床的意義
ネフローゼ症候群、腎不全などの重篤な腎疾患に認められる
補足
ろう様円柱の切れ込みは、尿細管腔での長時間停滞による濃縮を表している
つまり、尿細管腔を長時間閉塞し、ネフロンに大きな障害を与えていたことを意味する
脂肪円柱の形態と特徴
- 基質内に脂肪顆粒や卵円形脂肪体を含む円柱
- 脂肪顆粒は無染色で茶褐色~黄金色を呈する
染色性
円柱内の脂肪顆粒はS染色での染色性は不良でズダンⅢ染色で橙赤色~赤色に染色される
陽性基準
1個以上/WF
注意点
脂肪円柱を認め、卵円形脂肪体やろう様円柱を認めない場合は再確認する
類似する沈査成分と鑑別方法
★類似する成分
- 細長い脂肪顆粒細胞
- 卵円形脂肪体
★鑑別方法
これらは平行な二辺を待たず、基質が確認できないことや細胞に厚みがあることから鑑別可能である
臨床的意義
ネフローゼ症候群などの高タンパク尿を伴う腎疾患で出現する
赤血球円柱の形態と特徴
- 基質内に赤血球を3個以上含む円柱
- 赤血球の形状は球状~変性崩壊した顆粒化したものまである
- 無染色で淡黄色を呈する
染色性
円柱内の赤血球はS染色で不良であるが、脱ヘモグロビン状の赤血球は赤紫色に染まる
陽性基準
1個以上/WF
注意点
赤血球円柱を認めた場合は背景に変形赤血球が出現していないかを確認する
類似する成分と鑑別方法
★類似する成分
塩類・結晶円柱
★鑑別方法
塩類・結晶円柱はS染色で染色が不良~不染性あることや屈折率が異なる
RBC円柱出現時は背景にRBCが高確率で出現している
臨床的意義
IgA腎症などの慢性糸球体性腎炎で腎出血を伴う腎疾患に認められる
補足
円柱内の赤血球は、円柱内に封入されたゲル化タンパクによって包まれているため、尿細管腔を流れる際の流速、浸透圧、電解質などの変化に影響されないため、変形赤血球ではない(意外です)
白血球円柱の形態と特徴
- 基質内に白血球を3個以上含む円柱
- 白血球の形状は円形~類円形を呈する
- 無染色で灰白色~黄色を呈する
染色性
円柱内の白血球は、S染色での染色性は生細胞では不良であるが、死細胞では核が青色に染まる
陽性基準
1個以上/WF
注意点
炎症背景に円柱があれば注意深く観察する
類似する沈査成分と鑑別方法
★類似する成分
上皮円柱
★鑑別方法
円柱内の尿細管上皮細胞は、表面構造は顆粒状、辺縁構造は明瞭、核は濃縮状を呈することから鑑別可能
臨床的意義
強い出血と炎症を呈するループス腎炎や腎盂腎炎患者では好中球が主体、腎移植後に拒絶反応を起こしている患者ではリンパ球主体化学療法中の患者では単球主体となる
空砲変性円柱の形態と特徴
- 円柱内に大小不同の空砲が認められる円柱
- 基質は顆粒状~ろう様であることが多い
- 無染色で灰白色を呈する
染色性
- S染色で染色性は良好で、赤紫色調~青紫色調に染まる
- 空砲部分は染まらずに抜けて見える
陽性基準
1個以上/WF
注意点
無染色の円柱が出現している場合は、再度観察する
類似する沈査成分と鑑別方法
★類似する成分
食物残渣
★鑑別方法
食物残渣は二重構造が特徴的なので鑑別可能
臨床的意義
- 糖尿病性腎症の患者尿に高率で認められる
- 糖尿病性腎症は、広義の糖尿病を合併した原発性糸球体腎炎と狭義の糖尿病の一病変として発症した腎病変があり、後者で空砲変性円柱は著明にみられ、血清CRE値が2.0mg/dL前後から出現しやすい(糖尿病内科、腎臓内科で多く見れる)
補足
- 空砲変性した尿細管上皮細胞に由来すると考えられている
- 無染円柱の空砲化である可能性が高い
結晶と塩類の鑑別
結晶・塩類の由来
結晶・塩類は腎臓から排泄された成分が腎・尿路系や採尿容器内で析出及び結晶化したもの
通常結晶
無晶性塩類(尿酸塩、リン酸塩)
形態特徴
★尿酸塩由来
- 尿酸塩は顆粒状~小円形を示し、比較的柔らかい質感である
- 無染色で淡黄色~レンガ色を呈する
★リン酸塩由来
- リン酸塩は細顆粒状~顆粒状として認められ、硬い質感
- 無染色で無色~淡緑色を呈する
類似する沈査成分と鑑別方法
★鑑別を要する成分
顆粒円柱や尿細管上皮の崩壊による顆粒成分とヘモジデリン顆粒
★鑑別方法
無晶性塩類はS染色で不染であり、酢酸、塩酸、水酸化カリウムのいずれかによって溶解するので鑑別できる
臨床的意義
健常者でも食事で出現する為、意義は少ない
継続的にみられる場合は、尿細管障害や尿路結石症の原因となるので要注意
補足
塩類は溶解させると見やすくなるが、血球や上皮細胞が変性したり崩壊してしまうので、注意する
シュウ酸カルシウム結晶
形態
- 重屈折性のある正八面体、亜鈴状、ビスケット状、楕円形を示す
- 無染色で、無色~淡黄色
類似する沈渣成分
★鑑別を要する成分
RBCと酵母様真菌こ
★鑑別方法
- シュウ酸カルシウムは塩酸で溶解するが、酢酸に溶解しない。
- 酢酸でRBCは溶血する
臨床的意義
シュウ酸を豊富に含む食物の摂取で健常者でも出現する(ほうれん草、アスパラガス、トマト、みかん)
補足
- 亜鈴状やビスケット状の結晶はシュウ酸カルシウム1水和物
- 正八面体はシュウ酸カルシウム2水和物
尿酸結晶
形態
- 砥石状、菱形、束注状など様々な形態をとる
- 無染色で無色~黄褐色を呈する
類似する成分と鑑別方法
★鑑別を要する成分
シスチン結晶
★鑑別方法
尿酸結晶は厚みがあり、黄褐色を呈することや60℃加温、水酸化カリウム、アンモニア水で溶解するため鑑別可能
臨床的意義
- 尿酸結石は上部尿路結石の約6%を占め、患者数は上昇傾向
- 尿中尿酸排泄量は700mg/日であるが、1100mg/日以上で約50%に尿酸結石を形成する
リン酸カルシウム結晶
形態
- 板状、針状、束注状など様々な形態を示す
- 無染色で無色~灰白色を呈する
類似する沈渣成分と鑑別方法
★鑑別を要する成分
尿酸結晶
★鑑別方法
リン酸カルシウム結晶はアルカリ性~中性尿で見られ、塩酸、酢酸で溶解することや、束柱状の形態を示す場合は杙(くい)のように先が細くなっている
臨床的意義
尿路感染症でみられ、副甲状腺機能亢進症では結石を発生しやすい
リン酸アンモニウムマグネシウム結晶

形態
- 屈折性のある西洋棺蓋状、封筒状、プリズム形など様々な形態を示す
- 無染色で無色~淡黄色を呈する
類似する沈渣成分と鑑別方法
★鑑別を要する成分
尿酸結晶
★鑑別方法
リン酸アンモニウムマグネシウム結晶は、アルカリ~中性尿で見られ、塩酸、酢酸で溶解する
臨床的意義
- Proteus属の感染を原因とすることが最も多い
- Klebsiella属、Pseudomonas属、Serratia属などのウレアーゼを持つ尿素分解菌の感染によって、尿素からアンモニアが作られて尿がアルカリ化し、リン酸アンモニウムマグネシウムが結晶化する
尿酸アンモニウム結晶
形態
- 棘のある球状など様々な形態を示す
- 無染色で茶褐色を呈する
類似する沈渣成分と鑑別方法
★鑑別を要する成分
尿酸塩・尿酸結晶
★鑑別方法
尿酸アンモニウム結晶はアルカリ尿で見られ、塩酸、酢酸、水酸化カリウムで溶解するため鑑別可能
臨床的意義
- 尿路感染症で見られる
- ダイエットや難治性便秘を原因とした緩下剤乱用による脱水と尿量の減少。尿中尿酸濃度とアンモニア濃度の上昇によって尿酸アンモニウムが結晶化する
炭酸カルシウム結晶
形態
- 無晶性顆粒状、小球状、ビスケット状などの形態を示す
- 無染色で無色
類似する沈渣成分と鑑別方法
★鑑別を要する成分
シュウ酸カルシウム結晶
★鑑別方法
炭酸カルシウム結晶は、アルカリ~中性尿で見られ、酢酸で気泡を発しながら溶解する
臨床的意義
健常者でも見られ、意義は低い。炭酸カルシウムを含む薬剤の服用でも出現する
異常結晶
ビリルビン結晶
形態
- 針状
- 無染色で褐色
- 白血球や上皮細胞上に認めらることもある
類似する沈渣成分
★類似する成分
薬剤結晶
★鑑別方法
ビリルビン結晶はクロロホルム、アセトンに溶解
その他異常結晶
- チロシン結晶
- ロイシン結晶
- コレステロール結晶
- シスチン結晶
- 2,8-ジヒドロキシアデニン結晶
僕が検査で見つけた細胞編
画像①


まとめ
尿沈渣は、上記項目以外にもまだまだたくさんの細胞が存在します。
僕も未だにわからない細胞に出くわしたり、異形細胞が出るとドキッとすることもあります。
今回紹介した細胞はルーチンで頻繁に出会うものばかりなので、最低限これらは鑑別できるようになってください。
新米技師や、異動で初めて尿沈渣を担当する!という方にこの記事が少しでも役立てば幸いです。
上達のコツはとにかく目を慣らす事と、細胞に対する知識です。
ウェブでも十分に知識は得られますが、やはり画像となると書籍の方が見やすいです。
尿沈渣を早く習得するためには参考書を一冊程度はもっておくべきだと思います。