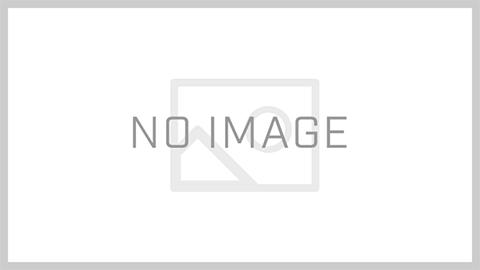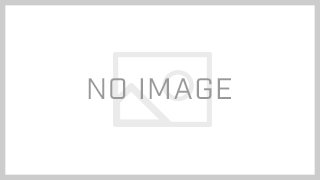SAI
国家試験公衆衛生学PM問90~94です。
過去問は厚労省ホームページより引用しております。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics_150873_139_140.html
国家試験の過去問解説のまとめページです
第69回公衆衛生学PM90~94
問題 90 法律とそれに規定されている内容の組合せで正しいのはどれか
- 児童福祉法 母子健康手帳
- 老人福祉法 ケアハウス
- 精神保健福祉法 療育手帳
- 身体障害者福祉法 福祉事務所
- 知的障害者福祉法 地域包括支援センター
解説:法律と規定内容を正しい形に直しました。正答数が2問あり、不適問題と思われます。
- 母子保健法:母子健康手帳
- 老人福祉法:ケアハウス(正)
- 知的障害者福祉法:療育手帳
- 身体障害者福祉法:福祉事務所(身体障害者福祉法の他に知的障害者福祉法、老人福祉法、社会福祉法も規定されている)(正)
- 介護保険法:地域包括支援センター
答え2と4
※厚生労働省の解答:2
問題 91 女性労働者の産前産後休暇を規定しているのはどれか
- 母子保健法
- 労働基準法
- 労働安全衛生法
- 育児・介護休業法
- 男女雇用機会均等法
解説:各法律の説明を簡単にします。
- 母子保健法
母性・乳児・幼児の健康保持と増進を目的とした法律 - 労働基準法
女性労働者の産前産後休暇を規定 - 労働安全衛生法
労働災害の防止を目的として主に労働者の安全と健康の確保に関する活動を規定する法律 - 育児・介護休業法
育児・子の看護を行う労働者を支援するために規定する法律 - 男女雇用機会均等法
事業主が母性健康管理の措置を講じる義務を規定する法律
答え2
問題 92 医療計画に含まれないのはどれか
- 保健所の設置
- 在宅医療の確保
- 基準病床数の設定
- 二次医療圏の設定
- 地域医療支援病院の整備
解説:医療計画の記載項目をまとめました。
★医療計画の記載項目
- 二次医療圏の設定
二次医療圏ごとに必要病床数を設定 - 五疾病五事業ごとに、必要な医療機能と各医療機能を担う医療機関の名称を医療計画に記載し、地域の医療連携体制を構築
- 疾病、事業ごとのPDCAサイクルの推進について
- 在宅医療に関わる医療体制の充実・強化について(在宅医療の確保)
- 精神疾患の医療体制の構築について
- 医療従事者の確保に関する事項について
- 災害時における医療体制の見直しについて
- 病院の施設基準を創設
- 医療計画制度の導入
- 特定機能病院の精度化
療養型病床群の精度化 - 診療所への療養型病床群の設置
地域医療支援病院制度の創設
医療計画制度の充実 - 療養病床、一般病床の創設
医療計画制度の見直し - 都道府県の医療対策協議会制度化
医療計画制度の見直し
長々とありますが、保健所の設置は含まれません。
答え1
問題 93 健康診断と根拠法の組合せで正しいのはどれか
- 特定健康診査 労働安全衛生法
- 特殊健康診断 高齢者医療確保法
- 乳幼児健康診査 母子保健法
- 妊産婦健康診査 母体保護法
- 給食従業員の検便 学校保健安全法
解説:設問を正しい組み合わせに直します。
★健康診断と根拠法
- 特定健康診査─高齢者医療確保法
- 特殊健康診断─労働安全衛生法
- 乳幼児健康診査─母子保健法(正)
- 妊産婦健康診査─母子保健法
- 給食従業員の検便─労働安全衛生法
答え3
問題 94 ある疾患の罹患率を調べるために行うのはどれか.
- 横断研究
- 介入研究
- コホート研究
- 症例集積研究
- 症例対照研究
解説:罹患率を調べるとしてコホート研究が最も有名です。解答が2個出てしまうため不適問題になりますが、各研究の説明をしていきます。
★横断研究
ある集団のある一時点での疾病の有無(有病率)と要因の保有状況を同時に調査する。
そのため、たとえ関連が認められたとしてもその要因が疾病の前なのか後なのかが明確ではなく、因果関係を確定することはできない
★介入研究
実験的な予防・治療・介入を受ける介入群と受けない対照群とを設定し、両群のアウトカム(罹患率、死亡率、その他の指標など)の比較によって評価を行う研究
(そのため罹患率を算出することも可能)
★コホート研究(よく出題される)
ある疾患の罹患率を調べるために行う。
- 要因暴露の程度で分けた群を比較する。
- 調査に時間や費用が多くかかる
- 目的以外の疾病の発生も評価できる
- 罹患率が算出できる
- 因果関係の推定が可能
★症例集積研究
ケースシリーズ研究とも呼ばれ、症例を多数集め症例の特徴を明らかにする研究
★症例対照研究は過去の曝露状況を調べる研究方法
- 後向き調査として行われる
- 観察機関が短く、費用もかからない(コホートと比べて)
- 稀な疾患の研究に適している
- 寄与危険度は計算できない
- 因果関係の推定が可能
答え2と3
※厚生労働省の解答:3
国家試験の過去問解説のまとめページです