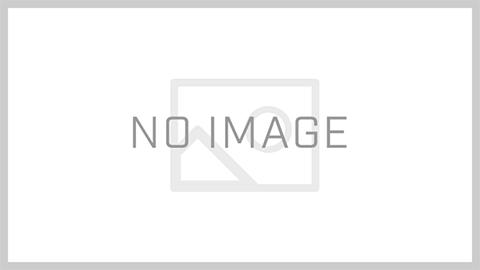学生くん
たんぱく質って何よ!アミノ酸か?SAVASか!?
SAI
・・・(笑)臨床化学のメインどころはTPとALBかな。もちろんアミノ酸もたんぱく質だけど、通常のルーチン検査ではアミノ酸は測定しないからね。
- 項目の学術的説明や測定原理などの細かい所は教科書や参考書を見てくださいね!
ここで書きすぎるとコピー疑いでサイトが抹消されかねないので(笑)
あわせて読みたい
【2020年版】臨床検査技師国家試験にオススメな参考書3選
たんぱく質とは
総蛋白
- TP
- アミノ酸の配列をたんぱく質の一次構造といい、水素結合、疎水結合、イオン結合、ジスルフィド結合などによって2次結合や3次結合(サブユニット)となる
- さらに会合することにより4次構造のたんぱく質(ユニット)が形成される。
代謝
- ほとんどは肝臓で合成される
- 形質細胞ではγ-グロブリン(Mたんぱく)
- 内分泌器官ではペプチドホルモン(C-ペプチドとか)などが生成されている(肝臓ではないよ!)
分析方法
SAI
分析方法は以下の通り多くの種類があって覚えるのが面倒くさい!けど、特にビウレット法は超メジャーな測定法だから覚えておきましょう!社会人になって、TPの測定原理を答えられないとちょい恥ずかしいかも!?(☜恥ずかしい経験済み)
物理的方法
- 比重法
- 屈折率法
- 紫外部吸収法
物理化学的方法
- たんぱく沈殿法
- Kingsbury-Clark法(一般検査でよく使う)
化学的方法
- 含有窒素測定法
- 比色法(ビウレット法)(超重要!!)
- 比色法(Folin-Lowry法)
- 色素結合法
基準範囲
共用基準値
6.6~8.1(g/dL)
臨床的意義
高値
- 多発性骨髄腫(TP10.0↑↑とか結構あります!)
- マクログロブリン血漿(M蛋白)(分画のMピークを見たら納得できる)
- 脱水
- 慢性的な感染症や炎症によるグロブリンの増加
低値
- ネフローゼ症候群(案外多いネフローゼ、ガチでTP下がる)
- 肝機能障害(たんぱく質合成低下)
- 低栄養(アルブミンの減少)
生理的変動要因
- 立位、座位>横臥位(ガチでか!?って正直思う)
- 成人>新生児(筋肉量を考えよう!)
アルブミンとは
アルブミン
- ALB
- 280nmで最大吸収
- 585個のアミノ酸からなる分子量は66458(6万5千)
- 等電点4.8
- 沈殿係数4.4S
- 水溶性たんぱく質
- 栄養源や、コロイド浸透圧の維持及び水分保持
- 酸塩基平衡の維持
- 各種物質の結合及び運搬など(結構重要)
SAI
アルブミンは重要な項目!なぜなら上記のようにたくさんの特徴や役割をもっているから。案外国家試験でも出るし、知っておかないといけない。
分析法
- 色素結合法(BCP改良法が主流)
- 塩析比色法(ぶっちゃけ仕事で使った事ないっす)
SAI
BCG法(ブロムクレゾールグリーン)がアルブミンだけでなく急性相反応蛋白と反応してしまうという問題点に対して、BCP(ブロムクレゾールパープル)を使うようになった!
基準値
共用基準値
4.1~5.1
異常値
- 2.5g/dL以下で浮腫を起こす
臨床的意義
アルブミンの低下
- ネフローゼ症候群
- 蛋白漏出性胃腸炎
- 肝硬変(肝機能の低下)
- 飢餓
A/G比とは
A/G比
- アルブミン/グロブリン比
- アルブミン65%、グロブリン35%が通常
- 基準値は1.1~2.0程度
臨床的意義
A/G比の増加
- 無γ-グロブリン血症
A/G比の減少
- アルブミンの減少
- グロブリンの増加
SAI
A/G比とか計算項目じゃんwとか軽視しがちだけど、案外病態観察には使えるんだよなぁ~。
蛋白分画とは
血清蛋白分画
- 荷電の程度(溶媒のPHやイオン強度、種類によって変わる)
- 蛋白粒子の形状や大きさ、溶媒の粘度によって決まる
- イオン強度が大きい緩衝液⇒移動度が遅くなるが分解能は向上し、ジュール熱も生じる
- イオン強度の小さい緩衝液⇒移動度が速くなり、分解能が低下する
- 緩衝液はベロナール緩衝液(イオン強度0.05、PH8.6)が主流(というかこれしか知らない)
- 支持体(血清たんぱく分画)⇒セルロースアセテート膜(めっちゃ破れやすい)
- 支持体(免疫電気泳動)⇒アガロースゲル(寒天)※ポリアクリルアミドゲルは神経毒があるので注意!
- 染色液⇒(セ・ア膜)ポンソーR
- 脱色⇒酢酸
- 透明化⇒デカリン
SAI
ごめんなさい!めっちゃ多くなった(笑)けど、蛋白分画ってこれくらいは知っておかないと検査でも困るし国家試験でも困るかも!
SAI
余談だけど、蛋白分画は相当にシビアだよ(笑)温度、湿度、風量などでも泳動に影響が出るし、バッファをこまめに変えないと泳動不良を起こすし、白金線もメンテナンスしないと泳動不良を起こす。メンテンナンスに気をめっちゃ使ったのを覚えてます(笑)
基準値
| アルブミン | 51.5~66.8(%) |
| α1-グロブリン | 1.7~2.9(%) |
| α2-グロブリン | 6.5~10.4(%) |
| β-グロブリン | 10.2~15.6(%) |
| γ-グロブリン | 11.3~24.8(%) |
| A/G比 | 1.6~2.4(%) |
臨床的意義
| ネフローゼ症候群、蛋白漏出せい胃腸炎 | γ-グロブリンの低下 |
| 肝硬変、膠原病 | β-γブリッジング |
| 多発性骨髄腫、原発性マクログロブリン血症 | M蛋白の出現 |