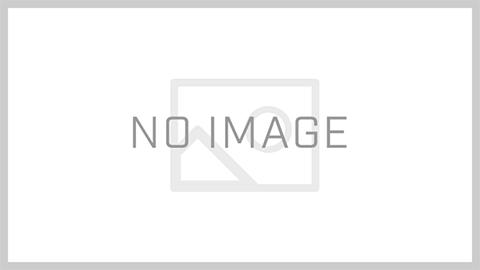過去問は厚労省ホームページより引用しております。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics_150873_139_140.html
基礎的な問題もありますが、比較的意地悪な問題が散見されています。過去類似問題も多いので、今回もしっかり対策をしておきましょう。
第70回臨床化学AM29~44
29 水、10mg/dL標準液、血清の終点分析法における反応終了後の吸光度を測定したところそれぞれ0.02、0.30、0.16であった。血清中に含まれる物質の濃度[mg/dL]で正しいのはどれか。
- 5.0
- 5.2
- 5.4
- 5.6
- 5.8
解説:難しく考えずに、やっていきましょう。何を聞いている問題なのか整理していきましょう。
水(DW)の吸光度が0.02、標準液の吸光度が0.30、検体の吸光度が0.16でした。検体の濃度はいくらか?という問題です。
まず、ブランクの吸光度0.02を、標準液と検体の吸光度からそれぞれ引きます。
つまり、標準液は0.28、検体は0.14となります。
この標準液の濃度が10mg/dLであるので、比の計算で検体は5mg/dLであることがわかります。
一応式で表すと以下の通りです。
0.28:0.14=10:X
0.28X=1.4
X=5
式で考えるより、単純に0.28と0.14で「あ、1/2だな」と考えた方が楽です。
答え:1
30 マグネシウムで正しいのはどれか。
- EDTA加血漿では低値となる。
- 欠乏すると味覚障害を引き起こす。
- 細胞内液より細胞外液に多く含まれる。
- 血清中では90%がイオン型で存在する。
- ホスホリパーゼDを用いた酵素法にて測定される。
解説:採血管と検査項目による組み合わせで、高値や低値になるものがあります。その中で、今回はマグネシウムについて知っていれば簡単に解くことができます。
Mgの様な金属イオンはEDTA採血管で採血をすると、キレート結合をしてしまいます。その結果、異常低値となります。
★抗凝固剤による影響まとめ
- EDTA
低値⇒ALP、Mg、LAP、Fe、Ca、AMY
高値⇒NaもしくはK(EDTA-2NaやEDTA-2K採血管のため) - ヘパリン
低値⇒特になし
高値⇒TP、LDH - クエン酸ナトリウム
低値⇒AMY
高値⇒Na(クエン酸Na) - フッ化ナトリウム
低値⇒ALP、Ca、IP、Mg、LAP、ChE、Fe
高値⇒Na(NaF)
その他の設問を見ていきましょう。
- 欠乏によって味覚障害が生じるのはZn(亜鉛)
- 細胞内液に多く含まれる
- イオン型は約55%である
- ホスホリパーゼDを用いた酵素法にて測定されるのはカルシウムである
味覚異常が亜鉛に影響するのは有名な話ですが、それ以外はややこしい内容であり、マニアックな設問もあります。
細胞内液、外液の箇所もよく出題されるので、今一度おさらいしておきましょう。
★体液の電解質の組成で多く含まれているもの
- 細胞内液
⇒K、Mg2+、HPO42- - 細胞外液
⇒Na+、CL–、HCO3–
答え:1
31 アガロースゲルを用いたリポ蛋白電気泳動で、β位とpreβ位に強い染色像が認められた。WHO脂質異常症タイプ分類で考えられるのはどれか。
- TypeⅠ
- TypeⅡa
- TypeⅡb
- TypeⅣ
- TypeⅤ
解説:難しいです。WHO脂質異常症タイプ分類と、リポ蛋白電気泳動について知っておかないといけません。さらにその鑑別も際どいです。


β位(LDL)とpreβ位(VLDL)に強い染色像は高β、高preβリポ蛋白血症(複合型脂質異常症)を意味するTypeⅡbが該当する。
座学のみの学生ではⅡaとⅡbの鑑別が難しいと思います。
参考までに、βとpreβ分画の増減する疾患をまとめてみました。参考にしてみてください。
・β、preβ分画増加:動脈硬化性疾患、糖尿病、甲状腺機能低下症、ネフローゼ症候群、肝障害、急性膵炎など
・β、preβ分画減少:甲状腺機能亢進症、肝硬変、吸収不全症候群など
ネフローゼだったのかなぁ。と思う問題でした。
答え:3
32 尿素で正しいのはどれか。
- 血中濃度は小児が成人よりも高い。
- ウリカーゼによって加水分解される。
- 消化管出血により血中濃度が減少する。
- 血中非蛋白性窒素の中で最も濃度が高い。
- 生体内でアルドラーゼによって生成される。
解説:選択肢の誤っている箇所を正しい形に直していきます。
- 尿素の血中濃度は成人が高い
- ウリカーゼによって分解されるのは尿酸で、アラントインに分解される
尿素はウレアーゼによって二酸化炭素とアンモニアに分解される - 消化管出血では血中蛋白質が分解されるため血中濃度は増加する
- 生体内ではアルギナーゼによって生成される
アルドラーゼはヒトの生体内に広く分布する解糖系酵素
血中非蛋白性窒素の中で最も濃度が高いのは尿素、その他内訳は
「尿素(8~20mg/dL)>尿酸(3~7mg/dL)>クレアチニン(0.6~1.1mg/dL)>
ビリルビン(0.2~1.0mg/dL)>アンモニア(35~70μg/dL)」となっている。
(基準値を考えると覚えやすいかも)
答え:4
33 AST活性測定用試薬(日本臨床化学会〈JSCC〉勧告法)に含まれないのはどれか。
- NADH
- オキサロ酢酸
- L-アスパラギン酸
- リンゴ酸脱水素酵素
- 2-オキソグルタル酸
解説:難しいというか、こんなの覚えて何になるのか?という問題ですね。
AST試薬における測定原理(JSCC勧告法)です。

※MDH:リンゴ酸脱水素酵素
上式のように、アスパラギン酸を基質としNADHの減少量を測定する測定法です。
この反応式を理解していないと解けない難問です。生化学の授業で見た記憶はあると思いますが笑
オキサロ酢酸は生成物なので、試薬組成には含まれておりません。
答え:2
34 敗血症マーカーはどれか。
- KL-6
- シスタチンC
- プレセプシン
- アンジオテンシン変換酵素〈ACE〉
- N-アセチルグルコサミニダーゼ〈NAG〉
解説:敗血症マーカーで有名なのはPCT(プロカルシトニン)ですが、
プレセプシン(P-sep)も敗血症マーカーとして近年(2002年ころ)発見され、2014年より保険適応となり臨床で多く使われだしたとされています。
特徴として、プロカルシトニンよりも半日~数日も早く陽性を示すことが知られています。
★敗血症マーカー
- PCT(プロカルシトニン)
- P-sep(プレセプシン)
その他の選択肢を見てみます。
- KL-6は間質性肺炎など
- シスタチンCは腎機能評価
- ACEはサルコイドーシスなど
- NAGは尿細管障害のマーカー
答え:3
35 グルコースオキシダーゼ法による血糖測定で利用する酵素はどれか。
- α-アミラーゼ
- α-グルコシダーゼ
- グルコース-6-ホスファターゼ
- マルターゼ
- ムタロターゼ
解説:糖の測定法(酵素法)の一つグルコースオキシダーゼ法についてまとめます。
※酵素法には、GOD法(グルコースオキシダーゼ法)、HK法(ヘキソキナーゼ法)、グルコースデヒドロゲナーゼ法があります。
★GOD法(グルコースオキシダーゼ法)
グルコースは溶液中でα-D-グルコースとβ-D-グルコースの形で平衡状態にある
グルコースオキシダーゼ法は酵素としてβ-D-グルコースオキシダーゼを用いる
この酵素はβ-D-グルコースを基質としてD-グルコン酸とH2O2を生成する

また、β-D-グルコースオキシダーゼはα-D-グルコースには作用しないため、
α-D-グルコースをβ-D-グルコースに変換するムタローゼが利用される。
生成したH2O2量をペルオキシダーゼとo-ジアニシジンなどの呈色試薬を用いて呈色し、測定する。
選択肢は糖に由来する名称の酵素が並んでおり、知っておかないと解けない問題です。
糖の測定でも大事な所なので、理解しておきましょう。
答え:5
36 血中の半減期が最も長いのはどれか。
- ALT
- AST
- CK
- LD5
- α-アミラーゼ
解説:選択肢の半減期をまとめました。
- ALTの半減期は約40~50時間
- ASTの半減期は約5~20時間
- CKの半減期はアイソザイムで異なる
CK-MM約15時間、CK-MB約12時間、CK-BB約3時間 - LDの半減期はアイソザイムで異なる
LD1は約100時間であるがMサブユニットが多くなるほど短くなる特徴があり、LD5では約10時間となる - アミラーゼの半減期は約2~4時間
半減期の問題もたまに見ますので、こうゆうものだと割り切って覚えてしまいましょう。
答え:1
37 ALPで誤っているのはどれか。
- ALP1は閉塞性黄疸で上昇する。
- ALP2はABO血液型の影響を受ける。
- ALP3は小児期に高値を示す。
- ALP4は妊娠後期に上昇する。
- ALP5は食事の影響を受ける。
解説:ALPについての問題です。過去にも出題されている内容だと思います。
その時に作成した表ですが、今回も十分対応可能ですので参考にしてください。

血液型の影響を受けるのはALP5です。また食事の影響というのは「高脂肪食」のことです。
答え:2
38 ペプチドホルモンはどれか。2つ選べ。
- アドレナリン
- アルドステロン
- カルシトニン
- サイロキシン
- 副甲状腺ホルモン〈PTH〉
解説:ホルモンの分類です。選択肢を見てみると
「ペプチドホルモン、アミノ酸誘導体ホルモン、ステロイドホルモン」で分類することができます。選択肢を含めて、代表的なものをまとめてみました。
★ホルモンの種類(化学構造の違い)
- ペプチドホルモン(アミノ酸がつながったもの)
⇒カルシトニン、副甲状腺ホルモン(PTH)、インスリン、グルカゴン、成長ホルモンなど - アミノ酸誘導体ホルモン(アミン(チロシンの誘導体))
⇒アドレナリン、ノルアドレナリン、甲状腺ホルモンなど - ステロイドホルモン(コレステロールから作られるもの)
⇒副腎皮質ホルモン(アルドステロン、アンドロゲン、コルチゾール、コルチゾン)など
ペプチドホルモンは多数あるため、消去法で解くか、こういった問題を網羅的に知識を深めていくかで対応しましょう。
カルシトニンと副甲状腺ホルモンがペプチドホルモンとなります。
答え:3と5
39 260nmが極大吸収波長であるのはどれか。
- DNA
- 尿 酸
- ビリルビン
- ヘモグロビン
- 芳香族アミノ酸
解説:物質の同定に「極大吸収波長」が有効で、その値は決まっています。
したがって、それらを覚えておかないとこの問題は解くことができません。
★極大吸収波長一覧
- DNA:260nm
- 尿 酸:285nm
- ビリルビン:450nm
- ヘモグロビン:410、540、570nm
- 芳香族アミノ酸:200~215、280nm
「核酸は260nm付近に極大吸収ピークを持つ」ということを知っておきましょう。また、第53回と古いですが、尿酸の極大吸収も国家試験に出題されています。
答え:1
40 グルコースのみで構成される二糖類はどれか。
- スクロース
- マルトース
- ラクトース
- ガラクトース
- フルクトース
解説:単糖類、二糖類、多糖類はしっかり把握しておくべきです。
★糖の分類
- 単糖類
五炭糖 ⇒ リボース
六炭糖 ⇒ グルコース(ブドウ糖)、ガラクトース、
フルクトース(果糖)、マンノース - 二糖類
マルトース(麦芽糖):グルコース+グルコース
スクロース(ショ糖):グルコース+フルクトース
ラクトース(乳糖):グルコース+ガラクトース - 多糖類
ホモ多糖類:でんぷん、グリコーゲン、セルロース、アミロース、アミロペクチン ⇒ これらはGluのみが多数縮合したホモ多糖類
ヘテロ多糖類:寒天、アガロース、ヘパリン、ヒアルロン酸、コンドロイチン硫酸
単糖類や二糖類は最低でも把握しておきましょう。マルトースはGlu+Gluの二糖類です。
答え:2
41 解糖系の律速酵素はどれか。
- エノラーゼ
- アルドラーゼ
- イソメラーゼ
- ヘキソキナーゼ
- ホスホグリセリン酸キナーゼ
解説:解糖系の律速酵素は3つ存在する。
★解糖系の律速酵素
- ヘキソキナーゼ
- ホスホフルクトキナーゼ
- ピルビン酸キナーゼ
★糖新生系の律速酵素
- ホスホエノールピルビン酸カルボキシラーゼ
- フルクトースビスホスファターゼ
- グルコース‐6‐ホスファターゼ
解糖系と、ついでに糖新生系の律速酵素を覚えておきましょう。
答え:4
42 構造蛋白質はどれか。
- アルブミン
- コラーゲン
- フィブリノゲン
- セルロプラスミン
- α1-リポプロテイン
解説:構造蛋白とは、簡単に言うと「体を構造する蛋白質」のことです。
毛や爪などを構成する「ケラチン」
骨や皮膚などを構成する「コラーゲン」などを指す。
その他の選択肢を見ると、セルロプラスミン、α1-リポプロテインは輸送蛋白質
フィブリノゲンは血液凝固に関わる蛋白質
アルブミンは輸送や栄養などを担う蛋白質
答え:2
43 半減期3日の放射性同位元素の放射能が1/8になるのはどれか。
- 6日後
- 9日後
- 12日後
- 24日後
- 48日後
解説:半減期の計算は、手順があります。
1/〇の〇をまず2の乗数に直します。今回は1/8なので、1/23になります。
この求めた乗数と、半減期の日数を掛けます。
3(乗数)×3(半減期日)=9
9日を要する。
答え:2
44 血中カルシウムで正しいのはどれか。
- 約30%がイオン型で存在する。
- 基準範囲は3.6~4.4mg/dLである。
- 低アルブミン血症では偽高値を示す。
- アルカローシスではイオン型が低下する。
- 副甲状腺ホルモン〈PTH〉の作用で低下する。
解説:カルシウムについての基礎知識を問う問題です。選択肢を正しいものに直し、まとめ直します。
- 約50~60%がイオン型で存在する
- 基準範囲は8.8~10.1 mg/dL(共用基準値)
- 低アルブミン血症では、低値を示す
- アルカローシスではアルブミンが通常より負に荷電するため、
イオン型カルシウムが蛋白に結合し、結果的に濃度が低下する - 副甲状腺ホルモン(PTH)は血中カルシウムを増加させる
アルカローシスではイオン型が低下するので④が正しい。
答え:4