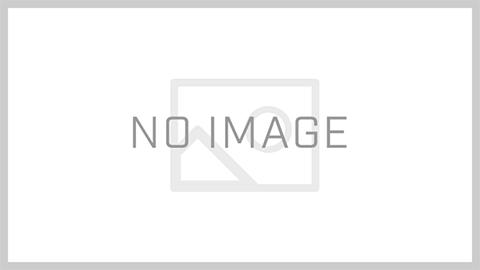はじめに
さい
これから国家試験に挑む方々、日々の勉強、本当にお疲れ様です!
本記事では、第71回国家試験(午前・午後)の問題を徹底的に分析し、近年の出題傾向と、合格を掴むための効果的な学習戦略を詳しく解説します。
「解説を読んでもピンとこない」「どこを重点的に勉強すればいいか分からない」といった悩みを抱える受験生の道しるべとなれば幸いです。
本記事では、第71回国家試験(午前・午後)の問題を徹底的に分析し、近年の出題傾向と、合格を掴むための効果的な学習戦略を詳しく解説します。
「解説を読んでもピンとこない」「どこを重点的に勉強すればいいか分からない」といった悩みを抱える受験生の道しるべとなれば幸いです。
第71回国家試験の3大キーワード:「臨床実践力」「原理原則」「分野横断」
午前午後計200問を全て吟味しました。
第71回の問題を一言で表すなら、「現場で使える知識と思考力」を問う試験であったと言えます。
単なる暗記だけでは太刀打ちできない、より臨床に即した問題が増加しており、以下の3つのキーワードが今後の学習の柱となります。
1. 圧倒的な「臨床実践力」重視の流れ
知識を問うだけでなく、「その知識を使ってどう判断するか」を試す問題が顕著でした。
多角的な判断力:
- パニック値 (AM8, PM(既出)): 数ある異常値の中から、直ちに医師へ報告すべき「緊急事態」を見抜く能力。これは臨床検査技師の最も重要な責務の一つです。ナトリウム175mmol/Lという値を見て、他の異常値との緊急性の違いを即座に判断できるかが問われました。
- コンパニオン診断 (AM1): EGFR変異解析に代表されるように、どの遺伝子変異がどの薬剤の効果予測に繋がるかという、現代医療の最前線で求められる知識が出題されました。
- 緊急報告を要する微生物 (PM77): 血液培養からのA群溶連菌や便からの腸管出血性大腸菌など、検出された場合に患者の生命や公衆衛生に直結する結果を正しく判断できるかが試されました。
精度管理の実践的理解:
- 患者データを用いた精度管理 (AM10): 従来の管理試料を用いる方法に加え、デルタチェックや項目間チェックといった、日々の患者データから異常を検知する実践的な手法が出題されました。
2. 「なぜ?」を問う「原理原則」への深い理解
表面的な暗記では対応できない、技術や現象の根本的な理解を問う問題が目立ちました。
検査法の原理:
- 自動血球計数装置 (PM59, AM63): 電気抵抗法の原理(パルス高=細胞体積)、フローサイトメトリーの原理(前方・側方散乱光)、そして機械の限界(形態異常は判別不可)まで、過去と比べると比較的深く問われていました。
- MALDI-TOF MS (PM44): なぜ真空中でイオンを飛ばすのか(大気圧中では不可)、何に基づいて分離されるのか(質量電荷比)といった、分析機器の根本原理の理解が必須でした。
病態生理との連携:
- クロスミキシング試験 (PM61): APTTが延長した際に、なぜ正常血漿を混ぜるのか。
その結果が「補正される(因子欠乏)」、「補正されない(インヒビターの存在)」というパターンに分かれる理由を理解していなければ解けない良問です。 - コールドアクチベーション (PM82): なぜ血清CH50は低値になり、EDTA血漿では正常範囲になるのか。低温と補体、抗凝固剤の相互作用というメカニズムの理解が問われました。
3. 知識をつなぐ「分野横断」的な視点
一つの科目に閉じず、複数の分野の知識を統合して答えを導き出す問題が増加しています。
- 臨床データと遺伝子異常の連携 (PM64): 血液データと末梢血像からCMLを想起し、そこからt(9;22)フィラデルフィア染色体という細胞遺伝学の知識を引き出す応用的な問題の代表例です。
- 貧血の鑑別と追加検査 (AM60): 赤血球恒数を計算し(臨床化学、血液学)、大球性貧血と分類し(血液学)、その原因検索として葉酸の測定を選択する(生化学)、という複数のステップと思考が求められました。
- 血液型と腫瘍マーカー (PM84): Lewis血液型がLe(a-b-)の場合、糖鎖抗原であるCA19-9が産生されないという、輸血免疫学と臨床化学(腫瘍マーカー)を結びつける高度な知識が問われました。(ある意味嫌がらせの領域)
過去問との比較と今後の対策
第71回の試験は、過去問の知識がベースになっている一方で、その応用力や深い理解度を試す方向にシフトしています。
- 過去問の焼き直しではない: 過去に出題されたキーワード(例:クロスミキシング試験、コンパニオン診断)でも、問う角度を変えたり、より深い原理の理解を求めたりしています。過去問の答えを丸暗記するだけでは通用しづらくなっています。
- 「なぜそうなるのか」を常に問う: 学習の際は、一つの事象に対して常に「なぜ?」「どういうメカニズムで?」と自問自答する癖をつけましょう。
例えば、「CMLといえばPh染色体」と覚えるだけでなく、「Ph染色体によってBCR-ABL融合遺伝子が形成され、恒常的に活性化するチロシンキナーゼが細胞を異常増殖させる」というストーリーで理解することが重要です。→全ての分野でそうゆう学習の癖をつけるべき。 - 図表や画像に強くなる: 教科書や参考書の図・写真をただ眺めるのではなく、「この所見は何を意味するのか」「正常とどこが違うのか」を自分の言葉で説明する訓練をしましょう。友人と問題を出し合うのも効果的です。
まとめ:合格への道筋
第71回国家試験を解いてみて、明らかに感じたことがあります。
それは、今後活躍すべき「考える力を持った臨床検査技師」を求めているということです。これからの国家試験対策は、以下の3本柱で進めることが合格への最短ルートとなるでしょう。
- 基礎知識の徹底: 全ての応用問題は、強固な基礎知識の上に成り立っています。各分野の重要語句、基準値、原理は確実に暗記しましょう。
- 関連付け学習の実践: 分野の壁を越えて知識を繋げる練習をしましょう。一つの疾患を学ぶ際には、関連する検査、病態生理、画像所見などをノートにまとめるのがおすすめです。
- 過去問の深掘り: 正解を導くだけでなく、全ての選択肢について「なぜ正しいのか」「なぜ誤っているのか」を完璧に説明できるまで繰り返し演習しましょう。
さい
皆さんの努力が実を結ぶことを心から応援しています。