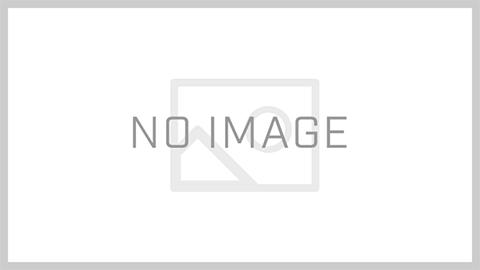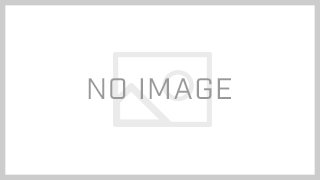【国試対策】髄液・穿刺液検査は1記事でOK!
漏出液と滲出液の違いがわかる過去問8問を徹底解説
今回は、体の奥深くからのメッセージである「髄液・穿刺液検査」について解説していきます。
📝 引用元について
この記事で解説している国家試験の問題文は、厚生労働省のウェブサイトで公開されているものを、学習目的で引用しています。(医療トピックス一覧に国家試験過去問のリンクがあります)
けど、「漏出液と滲出液の違い」と「髄膜炎の病態」をマスターすれば、国試の問題は必ず解けるようになります👍
漏出液 vs 滲出液:胸水・腹水・関節液の基本
胸水や腹水、関節液などの体腔液が異常に溜まった時、その液体が「漏出液」なのか「滲出液」なのかを鑑別することは、原因疾患を探る上で非常に重要です。国試では、この鑑別基準が繰り返し問われます。
漏出(ろうしゅつ)液 (Transudate)
💧
原因:非炎症性(心不全、肝硬変、ネフローゼなど)
メカニズム:圧力のバランスが崩れ、血管から水分だけが「漏れ出た」水っぽい液体。
滲出(しんしゅつ)液 (Exudate)
🔥
原因:炎症性(がん、結核、肺炎、関節リウマチなど)
メカニズム:炎症で血管の壁が壊れ、水分と一緒にタンパク質や血球が「滲み出た」ドロっとした液体。
「漏出液=水っぽい」「滲出液=ドロっとしている」と覚えておけば、鑑別基準は自然と頭に入ってきます。
漏出液 vs 滲出液 鑑別基準(Lightの基準など)
| 項目 | 💧 漏出液 (水っぽい) | 🔥 滲出液 (ドロっとしている) |
|---|---|---|
| 外観 | 淡黄色透明 | 混濁、膿性、血性など |
| 比重 | < 1.015 | > 1.018 |
| タンパク質 | < 2.5 g/dL | > 3.0 g/dL |
| LDH | 低値 | 高値 |
| 細胞数 | 少ない (主にリンパ球) | 多い (原因により好中球など) |
| リバルタ反応 | (-) | (+) |
国試で使える語呂合わせ
比重の境界線は 1.015
覚え方:「比重は“ヒーヒーゴー(1.015)”」
タンパク質の境界線は 3.0 g/dL
覚え方:「タンパク質は“プロ”テイン、“プロ(Pro)”は“さん(3)”付け」
【第67回 午後 問6 / 第69回 午後 問7 / 第71回 午後 問2】漏出液と滲出液の鑑別問題
【第67回】漏出性腹水に合致する所見はどれか。
- 1.混濁
- 2.pH 7.20
- 3.比重 1.026
- 4.LD 480 U/L
- 5.蛋白 1.8 g/dL
【第69回】滲出性胸水の所見はどれか。
- 1.無色透明
- 2.比重 1.010
- 3.細胞数 50/μL
- 4.LD比(胸水/血清)0.8
- 5.蛋白比(胸水/血清)0.2
【第71回】滲出液と比較して漏出液で高値を示すのはどれか。
- 1.LD
- 2.蛋白
- 3.比重
- 4.細胞数
- 5.グルコース
ここをクリックして答えと解説を見る
【67回】正解:5
【69回】正解:4
【71回】正解:5
「漏出液=水っぽい=タンパクや細胞が少ない」「滲出液=ドロっとしている=タンパクや細胞が多い」という原則で解いていきましょう!
【67回】漏出液(水っぽい方)に合うのは?
選択肢の中で、唯一「水っぽい」特徴を示しているのは「5.蛋白 1.8 g/dL」(基準の2.5 g/dLより低い)ですね。他はすべて滲出液の特徴です。
【69回】滲出液(ドロっとしている方)に合うのは?
「4.LD比(胸水/血清)0.8」が正解です。これはLightの基準の一つで、胸水/血清のLD比が0.6を超えると滲出液と判断します。他の選択肢はすべて漏出液の特徴です。
【71回】漏出液で「高値」を示す珍しい項目は?
これは少しひねった問題ですね。基本的に漏出液は成分が薄いですが、唯一、滲出液より高値を示す可能性があるのが「5.グルコース」です。
滲出液の原因となる炎症(特に細菌感染やがん)では、集まってきた白血球やがん細胞がエネルギー源としてグルコースを消費します。そのため、滲出液中のグルコース濃度は、血液中よりも低くなることが多いのです。
一方、漏出液ではグルコースの消費がないため、血漿中の濃度とほぼ同じ値を保ちます。結果として、滲出液に比べて漏出液の方がグルコース濃度が相対的に高くなることがある、というわけです。
【第68回 午後 問5】関節液の異常所見
関節液の異常所見はどれか。
- 1.淡黄色透明
- 2.比重 1.010
- 3.細胞数 50/μL
- 4.好中球比率 10%
- 5.蛋白濃度 3.5 g/dL
ここをクリックして答えと解説を見る
正解:5
まずは、その基準値を見てみましょう。
正常関節液の基準値
| 項目 | 基準値 |
|---|---|
| 外観 | 無色~淡黄色透明 |
| 粘稠性 | 高い(ヒアルロン酸に富む) |
| 比重 | 1.008~1.015 |
| タンパク濃度 | 1.0~2.0 g/dL |
| 細胞数 | 200/μL 未満 |
| 白血球分画 | 単核球主体(好中球 < 25%) |
正常と異常の境界線
上の表を見て分かる通り、正常な関節液は、無色透明で粘稠性が高く、細胞数やタンパク質は非常に少ないです。つまり、正常な関節液は「漏出液」に近い性状をしています。
関節リウマチや痛風、感染性関節炎などの炎症が起きると、関節液は「滲出液」に変化し、混濁して細胞数やタンパク質が増加します。
各選択肢の評価
- 5.蛋白濃度 3.5 g/dL → ○ (異常):基準値(1.0~2.0 g/dL)を大きく超えており、明らかに滲出液性の異常所見です。
- 1.淡黄色透明 → × (正常):正常な外観です。
- 2.比重 1.010 → × (正常):基準値(1.008~1.015)の範囲内です。
- 3.細胞数 50/μL → × (正常):基準値(200/μL未満)を下回っています。
- 4.好中球比率 10% → × (正常):基準値(25%未満)を下回っています。
【第67回 午後 問9 / 第68回 午前 問6 / 第69回 午後 問2 / 第70回 午後 問7】髄膜炎の鑑別問題
【第67回】健常成人の脳脊髄液について正しいのはどれか。
ここをクリックして問題と解説を見る
髄膜炎の鑑別 早見表
| 項目 | 正常 | 細菌性(化膿性) | 結核性 | ウイルス性 |
|---|---|---|---|---|
| 外観 | 水様透明 | 混濁・膿性 | キサントクロミー | 水様透明 |
| 細胞数 | 0-5/μL (リンパ球) | 著増 (好中球↑↑) | 中等度増 (リンパ球↑) | 軽度増 (リンパ球↑) |
| タンパク | 15-45 mg/dL | 著増 (100↑) | 中等度増 | 正常~軽度増 |
| 糖 | 血糖の2/3程度 | 著減 | 減少 | 正常 |
| Cl | 血清より高値 | 減少 | 著減 | 正常 |
特に、細菌や結核菌は糖を消費するので「糖が下がる」、炎症でタンパクが増える、というポイントを押さえるのが重要です。
キサントクロミーとは、本来は無色透明であるはずの脳脊髄液(髄液)が、黄色〜淡黄色、あるいはピンク色を呈する状態を指します。
ギリシャ語で、Xantho(キサント) = 黄色、-chromia (クロミー) = 「色」
これは、髄液中に出血が起こり、数時間以上経過した赤血球が壊れ、中のヘモグロビンがビリルビン(黄色い色素)に分解されることで生じます。
臨床的意義
キサントクロミーの有無は、「本物の脳内出血(くも膜下出血など)」と「採血時の失敗(外傷性穿刺)」を鑑別するための極めて重要な所見です。遠心して上清が黄色ければ、それは採血する前にすでに出血が起きていた証拠となります。
※結核性髄膜炎のように、タンパク濃度が著しく高い場合にも、髄液は淡黄色を呈することがあります。
【第67回】健常成人の脳脊髄液について正しいのはどれか。
- 1.色調は黄色である。
- 2.糖濃度は血漿の約10%である。
- 3.蛋白濃度は血清の約10%である。
- 4.細胞成分はリンパ球が主体である。
- 5.クロール濃度は血清より低値である。
正解:4
表の「正常」の欄を見れば一目瞭然ですね。正常髄液の細胞はごくわずかですが、そのほとんどはリンパ球です。
【第68回】化膿性髄膜炎を疑う髄液所見として誤っているのはどれか。
- 1.混濁
- 2.LDの上昇
- 3.蛋白濃度の上昇
- 4.多形核球比率の上昇
- 5.髄液糖/血糖比の上昇
正解:5
化膿性(細菌性)髄膜炎では、細菌が糖を消費するため、髄液の糖は著しく低下します。したがって「髄液糖/血糖比」は低下します。
【第69回】結核性髄膜炎において、髄液の測定値が低値となるのはどれか。2つ選べ。
- 1.圧
- 2.糖
- 3.蛋白
- 4.クロール
- 5.アデノシンデアミナーゼ
正解:2, 4
表の「結核性」の欄を見てください。結核性髄膜炎では、糖の減少と、特にクロールの著しい減少が特徴的です。ADA(アデノシンデアミナーゼ)は高値となります。
【第70回】結核性髄膜炎でみられる脳脊髄液所見はどれか。
- 1.膿性
- 2.Cl濃度低下
- 3.蛋白細胞解離
- 4.血糖と同程度の糖濃度
- 5.好酸球優位の細胞増多
正解:2
これも同じ知識を問う問題ですね。結核性髄膜炎のキーワードは「クロール(Cl)低下」と「リンパ球優位の細胞増多」です。
ちなみに「蛋白細胞解離(細胞数が増えずに蛋白だけが著増する)」はギラン・バレー症候群の特徴的な所見です。
まとめ
お疲れ様でした!髄液・穿刺液検査はいかがだったでしょうか?細かい数値の暗記は苦労しますが、ポイントをしっかり押さえれば、もう怖くありません。
- 漏出液か滲出液か、それが問題だ:「漏出液=水っぽい=非炎症性」、「滲出液=ドロっとしている=炎症性」というイメージがすべての基本。比重、タンパク、細胞数、リバルタ反応で鑑別する。
- グルコースは消費される:滲出液(特に細菌感染)では、細胞がグルコースを消費するため濃度が下がる。これが、漏出液の方が相対的にグルコースが高くなる理由。
- 髄膜炎は表で覚える:「細菌性=好中球↑↑、糖↓↓」、「結核性=リンパ球↑、糖↓、Cl↓↓」、「ウイルス性=リンパ球↑、糖→」。この3つのパターンの違いを明確に!