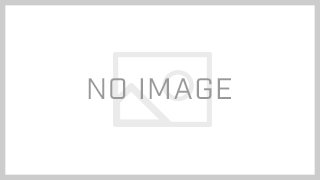臨床検査技師国家試験第71回(午前)の解説を作成してみました。
こんな悩みを解決します
「市販の過去問集は解説がシンプルすぎて、なぜそうなるのか分からない…」
「一つひとつ調べながら勉強すると、膨大な時間がかかってしまう…」
「1問から関連知識を広げて、効率よく学習したい!」
この記事は、かつて国試勉強で私自身が抱えていた悩みを解決し、皆さんの学習を徹底的にサポートするために作成しています。
スクロールが非常に面倒だと思い、改良できる箇所はしていこうと思います。
(プログラムは調べながらなのでうまくいかないかもですが汗)
問題は厚労省ホームページより引用しております。https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp250428-07.html
なるべく間違いのないように何度も見直しをしていますが、もし間違いがあった場合は連絡フォームより教えていただくか、X のDMにて教えていただけますと幸いです。
第71回(AM)臨床検査総論(1〜10)
▼ クリックすると詳細が開きます
1 コンパニオン診断に用いられるのはどれか。
- PSA
- 血小板凝集能
- EGFR変異解析
- 75g経口グルコース負荷試験
- T細胞サブセット〈CD4/CD8〉
★コンパニオン診断とは
- 患者に対する薬の効果や副作用を予測し、最適な治療法を選択するための検査です。
- 個別化医療(Precision Medicine)を実現するための重要なツール。
- 特に分子標的薬とセットで開発されることが多い。
検査法
- PCR法(リアルタイムPCRなど)
- シーケンス解析(サンガーシーケンス、次世代シーケンスなど)
- 蛍光in situハイブリダイゼーション(FISH法)
- 免疫組織化学染色(IHC法)
遺伝子変異の検出
- EGFR遺伝子変異(上皮成長因子受容体遺伝子変異)
対象疾患: 非小細胞肺がん - ALK融合遺伝子(未分化リンパ腫キナーゼ融合遺伝子)
対象疾患: 非小細胞肺がん - BRAF遺伝子変異(V600Eなど)
対象疾患: 悪性黒色腫、非小細胞肺がん、大腸がんなど - HER2遺伝子変異(HER2増幅・過剰発現)
対象疾患: 乳がん、胃がんなど
たんぱく質発現の検出
- PD-L1発現
対象疾患: 非小細胞肺がん、悪性黒色腫、腎細胞がんなど
選択肢の中で、これに該当するのはEGFR変異解析です。
EGFR変異解析は、非小細胞肺がんの治療薬であるEGFRチロシンキナーゼ阻害薬(TKI)の投与対象となる患者さんを特定するために行われる代表的なコンパニオン診断です。
EGFR遺伝子に変異がある場合に、これらの薬剤が効果を発揮するとされています。
他の選択肢を見てみます。
- PSA(前立腺特異抗原)
前立腺がんのスクリーニングや経過観察に用いられる腫瘍マーカーですが、特定の薬剤の適応を判断するコンパニオン診断ではありません。 - 血小板凝集能
出血傾向や血栓症のリスクを評価する検査であり、コンパニオン診断には直接関係ありません。 - 75g経口グルコース負荷試験:
糖尿病の診断や耐糖能異常の評価に用いられる検査であり、コンパニオン診断ではありません。 - T細胞サブセット〈CD4/CD8〉
免疫機能の評価やHIV感染症の経過観察などに用いられる検査であり、コンパニオン診断ではありません。
答え:3
2 混濁尿は透明化処理で鑑別が可能である。処理方法と対象となる混濁の原因の組合せで正しいのはどれか。
- 加 温 細 菌
- 3%酢酸 リン酸塩
- 10%塩酸 尿酸塩
- 10%水酸化カリウム 脂 肪
- アルコール・エーテル混合液(2:1) シュウ酸塩
尿沈渣における結晶の鑑別方法です。下に表にしました。
★結晶・塩類の鑑別方法
| 結晶 | 酢酸 | 塩酸 | KOH | クロロホルム | pH | 加温 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シュウ酸Ca結晶 | (-) | (-) | (+) | (-) | アルカリ性~酸性 | 不変 |
| 尿酸塩 | (-) | (+) | (-) | (-) | 弱酸性 | 溶解 |
| 尿酸結晶 | (-) | (+) | (-) | (-) | 酸性 | 溶解 |
| リン酸塩 | (+) | (+) | (-) | (-) | 中性~アルカリ性 | 不変 |
| リン酸Ca結晶 | (+) | (+) | (-) | (-) | 中性~アルカリ性 | 不変 |
| リン酸アンモニウムMg結晶 | (+) | (+) | (-) | (-) | 中性~アルカリ性 | 不変 |
| 尿酸アンモニウム結晶 | (+) | (+) | (-) | (-) | 中性~アルカリ性 | 溶解 |
| 炭酸Ca結晶 | (+) 気泡 | (+) 気泡 | (-) | (-) | 中性~アルカリ性 | 不変 |
| ビリルビン結晶 | (-) | (-) | (+) | (+) | 中性~酸性 | 不変 |
| コレステロール結晶 | (-) | (-) | (+) | (+) | 中性~酸性 | 溶解 |
| シスチン結晶 | (-) | (+) | (+) | (-) | 酸性 | 溶解 |
| 2,8-DHA結晶 | (-) | (-) | (+) | (-) | 中性~酸性 | 不変 |
-
酢酸・塩酸で「気泡」が出る=炭酸塩系(炭酸Caなど)
-
クロロホルムに溶けるのは脂溶性物質(ビリルビン、コレステロールなど)
-
加温で溶ける=尿酸、シスチン、コレステロール など一部
-
pHによる存在領域の把握も重要(尿酸=酸性、リン酸塩=アルカリ性)
表よりほとんどの結晶を鑑別することができます。
- 加温で消失すれば尿酸塩
- 3%酢酸で気泡を生じて消失すれば炭酸塩
- 気泡を生じずに消失すればリン酸塩
- 10%塩酸で消失すればシュウ酸カルシウム
- 10%水酸化カリウムで消失すれば尿酸結晶
→膠状になれば膿汁 - アルコール・エーテル混合液 (2:1) で消失すれば脂溶性のコレステロール結晶、ビリルビン結晶が考えられる
正しい組み合わせは酢酸添加でリン酸塩は溶解になります。
答え:2
3 DNA合成酵素はどれか。
- リガーゼ
- ヘリカーゼ
- イソメラーゼ
- ポリメラーゼ
- エンドヌクレアーゼ
各酵素についてまとめます。
★DNA合成酵素とは
DNAの鋳型をもとに新しいDNA鎖を合成する酵素の総称。
この機能を持つ酵素は、細胞分裂時のDNA複製や、DNA損傷の修復など、生命活動において非常に重要な役割を担っている。
★DNA複製に関わる主要な酵素群とその機能
- DNAヘリカーゼ (Helicase)
- DNA二重らせんの水素結合を切断し、DNAを一本鎖にほどく。
- DNAプライマーゼ (Primase)
- DNA複製開始点に短いRNAプライマーを合成するRNAポリメラーゼの一種。
- DNAポリメラーゼ (DNA Polymerase)
- DNAポリメラーゼは、DNAを鋳型として、それに相補的な塩基配列を持つDNA鎖を合成する酵素。DNAの複製や修復の中心的な役割を担う。
- RNAプライマーの除去とDNAへの置換
(原核生物ではDNAポリメラーゼIが、真核生物ではDNAポリメラーゼδ/εが主に関与)
- DNAリガーゼ (Ligase)
- DNA鎖のニック(切れ目)をリン酸ジエステル結合で連結する。
特にラギング鎖の岡崎フラグメントの結合に重要。
- DNA鎖のニック(切れ目)をリン酸ジエステル結合で連結する。
- トポイソメラーゼ (Topoisomerase)
- DNAの超らせん構造を解消・調節する。
複製フォーク前方のねじれを解消する。
- DNAの超らせん構造を解消・調節する。
上記よりDNAポリメラーゼが該当する。
上記を参考に他の選択肢を見てみます。
- リガーゼ(DNAリガーゼ)
→DNA断片とDNA断片の間、またはDNA鎖の切れ目をリン酸ジエステル結合で連結する酵素です。DNAの合成ではなく、結合に関わります。 - ヘリカーゼ(DNAヘリカーゼ)
→DNAの二重らせん構造をほどき、一本鎖に分離する酵素です。
DNAの合成の前にDNAを開く役割があります。 - イソメラーゼ(DNAトポイソメラーゼ)
→DNAの超らせん構造を解消したり、ねじれを調整したりする酵素です。(異性体に転換)
DNAの合成そのものではなく、DNAの構造変化に関わります。 - エンドヌクレアーゼ
→DNA鎖の内部のホスホジエステル結合を切断する酵素です。
DNAの損傷修復や、遺伝子組換え技術などで用いられます。
上記より、DNA合成酵素はポリメラーゼとなります。
答え:4
4 虫卵で小蓋がないのはどれか。
- 回 虫
- 肝 蛭
- 肝吸虫
- 日本住血吸虫
- 日本海裂頭条虫
解説:小蓋(Operculum)とは、主に吸虫や一部の条虫の卵に見られる特徴的な構造で、卵の殻の一端にある蓋状の部分のこと
★寄生虫卵の鑑別表:小蓋の有無と特徴
| 寄生虫名 | 小蓋の有無 | 卵の主な特徴 |
|---|---|---|
| 小蓋を持たないもの | ||
| 回虫 | なし | 卵形/広楕円形、厚い卵殻、 乳頭状(受精卵) または細長滑面(不受精卵)。 |
| 鞭虫 | なし | レモン形/樽形、両端に栓状の極栓(小蓋ではない)、厚い卵殻。 |
| 鉤虫 | なし | 楕円形、薄い卵殻、内部に2~8細胞期の胚。 |
| 東洋毛様線虫 | なし | 鉤虫卵に似るがやや大きく細長い楕円形、内部の胚はより進んでいる。 |
| 蟯虫 | なし | 左右非対称のD字形、薄い卵殻、内部に幼虫。 |
| 日本住血吸虫 | なし | ほぼ球形/広楕円形、薄い卵殻、側方に小さな棘。 内部にミラシジウム。 |
| マンソン住血吸虫 | なし | 楕円形、薄い卵殻、側棘が大きく突出。 内部にミラシジウム。 |
| ビルハルツ住血吸虫 | なし | 楕円形、薄い卵殻、末端に棘。内部にミラシジウム。 |
| 有鉤条虫/無鉤条虫 | なし | ほぼ球形、厚い放射状線条のある卵殻、内部に六鉤幼虫(六鉤子)。形態的に区別不能。 |
| 糞線虫 | なし | 通常、便中に卵は排出されず、桿状食道型幼虫が検出される。 |
| 小蓋を持つもの | ||
| 肝吸虫 | あり | 洋梨形、肩隆部、小さい小蓋。内部にミラシジウム。 |
| 広節裂頭条虫 | あり | 楕円形、鑑別が難しい不明瞭な小蓋と反対側にボタン状突起。 |
| 横川吸虫 | あり | 小さな米粒形、明瞭な小蓋。 |
| 肺吸虫(ウェステルマン肺吸虫) | あり | 広楕円形、厚い卵殻、明瞭な小蓋、卵殻肥厚。 |
| 肥大吸虫 | あり | 楕円形、明瞭な小蓋。 |
| 肝蛭 | あり | 大型、卵形、明瞭な小蓋、平滑な卵殻。 |
★補足
- 極栓と小蓋の違い: 鞭虫卵の「極栓」は、卵の内容物が排出される際に開く「小蓋」とは異なる構造です。国家試験ではこの違いが問われることがあります。
- 住血吸虫卵の棘: 住血吸虫の卵は小蓋を持たず、その代わりに棘の位置(側棘、末端棘)が重要な鑑別点となります。
表より1と4が正解となります。複数の答えがあり問題としては不適です。
それぞれの選択肢について簡単に説明します。
- 肝蛭(肝蛭卵): 小蓋があります。比較的大きく、淡黄褐色です。
- 肝吸虫(肝吸虫卵): 小蓋があります。小型で、肩部が目立つのが特徴です。
- 日本住血吸虫(日本住血吸虫卵): 小蓋がありません。 卵殻は薄く、側方に突出した棘(側棘)があるのが特徴です。
- 日本海裂頭条虫(日本海裂頭条虫卵): 小蓋があります。楕円形で、淡黄褐色です。
答え:1と4
5 Lambl(ランブル)鞭毛虫の主な寄生部位はどれか。
- 胃
- 肺
- 大 腸
- 脳脊髄
- 十二指腸
ランブル鞭毛虫の寄生部位についての出題です。知っておけば楽勝ですね。
ランブル鞭毛虫(Giardia intestinalis)は、消化管に寄生する原虫で、主に十二指腸から空腸上部にかけて寄生する。
この寄生により、下痢、腹痛、膨満感などの症状を引き起こす。
上記より、ランブル鞭毛虫は十二指腸〜空腸にかけて寄生する。選択肢は十二指腸のみあるので、それが回答となります。
★参考(選択肢の関連する寄生虫)
| 選択肢(寄生部位) | 代表的な寄生虫 |
|---|---|
| 胃 | アニサキス |
| 肺 | ウェステルマン肺吸虫 |
| 大腸 | 赤痢アメーバ、鞭虫 |
| 脳脊髄 | 有鉤条虫 |
| 十二指腸 | Lambl鞭毛虫 |
参考までに覚えておくといいかもしれません。
答え:5
6 腟トリコモナス症で誤っているのはどれか。
- 尿沈渣で虫体が検出される。
- 栄養型による接触感染である。
- 腟分泌物から囊子が検出される。
- 患者とパートナーを同時に治療する。
- 塗抹標本ではGiemsa染色が用いられる。
膣トリコモナス症についてまとめてみました。
★腟トリコモナス症の主な特徴
腟トリコモナス症は、原虫の一種である腟トリコモナス(Trichomonas vaginalis)によって引き起こされる性感染症です。
- 原因微生物: 腟トリコモナス(Trichomonas vaginalis)という原虫。
- 形態: 栄養型のみで、囊子(シスト)は形成しません。この点が、アメーバなど他の原虫との大きな違いです。
- 感染経路: 主に性行為による接触感染です。まれにタオル、浴槽などを介した感染も報告されています。
- 症状
- 女性: 泡状で悪臭を伴う黄緑色の帯下、外陰部の掻痒感、灼熱感、性交時痛、排尿時痛など。無症状のキャリアも多いです。
- 男性: 無症状が多いですが、軽度の尿道炎を起こすこともあります。
- 診断
- 腟分泌物や尿の直接鏡検(生食液塗抹): 運動性のある栄養型虫体の確認が最も簡便で確実な診断法です。
- 塗抹標本の染色: ギムザ(Giemsa)染色などで染色し、虫体の形態を確認します。
- 治療
- メトロニダゾールなどのニトロイミダゾール系薬剤が第一選択薬です。内服薬が一般的です。
- 患者本人だけでなく、性行為のパートナーも同時に治療することが極めて重要です(ピンポン感染の防止)。これは性感染症全般に言えることですが、特に強調されます。
- 尿沈渣で虫体が検出される。
正しい。 腟トリコモナスは女性の腟だけでなく、男性の尿道にも感染することがある。
尿道感染の場合、尿沈渣中にトリコモナス(栄養型)が検出されることがある。
- 栄養型による接触感染である。
正しい。 腟トリコモナスは、主に性行為による直接的な接触感染で広がる。
また、その感染形態は「栄養型」のみであり、病原性を持つのはこの形態。
- 腟分泌物から囊子(のうし)が検出される。
誤り。 腟トリコモナス(Trichomonas vaginalis)は、嚢子を形成しない原虫。
常に栄養型として存在し、この栄養型が感染源となります。
- 患者とパートナーを同時に治療する。
正しい。 腟トリコモナス症は性感染症であり、パートナー間で「ピンポン感染」を起こしやすい。
再感染を防ぎ、治療を成功させるためには、患者本人だけでなく、パートナーも同時に治療することが重要。
- 塗抹標本ではGiemsa染色が用いられる。
正しい。 腟トリコモナスの検出には、腟分泌物や尿沈渣を塗抹し、顕微鏡で観察する直接鏡検がよく用いられます。
この際、Giemsa(ギムザ)染色や尿沈渣のステルンハイマー染色(Sternheimer)染色などによって染色することで、虫体の形態が明瞭になり、鑑別がしやすくなります。新鮮な検体であれば、運動性の有無も診断の助けになります。
答え:3
7 条虫で正しいのはどれか。
- 雌雄異体である。
- 消化管を有する。
- 神経細胞はない。
- 中間宿主内で増殖する。
- 頭部、頸部、片節の3部位からなる。
以下に各選択肢の解説をします。
- 雌雄異体である。
- 条虫は基本的に雌雄同体。一つの片節内に雄性生殖器と雌性生殖器の両方を持っている。(ただし、有節条虫類に限る)
→雌雄異体なのは、住血吸虫などの吸虫類の特徴。
- 条虫は基本的に雌雄同体。一つの片節内に雄性生殖器と雌性生殖器の両方を持っている。(ただし、有節条虫類に限る)
- 消化管を有する。
- 条虫は消化管を持たず、体表から栄養を吸収する。これは、宿主の消化管内で栄養が豊富にある環境に適応した特徴。
- 神経細胞はない。
- 条虫には神経節(脳のようなもの)と神経索(神経細胞の集まり)が存在する。
特に頭部に神経節が集中しており、そこから体全体に神経が伸びている。
- 条虫には神経節(脳のようなもの)と神経索(神経細胞の集まり)が存在する。
- 中間宿主内で増殖する。
- 条虫は中間宿主内で幼虫が発育するが、増殖(個体数を増やすこと)はしない。
増殖は通常、終宿主の消化管内で成虫が卵を産むことで行われる。
- 条虫は中間宿主内で幼虫が発育するが、増殖(個体数を増やすこと)はしない。
- 頭部、頸部、片節の3部位からなる。
条虫の成虫は
- 頭部(scolex): 宿主の腸壁に吸着するための吸盤や鉤(かぎ)を持つ。
- 頸部(neck): 片節を新しく形成する増殖帯。
- 片節(proglottid): 多数連なった体の部分で、それぞれに生殖器官を持つ。
の3つの主要な部位から構成されている。
答え:5(厚労省)
8 パニック値対応となるのはどれか。
- ALP 300U/L
- カルシウム 10.8mg/dL
- グルコース 200mg/dL
- ナトリウム 175mmol/L
- 総コレステロール 300mg/dL
臨床検査値の共用基準範囲(共用基準値)を参考までに載せておきます。
【参照:臨床検査値の共用基準範囲(共用基準値)2022年10月改定版】
åhttps://www.jccls.org/wpcontent/uåploads/2022/10/kijyunhani20221031.pdfこの基準値は、日本臨床検査医学会と日本臨床化学会が共同で設定したもので、成人(空腹時)を対象とした一般的な目安です。
注:基準範囲は検査方法や対象集団(年齢、性別、生活習慣等)により変動する可能性があります。必ずしもこの範囲外の数値が異常を意味するわけではありません。
| 検査項目 | 単位 | 基準範囲 | 備考(参考情報) |
|---|---|---|---|
| 血糖 | mg/dL | 73-109 | 空腹時血糖 |
| HbA1c | % | 4.9-6.0 | NGSP値 |
| 総コレステロール | mg/dL | 142-248 | |
| HDLコレステロール | mg/dL | 男性:38-90 女性:48-103 |
|
| LDLコレステロール | mg/dL | 65-163 | |
| 中性脂肪 | mg/dL | 男性:40-234 女性:30-117 |
空腹時 |
| AST(GOT) | U/L | 10-30 | |
| ALT(GPT) | U/L | 男性:10-42 女性:7-23 |
|
| γ-GT | U/L | 男性: 13-64 女性: 9-32 |
|
| ALP | U/L | JSCC:106-322 IFCC:38-113 |
|
| LDH | U/L | 124-222 | |
| ChE | U/L | 男性:240-486 女性:201−421 |
|
| 総蛋白 | g/dL | 6.6-8.1 | |
| アルブミン | g/dL | 4.1-5.1 | |
| 総ビリルビン | mg/dL | 0.4-1.5 | |
| 尿素窒素 (BUN) | mg/dL | 8-20 | |
| クレアチニン | mg/dL | 男性: 0.65-1.07 女性: 0.46-0.79 |
|
| 尿酸 | mg/dL | 男性: 3.7-7.8 女性: 2.6-5.5 |
|
| ナトリウム | mEq/L | 138-145 | |
| カリウム | mEq/L | 3.6-4.8 | |
| クロール | mEq/L | 101-108 | |
| カルシウム | mg/dL | 8.8-10.1 | |
| 無機リン | mg/dL | 2.7-4.6 | |
| CRP | mg/dL | 0.00-0.14 | |
| アミラーゼ | U/L | 44-132 | |
| CK | U/L | 男性:59-248 女性:41-153 |
|
| 鉄 (Fe) | µg/dL | 40-188 |
各選択肢を見ていきましょう。慣れていると一目で異常だとわかるレベルの問題です。
- ALP(アルカリホスファターゼ) 300 U/L
- 通常、成人における基準値は38~113 U/L程度(IFCC)です。
300 U/Lは基準値を上回りますが、生命を脅かす「パニック値」と定義される水準には達していません。
パニック値は、1000~1500 U/Lを超えるような極端な高値に設定されていることが多いです。子供は高値なので要注意です。
- 通常、成人における基準値は38~113 U/L程度(IFCC)です。
- カルシウム 10.8 mg/dL
- カルシウムの基準値は8.8~10.1 mg/dL程度であり、10.8 mg/dLはやや高値です。しかしながら、一般的に「高カルシウム血症」として臨床的に問題となるのは12 mg/dL以上であり、重篤な症状が出始めるのは14 mg/dL以上とされています。
パニック値としては、低値で6 mg/dL以下、高値で12.0 mg/dL以上が設定されていることが多いです。
- カルシウムの基準値は8.8~10.1 mg/dL程度であり、10.8 mg/dLはやや高値です。しかしながら、一般的に「高カルシウム血症」として臨床的に問題となるのは12 mg/dL以上であり、重篤な症状が出始めるのは14 mg/dL以上とされています。
- グルコース 200 mg/dL
- グルコース(血糖値)の基準値は、空腹時で70~100 mg/dL程度です。
食後であれば200 mg/dLは高値ですが、通常、低血糖であれば50 mg/dL以下、高血糖であれば`350 mg/dL以上、入院患者では500 mg/dL以上でパニック値とされる施設が多いと思います。
- グルコース(血糖値)の基準値は、空腹時で70~100 mg/dL程度です。
- ナトリウム 175 mmol/L:
- ナトリウムの基準値は135~145 mmol/L程度。恒常性が働くため、電解質の基準値はシビアに見たほうがいいです。
175 mmol/Lは著しい高ナトリウム血症であり、パニック値に該当する。重度の高ナトリウム血症は、意識障害、痙攣、脳浮腫などの神経症状を引き起こし、生命に関わる緊急事態です。
ナトリウムのパニック値は160 mmol/L以上、または120 mmol/L以下と設定されている施設が多いと思います。
- ナトリウムの基準値は135~145 mmol/L程度。恒常性が働くため、電解質の基準値はシビアに見たほうがいいです。
- 総コレステロール 300 mg/dL
- 総コレステロールの基準値は140~240 mg/dL程度です。
300 mg/dLは高値であり、将来的な動脈硬化性疾患のリスクは高まりますが、緊急に治療が必要な「パニック値」ではありません。コレステロール値自体が直接的に生命を脅かすことは稀であり、パニック値は設定されていないのが一般的です。
- 総コレステロールの基準値は140~240 mg/dL程度です。
答え:4
9 尿沈渣に認められた結晶(別冊No. 1)を別に示す。考えられるのはどれか。

- 高尿酸血症
- 閉塞性黄疸
- ネフローゼ症候群
- 先天性シスチン尿症
- 先天性アデニンホスホリボシルトランスフェラーゼ欠損症
写真の成分は「ビリルビン結晶」の代表的な画像です。
★ビリルビン結晶の特徴
【形態】
- 針状、顆粒状、または不規則な塊状: 細かい針状の結晶が集合して、不規則な塊や顆粒状に見えることが多いです。
- 特徴的な色: 結晶自体が黄褐色~黄赤色を呈します。これはビリルビンの色素によるものです。
【病態】
- 閉塞性黄疸
- 肝細胞性黄疸
- 重症肝障害
など
したがって、選択肢の中では閉塞性黄疸が該当する。
答え:2
第71回(AM)臨床検査医学総論(10〜15)
▼ クリックすると詳細が開きます
10 内部精度管理法で患者データを用いるのはどれか。2つ選べ。
- X-R管理図法
- 累積和管理図法
- 項目間チェック法
- デルタチェック法
- マルチルール管理図法
以下にそれぞれの内部精度管理法について解説します。
- X-R管理図法、累積和管理図法、マルチルール管理図法
これらは、主に管理用試料(コントロール血清など)の測定値を用いて、測定系の精度を管理する方法です。
日々の測定値が統計的に許容範囲内にあるかを確認し、異常があれば測定系のトラブルを早期に発見することを目的とします。患者データは直接使用しません。
- 項目間チェック法(Inter-item check)
これは、患者データを用いて精度管理を行う方法の一つです。
複数の検査項目(例えば、電解質や肝機能項目など、生理的に関連のある項目)の測定値を比較し、その比率やバランスが異常でないかを確認します。例えば、NaとClの比率や、ASTとALTの比率などが用いられます。
これにより、測定系の異常や検体取り違いなどを検出することができます。
- デルタチェック法(Delta check)
これも、患者データを用いて精度管理を行う方法です。同一患者の過去の測定値と今回の測定値を比較し、その差(デルタ値)が許容範囲を超えていないかを確認します。急激な変動があった場合に、検体取り違い、採血ミス、測定エラーなどを疑うことができます。
もちろん、病気の進行により急激にデータ変動が認められる場合もあります。
したがって、患者データを用いるのは 項目間チェック法 と デルタチェック法 です。
-
患者データを用いるのは
→ 項目間チェック法
→ デルタチェック法 -
管理用試料(コントロール血清など)を用いるのは
→ X-R管理図法
→ 累積和管理図法
→ マルチルール管理図法
答え:3と4
11 カットオフ値が用いられるのはどれか。
- AST
- CEA
- LD
- クレアチニン
- ナトリウム
★カットオフ値とは
- カットオフ値(Cut-off value)とは、検査結果の数値が「正常(陰性)」か「異常(陽性)」かを区別するための「境界値」のこと。
- 通常は腫瘍マーカーやウイルス抗体価に用いられる。
※【補足】
「共用基準値」は、健康な集団の検査値の95%が含まれる範囲(上下2.5%は含まない)を示すもの。
それに対し、カットオフ値は特定の疾患の診断やスクリーニングにおいて「ある状態か、そうでないか」を区別するための一点(境界)を指す。
以下にそれぞれの項目について解説します。
- AST 、LD 、クレアチニン、ナトリウム
これらは一般的な生化学検査項目であり、通常は基準範囲や正常値と呼ばれる範囲が設定されています。
「カットオフ値」を設定してそれ以上(以下)で「陽性」「陰性」を判断することはないです。
- CEA (癌胎児性抗原)
CEAは腫瘍マーカーの一種です。腫瘍マーカーは、がんの有無や治療効果を評価するために測定されますが、多くの場合、特定の疾患(がん)を診断するための「カットオフ値」が設定されています。
この値を超えると「陽性」と判断され、がんの可能性が示唆されたり、治療効果が不十分であったり、再発が疑われたりします。
例えば、CEAは「5.0 ng/mL以上で陽性」といったカットオフ値が設定され、がんのスクリーニングや経過観察に用いられます。
答え:2
12 子宮頸癌の原因はどれか。
- EBウイルス
- 単純ヘルペスウイルス
- ヒトT細胞白血病ウイルスI型
- ヒトパピローマウイルス
- ヒト免疫不全ウイルス
選択肢のウイルスがどういった病態をもたらすかを解説します。
- EBウイルス (Epstein-Barr Virus)
伝染性単核球症や、バーキットリンパ腫、上咽頭癌などとの関連が知られています。 - 単純ヘルペスウイルス (Herpes Simplex Virus)
口唇ヘルペスや性器ヘルペスの原因ウイルスです。 - ヒトT細胞白血病ウイルスI型 (HTLV-I)
成人T細胞白血病・リンパ腫(ATL)の原因ウイルスです。 - ヒトパピローマウイルス (HPV)
子宮頸癌の主要な原因ウイルスです。特に16型と18型が高リスク型として知られており、子宮頸癌の約70%を引き起こします。
HPVは性交渉で感染し、多くは一過性だが、一部が持続感染し異形成〜癌へ進行。
ワクチン(HPVワクチン)はこれらの高リスク型を対象にした予防手段。
- ヒト免疫不全ウイルス (HIV)
AIDS(エイズ)の原因ウイルスであり、免疫力を低下させます。HIV感染者はHPV感染が持続しやすく、子宮頸癌の発症リスクが高まることが知られていますが、HIV自体が子宮頸癌を直接引き起こすわけではありません。
子宮頸癌の直接の原因となるのは、HPV(ヒトパピローマウイルス)です。
答え:4
13 Basedow病で認められるのはどれか。
- 頻 脈
- 便 秘
- 皮膚乾燥
- フレイル
- 記銘力低下
バセドウ病の代表的な症状をまとめました。
★バセドウ病の主な症状
- 甲状腺腫(甲状腺の腫れ)
- 眼球突出
- 頻脈、動悸
- 全身の代謝の亢進(体重減少、多汗、手の震えなど)
上記より頻脈が解答になるのですが、他の選択肢も見ていきましょう。
- 便秘
甲状腺ホルモンの作用で腸の動きも活発になるため、Basedow病ではむしろ下痢や軟便になりやすい傾向があります。
便秘は甲状腺機能低下症(橋本病など)でよく見られる症状です。
- 皮膚乾燥
新陳代謝が活発になるため、発汗が多くなり、皮膚はしっとりしたり、汗ばんだりすることが多いです。
皮膚の乾燥は甲状腺機能低下症でよく見られる症状です。
- フレイル
加齢に伴い心身の活力が低下し、健康障害に陥りやすい、虚弱な状態を指します。健康な状態と、要介護状態の中間に位置します。
- 記銘力低下
Basedow病では、精神的な興奮、イライラ、集中力の低下が見られることはありますが、直接的な記銘力低下は一般的ではありません。
甲状腺機能低下症で、思考力の低下や物忘れなどの症状が見られることがあります。
答え:1
14 ネフローゼ症候群で誤っているのはどれか。
- 浮 腫
- 乏 尿
- 蛋白尿
- 血清アルブミン低下
- LDL-コレステロール低下
★ネフローゼ症候群の主要な特徴
ネフローゼ症候群は、以下の4つの主要な兆候(四大症状)を特徴とします。
- 高度の蛋白尿(1日3.5g以上)
- 低アルブミン血症(血清アルブミン 3.0g/dL以下)
- 浮腫
- 高脂血症
ネフローゼ症候群は、腎臓の糸球体という部分に異常が起き、タンパク質が大量に尿中に漏れ出てしまう病気です。これにより、体内で様々な変化が起こります。
上表を参考に各選択肢について解説します。
- 浮腫(正しい)
尿中に大量のタンパク質が失われると、血液中のタンパク質(特にアルブミン)が減少し、血管内の浸透圧が低下します。これにより、血管内の水分が血管外(間質)に漏れ出しやすくなり、顔や手足、全身に浮腫が現れます。
- 乏尿(正しい)
ネフローゼ症候群では、循環血液量が減少したり、腎機能が低下したりすることで、尿量が減少する「乏尿」を呈することがあります。重症度によっては、さらに尿量が減少して「無尿」となることもあります。
- 蛋白尿(正しい)
ネフローゼ症候群の最も基本的な特徴です。腎臓の糸球体のフィルター機能が障害され、本来なら尿中にほとんど排泄されないはずのタンパク質(特にアルブミン)が大量に尿中に漏れ出てしまいます。
- 血清アルブミン低下(正しい)
低アルブミン血症が浮腫の主な原因となります。
- LDL-コレステロール低下(誤り)
ネフローゼ症候群では、肝臓がアルブミンの合成を亢進させるのと同時に、脂質(コレステロールや中性脂肪)の合成も亢進させます。
これは、血液中の浸透圧を保とうとする代償反応の一つと考えられています。そのため、LDL-コレステロール値だけでなく、総コレステロールや中性脂肪も高値(高脂血症)となるのが特徴です。
答え:5
15 バイタルサインでないのはどれか。
- 血 圧
- 呼 吸
- 体 温
- 体 重
- 脈 拍
バイタルサインについてまとめました。
★バイタルサイン(4つ)
- 体温(Body Temperature)
- 脈拍 (Pulse Rate)
- 呼吸 (Respiration Rate)
- 血圧 (Blood Pressure)
補足:SpO2や意識レベル(JCS、GCS)などを含める施設もある。
バイタルサイン(vital signs)とは、生命兆候とも呼ばれ、体の基本的な生命活動の状態を示す指標のことです。医療現場では患者さんの状態を把握するために継続的に測定されます。
体重は、生命活動の「兆候」をリアルタイムに示すバイタルサインには含まれません。
答え:4
第71回(AM)臨床生理学(16〜28)
▼ クリックすると詳細が開きます
16 標準12誘導心電図でV4誘導の電極位置はどれか。
- 第4肋間胸骨右縁
- 第4肋間胸骨左縁
- 第5肋間と左鎖骨中線の交点
- 第5肋間と左前腋窩線の交点
- 第5肋間と左中腋窩線の交点

★標準12誘導心電図のV誘導電極位置
標準12誘導心電図では、胸部誘導(V1~V6)の電極を特定の場所に配置します。それぞれの位置は以下の通りです。
- V1: 第4肋間胸骨右縁
- V2: 第4肋間胸骨左縁
- V3: V2とV4の中間地点
- V4: 第5肋間と左鎖骨中線の交点
- V5: V4と同じ水平線上で、左前腋窩線との交点
- V6: V4と同じ水平線上で、左中腋窩線との交点
答え:3
17 標準12誘導心電図(別冊No. 2)を別に示す。所見はどれか。

- 心房細動
- 心房粗動
- 上室頻拍
- 心室細動
- 心室頻拍
心電図から「のこぎり歯状のF波と規則的なRR間隔」が読み取れます。
これは「心房粗動」に特徴的な心電図であり、他の特徴を表にまとめました。
- 特徴的なF波(粗動波)
II、III、aVF誘導でのこぎり歯状、または逆P波と呼ばれる特徴的な基線の揺れ(F波)が認められます。
F波の周波数は通常250~350回/分と非常に速く、規則的です。
- 規則的なRR間隔と心室レート
房室結節でのブロックによって、心室への伝導が規則的に行われます。
心房からの興奮が2回に1回、または4回に1回心室に伝導される「2:1伝導」や「4:1伝導」が多く見られます。
これにより、QRS波の間隔(RR間隔)は規則的になり、心室レートも比較的規則的になります。
- P波の欠如
通常の洞結節からのP波は認められず、F波がその代わりをしています。
選択肢を見ると心房細動との鑑別になるかなと思われますが、問題の心電図では
- p波と平坦な基線が見られず、Ⅱ、Ⅲ、Fで鋸歯状のF波が認められる。
- 4回の心房興奮のうち1回が心室に伝わっているため、4:1伝導だと考えることができる。
★心房細動の特徴
- P波の消失
規則的なP波は認められず、基線が不規則に揺れるf波(細動波)が見られます。 - RR間隔の不整
QRS波の間隔が完全に不規則になります。 - 心拍数の増加
心室への伝導が速くなると、心拍数が100拍/分を超える頻脈になることが多いです。
心房細動だとすれば F波はなくf波 となり、RR間隔も不整となるため、問題のような規則的な波形にはならない。
上室頻拍、心室細動、心室頻拍もどれも代表的な所見を持つ波形であるため、確認しておくべき心電図です。
答え:2
18 スパイログラム(別冊No. 3)を別に示す。Aが示すのはどれか。

- 肺活量
- 一回換気量
- 最大吸気量
- 予備吸気量
- 予備呼気量

上の図から、Aが示す安静吸気位から最大吸気位までの気量は最大吸気量である事がわかる。
その他の選択肢も、上図を参考にするとどこに該当するものなのかがわかリます。
答え:3
19 肺拡散能(DLco)が低下しないのはどれか。
- 肺気腫
- 肺切除後
- 間質性肺炎
- 気管支喘息
- 肺血栓塞栓症
★肺拡散能 (DLco) とは
肺胞から血液中へCOガス(一酸化炭素)がどれだけ効率よく移動できるかを評価する検査のこと。
この値が低下するということは、ガス交換の効率が悪くなっていることを意味します。
上記を参考に、各選択肢を見ていきましょう。
- 肺気腫
肺気腫は、肺胞壁が破壊され、ガス交換が行われる表面積が減少する疾患です。
そのため、DLcoは著しく低下します。
- 肺切除後
肺の一部を切除すると、当然ながらガス交換を行う肺の量が減少します。
そのため、全体のDLcoは低下します。ただし、残された肺の機能自体が低下しているわけではないので、DLcoを肺気量で補正した値(DLco/VA)は正常範囲内になることがあります。しかし、問題は「DLcoが低下しない」なので、肺切除後のDLcoは低下します。
- 間質性肺炎
間質性肺炎は、肺胞と毛細血管の間にある「間質」と呼ばれる組織が炎症や線維化を起こし、厚くなる病気です。
これにより、ガスが拡散する距離が長くなり、ガス交換が阻害されます。
そのため、DLcoは低下します。
- 気管支喘息
気管支喘息は、気道が炎症を起こし、狭くなることで呼吸困難が生じる疾患です。
主な病態は気道の閉塞であり、肺胞や毛細血管のガス交換能力自体は通常保たれています。そのため、DLcoは低下しません。
- 肺血栓塞栓症
肺血栓塞栓症は、肺動脈が血栓で閉塞し肺への血流が阻害される疾患です。
これにより、ガス交換が行われる肺胞は存在するものの、血流がないためにガス交換ができません。
有効なガス交換面積(毛細血管床)が減少するため、DLcoは低下します。
答え:4
20 室内気吸入時の動脈血ガス分析で基準範囲内にあるのはどれか。
- pH 7.00
- PaO2 70 mmHg
- PaCO2 40 mmHg
- HCO3- 30mmol/L
- BE +5mmol/L
一般的な動脈血ガス分析の基準範囲は以下に示します。
★血液ガスの基準値
| 項目 | 基準値 | 単位 | 補足 |
|---|---|---|---|
| pH | 7.35 ~ 7.45 | ||
| PaO2 | 80 ~ 100 | mmHg | 動脈血酸素分圧。年齢によって低くなる傾向があります。 |
| PaCO2 | 35 ~ 45 | mmHg | 動脈血二酸化炭素分圧。 |
| HCO3- | 22 ~ 26 | mmol/L | 重炭酸イオン。 |
| BE | ±2 以内 | mmol/L | Base Excess、塩基過剰。 |
上記の基準値と選択肢を比較してみましょう。
- pH 7.00
基準範囲(7.35~7.45)よりはるかに低く、重度のアシドーシスを示します。 - PaO2 70 mmHg
基準範囲(80~100 mmHg)より低く、低酸素血症を示します。 - PaCO2 40 mmHg
基準範囲(35~45 mmHg)内にあります。 - HCO3- 30 mmol/L
基準範囲(22~26 mmol/L)より高く、代謝性アルカローシスまたは代償性アルカローシスを示します。 - BE +5 mmol/L
基準範囲(±2 mmol/L以内)より高く、代謝性アルカローシスを示します。
したがって、基準範囲内にあるのはPaCO2 40 mmHg です。
答え:3
21 ニューロンの活動電位の始まりを担うイオンはどれか。
- Ca2+
- Cl
- K+
- Mg2+
- Na+
★活動電位とは
膜電位が閾値を超えると、膜電位依存性 Na+チャネルが開き細胞内に大量のNa+が一気に流入し、脱分極する。
これを活動電位とよぶ。
活動電位の発生メカニズムは以下のようになります。
- ①静止膜電位
→ニューロンは通常、細胞内が細胞外に対して負の電位(約 -70mV)に保たれています。これは主にK+チャネルとNa+/K+ポンプによって維持されています。 - ②脱分極
→ある刺激によって細胞膜が興奮し、膜電位が閾値(いきち)電位(約 -55mV)に達すると、電位依存性Na+チャネルが開きます。 - ③活動電位の立ち上がり(上昇相)
→開いたNa+チャネルを通って、細胞外の高濃度のNa+イオンが急速に細胞内へ流入します。
これにより、細胞内の電位は一気に正の方向に変化し、活動電位の立ち上がり(脱分極の急激な上昇)が起こります。
これが活動電位の「始まり」を担う重要なステップです。 - ④再分極
→Na+チャネルが不活性化し、同時に電位依存性K+チャネルがゆっくりと開き、K+イオンが細胞外へ流出することで、膜電位は再び負の方向に戻ります。 - ⑤過分極
→K+チャネルの閉鎖が遅いため、一時的に静止膜電位よりも過剰に負の電位になることがあります。
順序立てて考えると、何が始まりなのかがわかると思います。
活動電位の急激な立ち上がりを担うのはナトリウムイオンの流入です。
答え:5
22 反復神経刺激検査で検出できる機能障害の部位はどれか。
- 大脳運動野
- 脊 髄
- 末梢神経
- 神経筋接合部
- 骨格筋
★反復神経刺激検査(Repetitive Nerve Stimulation Test: RNS)
反復神経刺激検査は、末梢神経に電気刺激を繰り返し与え、それによって誘発される筋の複合活動電位(Compound Muscle Action Potential: CMAP)の振幅が、刺激回数を重ねるごとにどのように変化するかを評価する検査のこと。
神経筋接合部の機能障害を検出できる。
主な疾患としては
- 重症筋無力症(Myasthenia Gravis)
- Lambert-Eaton筋無力症候群
などの神経筋接合部疾患などを検出できる。
なぜこの検査が有効なのかを補足説明します。
- 重症筋無力症(Myasthenia Gravis)
→神経筋接合部において、神経からのアセチルコリン放出や、筋側の受容体の異常により、神経から筋への信号伝達が障害されます。反復刺激によってアセチルコリンの枯渇や受容体の機能不全が顕著になり、CMAPの振幅が段階的に減少する「waning(ウェイニング)」または「decremental response(漸減現象)」が特徴的に見られます。 - ランバート・イートン筋無力症候群(Lambert-Eaton Myasthenic Syndrome: LEMS)
→神経筋接合部におけるアセチルコリン放出の障害が原因で、やはり特徴的な反応を示します(高頻度刺激でCMAPが増大するなど)。
他の選択肢も見てみましょう。
- 大脳運動野
→大脳運動野の機能障害は、主に脳波検査やMRIなどの画像検査、あるいは経頭蓋磁気刺激(TMS)などで評価されます。 - 脊髄: 脊髄の機能障害は、誘発筋電図(SEP: 体性感覚誘発電位など)やMRIなどで評価されます。
- 末梢神経
→末梢神経そのものの障害(多発性神経炎、ギラン・バレー症候群など)は、神経伝導検査(Nerve Conduction Study: NCS)で神経伝達速度の遅延や振幅の低下として検出されます。 - 骨格筋
→骨格筋そのものの障害(筋ジストロフィー、多発性筋炎など)は、筋電図検査(針筋電図)で、筋線維の活動電位の異常や、筋力低下を伴う電位のパターンとして検出されます。
答え:4
23 健常成人の脳波(別冊No. 4)を別に示す。睡眠段階はどれか。

- Stage W
- Stage N1
- Stage N2
- Stage N3
- Stage R
★健常人の睡眠段階と脳波の主要な特徴
睡眠は主にノンレム睡眠とレム睡眠に分けられ、ノンレム睡眠はさらに深さによって3段階に分類されます。
- 覚醒 (WAKE)
→脳波: 閉眼時: α波 (8~13Hz)
→開眼時/活動時: β波 (13Hz以上) - ノンレム睡眠 (NREM sleep)
→N1 (睡眠導入期): θ波 (4~7Hz) が主で、頂点鋭波が出現することもあります。
→N2 (軽睡眠期): 睡眠紡錘波 (12~14Hz) とK複合もしくは両者が出現します。
→N3 (深睡眠期): 高振幅のδ波 (0.5~4Hz) が全体の20%以上を占めます。 - レム睡眠 (REM sleep)
→脳波: 覚醒時に似た低振幅の非同期性脳波。
→特徴: 急速眼球運動 (REM) と筋緊張のほぼ消失(アトニア)。
設問の脳波には頭頂銀波と14 Hzの紡錘波が認められるため、Stage N2であると考えられる。
答え:3
24 脳波(別冊No. 5)を別に示す。最も考えられるのはどれか。

- West症候群
- 欠神てんかん
- Creutzfeldt-Jakob病
- ミオクロニーてんかん
- Lennox-Gastaut症候群
脳波を見てみると、鋭波、棘波、高振幅徐波などの異常放電が一定の周期で反復的に出現する周期性同期性放電が認められています。
この所見から、Creutzfeldt-Jakob (クロイツフェルト・ヤコブ) 病が鑑別に上がります。
他の選択肢も含めて表にまとめてみました。
★脳波所見と関連疾患の鑑別点
| 疾患名 | 特徴的な脳波所見 | 補足 |
|---|---|---|
| Creutzfeldt-Jakob (クロイツフェルト・ヤコブ) 病 | 鋭波、棘波、高振幅徐波などの周期性同期性放電 | 一定の周期で反復的に異常放電が出現します。 |
| West (ウェスト) 症候群 | 高振幅な徐波と棘波が時間的, 部位的に変化してみられるヒプスアリスミア | 小児てんかん性脳症に特徴的な脳波パターンです。 |
| 欠神てんかん | 3 Hz棘徐波複合 | 意識消失が主症状です。 |
| ミオクロニーてんかん | 広汎性多棘徐波複合 | 四肢の不随意なミオクロニー発作(ぴくつき)が特徴です。 |
| Lennox-Gastaut (レノックス・ガスト) 症候群 | 1.5~2.5 Hzの鋭徐波複合 | 多彩なてんかん発作型を示す重症小児てんかんです。 |
答え:3
25 体表からの超音波検査で使用する探触子の周波数が最も低いのはどれか。
- 肝 臓
- 心 臓
- 膵 臓
- 乳 腺
- 頸動脈
超音波の基礎問題です。
【周波数と分解能】
- 周波数が高いほど、分解能は向上し、細かい構造がよく見える。
→甲状腺、乳腺、血管表在部などの表在臓器の観察に適する。
【周波数と減衰(透過深度)】
- 周波数が高いほど、減衰が大きくなり、超音波が奥まで届きにくい。
(透過深度が浅い)
→深部臓器の観察には不向き
【周波数の選択】
- 高周波プローブ(7MHz以上):
→乳腺、頸動脈(7.5MHz以上)などの体表臓器 - 低周波プローブ(2〜5MHz)
→心臓:2.25~3.5 MHz
→肝臓:3.5〜5.0 MHz
超音波検査における一般的な周波数の選択
| 周波数の種類 | 周波数帯の目安 | 特徴 (分解能と減衰) | 主な観察部位・用途 |
|---|---|---|---|
| 高周波 | 7MHz以上 | 分解能が良い、減衰が大きい、透過深度が浅い | 甲状腺、乳腺、頸動脈、精巣、眼球、皮膚、リンパ節など表在臓器の観察 |
| 低周波 | 2~5MHz | 分解能は劣る、減衰が小さい、透過深度が深い | 肝臓、胆嚢、膵臓、腎臓、脾臓、子宮、卵巣、心臓、大血管など深部臓器の観察、体格の大きな患者の検査 |
上のまとめにもありますが、最も低周波なプローブは心臓に用いるセクタプローブでしょう。
答え:2
26 心エコーで連続波ドプラ法を使用するのはどれか。
- e′
- E/A
- 左室駆出率
- 肺体血流比
- 右室収縮期圧
心エコーにおけるドプラ法には、主に「パルスドプラ法 (PW Doppler)」と「連続波ドプラ法 (CW Doppler)」があります。
パルスドプラと連続波ドプラについて簡単にまとめました。
- パルスドプラ法 (PW Doppler)
→特定の深さ(サンプルボリューム)の血流速度を正確に測定できますが、計測できる速度には上限(ナイキスト限界)があります。比較的低速の血流や、特定の弁口血流の速度パターンを評価するのに適しています。 - 連続波ドプラ法 (CW Doppler)
→探触子から連続的に超音波を送信し、反射波も連続的に受信するため、非常に高速な血流も正確に測定できますが、どの深さからの信号であるかを特定する距離分解能がありません。
これらの特性を踏まえて各選択肢を見ていきます。
- e′ (僧帽弁輪拡張早期移動速度)
これは組織ドプラ法 (TDI)で測定される指標で、左室の拡張能を評価するために用いられます。
組織ドプラは基本的にはパルスドプラ法の一種であり、心筋の動きのような比較的低速の動きを正確に追うのに適しています。
- E/A (僧帽弁血流速波形の早期拡張期波と心房収縮期波の比)
これも左室の拡張能を評価する指標で左室流入血流速波形から計測します。
僧帽弁口の血流速度を測定します。弁口血流の速度は比較的低速であり、特定の場所(弁口部)の情報を得る必要があるため、パルスドプラ法が用いられます。
- 左室駆出率 (LVEF)
これは心臓の収縮能を示す最も重要な指標の一つですが、ドプラ法ではなく、主にBモード画像(断層像)やMモードを用いて左室の拡張末期容積と収縮末期容積を測定し、Simpson法などの計算式で算出します。LVEF = (LVEDV – LVESV) / LVEDV × 100%)
ドプラ法は直接的には関係ありません。
- 肺体血流比 (Qp/Qs)
心内シャント(心房中隔欠損症や心室中隔欠損症など)がある場合に、肺血流量と体血流量の比を評価するものです。
これは、肺動脈と大動脈のそれぞれの血流量を、パルスドプラ法で測定した血流速度と血管径から算出します。
- 右室収縮期圧 (RVSP)
これは三尖弁逆流(TR)の速度を測定することで推定されます。
三尖弁逆流は、右室が収縮する際に、右室から右房へ血液が逆流する現象であり、その血流速度は非常に速いことがあります。
この高速な血流速度を正確に測定し、圧力勾配(ベルヌーイの式:ΔP = 4V²)を算出するためには、連続波ドプラ法が用いられます。
測定された圧較差に右房圧を加えることで、右室収縮期圧が推定できます。肺高血圧症の診断や重症度評価に非常に重要です。
したがって、心エコーで連続波ドプラ法を使用するのは 「右室収縮期圧」です。
答え:5
27 健常者の右肋間走査の超音波像(別冊No. 6)を別に示す。矢印で示すのはどれか。

- 門 脈
- 肝動脈
- 左肝静脈
- 中肝静脈
- 右肝静脈
右肋間走査にて描かれた、腹部エコー画像には肝臓、胆嚢、門脈が描出されています。うっすら肝静脈も見えますが、肝静脈と門脈の違いは壁が白く描出されているかで簡単に見抜くことができます。
血管の走行で認識できるのが望ましいですが、国家試験レベルであればその鑑別レベルで良いかと思います。
★血管壁のエコー輝度
- 門脈の血管壁は、周囲の肝実質よりも白く(高エコーに)見えます。これは、門脈壁に結合組織が豊富に含まれているためです。
- 肝静脈と区別する重要なポイントで、肝静脈は血管壁が薄くエコーを示しません。
答え:1
28 乳房の超音波像(別冊No. 7)を別に示す。乳腺実質はどれか。

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤
乳腺エコーにおける選択肢の①〜⑤までそれぞれ何かを見ていきます。
- ①皮下脂肪織
- ②乳腺実質
- ③乳腺後脂肪織
- ④大胸筋
- ⑤肋骨
答え:2
第71回(AM)臨床化学(29〜44)
▼ クリックすると詳細が開きます
29 無機質の動態で誤っているのはどれか。
- 腎不全により高マグネシウム血症をきたす。
- 副甲状腺機能低下症により高無機リン血症をきたす。
- 代謝性アルカローシスにより高カリウム血症をきたす。
- 異所性PTH産生腫瘍により高カルシウム血症をきたす。
- 原発性アルドステロン症により高ナトリウム血症をきたす。
無機質の動態について以各選択肢ごとに解説をします。
- 腎不全により高マグネシウム血症をきたす。
正しい。マグネシウムは主に腎臓から排泄されます。
腎機能が低下するとマグネシウムの排泄が滞り、血液中のマグネシウム濃度が上昇し、高マグネシウム血症をきたします。
- 副甲状腺機能低下症により高無機リン血症をきたす。
正しい。副甲状腺ホルモン(PTH)は、腎臓からのリン排泄を促進する働きがあります。
副甲状腺機能低下症ではPTHの分泌が不足するため、腎臓からのリン排泄が低下し、血液中の無機リン濃度が上昇し、高無機リン血症をきたします。
※同時に、カルシウム吸収が低下し、尿細管での再吸収も低下するため、低カルシウム血症をきたします。
- 代謝性アルカローシスにより高カリウム血症をきたす。
誤り。 代謝性アルカローシス(体液がアルカリ性に傾く状態)では、細胞外の水素イオン(H+)濃度が低下します。
このH+濃度を補うために、細胞内のH+が細胞外へ移動し、その代わりに細胞外のカリウムイオン(K+)が細胞内へ取り込まれます。この結果、血液中のカリウム濃度は低下(低カリウム血症)します。
- 異所性PTH産生腫瘍により高カルシウム血症をきたす。
正しい。PTH(副甲状腺ホルモン)は、血液中のカルシウム濃度を上昇させる働きがあります
(骨からのカルシウム放出促進、腎臓でのカルシウム再吸収促進、ビタミンD活性化による腸管からのカルシウム吸収促進)。
異所性PTH産生腫瘍(PTHrP産生腫瘍、例:扁平上皮癌など)は、本来副甲状腺以外からPTHに類似した物質を産生し、これにより副甲状腺機能亢進症と同じように血液中のカルシウム濃度が上昇し、高カルシウム血症をきたします。これは悪性腫瘍による高カルシウム血症の主要なメカニズムの一つです。
- 原発性アルドステロン症により高ナトリウム血症をきたす。
正しい。アルドステロンは副腎皮質から分泌されるホルモンで、腎臓の尿細管においてナトリウムの再吸収を促進し、カリウムの排泄を促進します。
原発性アルドステロン症ではアルドステロンが過剰に分泌されるため、ナトリウムが過剰に再吸収され、高ナトリウム血症をきたすことがあります。
答え:3
30 蛋白で誤っているのはどれか。
- セルロプラスミンは銅を運搬する。
- フェリチンは肝臓に多く分布している。
- トランスサイレチンはビタミンAの代謝に関与する。
- レチノール結合蛋白の血中半減期は約12時間である。
- トランスフェリンは1分子に約3,000個の鉄原子を含有する。
蛋白質についての問題です、よく出ている問題だと思います。
それぞれの選択肢を見ていきましょう。
- セルロプラスミンは銅を運搬する。
正しい。 セルロプラスミンは、銅を運搬する主要なタンパク質であり、体内の銅代謝に重要な役割を果たします。
- フェリチンは肝臓に多く分布している。
正しい。 フェリチンは鉄を貯蔵するタンパク質であり、主に肝臓、脾臓、骨髄などの網内系組織に多く分布しています。血清フェリチンは体内の貯蔵鉄量を反映する指標となります。
- トランスサイレチンはビタミンAの代謝に関与する。
正しい。 トランスサイレチン(Transthyretin: TTR、またはプレアルブミン)は、甲状腺ホルモン(サイロキシン)と、レチノール結合タンパク質(Retinol-Binding Protein: RBP)に結合したビタミンA(レチノール)を運搬します。
間接的にビタミンAの代謝(運搬)に関与しています。
- レチノール結合蛋白の血中半減期は約12時間である。
正しい。 レチノール結合タンパク質(RBP)は、血中でトランスサイレチンと結合して運搬されますが、その血中半減期は比較的短く、約10~12時間程度とされています。
- トランスフェリンは1分子に約3,000個の鉄原子を含有する。
誤り。 トランスフェリンは鉄を運搬するタンパク質ですが、1分子のトランスフェリンが結合できる鉄原子は、最大で2個です(Fe3+の形で)。
3,000個という数字は著しく多く、完全に誤りです。
【補足】
トランスフェリンは分子量 77,000の糖蛋白質であり、N末端とC末端の2箇所にFe3+の結合部位が存在する。
正常ではトランスフェリン全体の1/3がFe3+と結合し、残りの2/3は未結合の遊離トランスフェリンとして存在する。
答え:5
31 ホルモンで正しいのはどれか。
- TSHはBasedow病で高値を示す。
- ACTHはCushing病で低値を示す。
- C-ペプチドはインスリノーマで低値を示す。
- ガストリンはZollinger-Ellison症候群で高値を示す。
- ADHは抗利尿ホルモン不適合分泌症候群〈SIADH〉で低値を示す。
各種ホルモンの問題です。以下に各選択肢の解説をします。
- TSHはBasedow病で高値を示す。
Basedow病(バセドウ病)は甲状腺機能亢進症の一種で、甲状腺ホルモン(T3、T4)が過剰に分泌されます。
甲状腺ホルモンが過剰になると、視床下部-下垂体-甲状腺系のネガティブフィードバック機構により、下垂体から分泌されるTSH(甲状腺刺激ホルモン)は抑制され、低値を示します。
【補足】
橋本病では以下の通りになります。
甲状腺ホルモン(T3、T4)の低下: 甲状腺の機能が低下しているため、血中の甲状腺ホルモン濃度が低下します。
下垂体からのTSH分泌増加: 低下した甲状腺ホルモンを補うため、下垂体は甲状腺をより強く刺激しようと、TSH(甲状腺刺激ホルモン)を過剰に分泌します。
- ACTHはCushing病で低値を示す。
誤り。
→Cushing病(クッシング病)は、下垂体前葉からACTH(副腎皮質刺激ホルモン)が過剰に分泌されることで、副腎皮質からのコルチゾール分泌が過剰になる病態です。
したがって、ACTHは高値を示します。
- C-ペプチドはインスリノーマで低値を示す。
誤り。
→インスリノーマは、膵臓のβ細胞からインスリンが過剰に分泌される腫瘍です。
インスリンはプロインスリンからC-ペプチドと同時に生成されるため、内因性のインスリン分泌が亢進しているインスリノーマでは、C-ペプチドも高値を示します。
外因性インスリンを注射した場合(インスリン自己注射など)は、C-ペプチドは生成されていないため低値となります。
- ガストリンはZollinger-Ellison症候群で高値を示す。
正しい。
→Zollinger-Ellison症候群(ゾリンジャー・エリソン症候群)は、ガストリン産生腫瘍(ガストリノーマ)によってガストリンが過剰に分泌される病態です。
ガストリンは胃酸分泌を強力に促進するため、重度の消化性潰瘍を引き起こします。
- ADHは抗利尿ホルモン不適合分泌症候群〈SIADH〉で低値を示す。
誤り。
→抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)は、ADH(抗利尿ホルモン、バソプレシン)が不適切に過剰に分泌されることで、体内の水分が過剰に保持され、希釈性低ナトリウム血症をきたす病態です。
したがって、ADHは高値を示します。
答え:4
32 コレステロールから生成されるのはどれか。
- 黄体ホルモン
- 成長ホルモン
- 副甲状腺ホルモン
- 卵胞刺激ホルモン
- ヒト絨毛性ゴナドトロピン
コレステロールは、ステロイドホルモンの前駆体です。
ステロイドホルモンには、
性ホルモン(エストロゲン、プロゲステロン、アンドロゲン)や
副腎皮質ホルモン(コルチゾール、アルドステロン)が含まれます。
すなわち上記のホルモンを探し出せばOKです。では、各選択肢を見ていきましょう。
- 黄体ホルモン (プロゲステロン)
正しい。
→プロゲステロンは代表的なステロイドホルモンであり、卵巣の黄体から分泌されます。
コレステロールを前駆体として生合成されます。
- 成長ホルモン
→成長ホルモンは、脳下垂体前葉から分泌されるタンパク質ホルモン(ペプチドホルモン)です。
- 副甲状腺ホルモン (PTH)
→副甲状腺ホルモンは、副甲状腺から分泌されるタンパク質ホルモン(ペプチドホルモン)です。
- 卵胞刺激ホルモン (FSH)
→卵胞刺激ホルモンは、脳下垂体前葉から分泌される糖タンパク質ホルモン(性腺刺激ホルモン)です。
- ヒト絨毛性ゴナドトロピン (hCG)
→ヒト絨毛性ゴナドトロピンは、妊娠中に胎盤から分泌される糖タンパク質ホルモンです。
答え:1
33 蛋白質に糖鎖の付加が行われるのはどれか。
- 核
- 細胞膜
- ゴルジ装置
- リソソーム
- リボソーム
細胞内小器官の機能とタンパク質の翻訳後修飾に関する知識を聞いています。
イメージをしやすいように過去問より類似イラストを持ってきます。

選択肢を含めたそれぞれの役割を簡単にまとめます。
★主要な細胞内小器官とその簡潔な役割
- ゴルジ装置: タンパク質や脂質の修飾・選別・輸送、特に糖鎖の付加。
- ミトコンドリア: 細胞のエネルギー(ATP)生産。
- 核: 細胞の遺伝情報(DNA)を格納し、活動を制御。
- リボソーム: タンパク質を合成(翻訳)。
- 細胞膜: 細胞の内外を隔て、物質の出入りを制御。
- リソソーム: 細胞内の不要な物質や老廃物を分解。
- 小胞体:
→粗面小胞体: 分泌・膜タンパク質の合成、初期の糖鎖付加。
→滑面小胞体: 脂質の合成、カルシウム貯蔵、解毒。 - 核小体: リボソームRNAの合成とリボソームの組み立て。
- 核膜: 核を囲む二重膜で、核内外の物質の出入りを制御。
複雑ですが、この問題もよく出ると思います。しっかりと把握しておきましょう。
答え:3
34 血漿中でアルブミンと結合しているのはどれか。
- ケトン体
- リン脂質
- 遊離脂肪酸
- コレステロール
- トリグリセライド
血液中の物質輸送に関する知識を聞いている問題です。
各選択肢について見ていきましょう。
- ケトン体
→ケトン体(アセト酢酸、3-ヒドロキシ酪酸、アセトン)は水溶性であり、血漿中では主に遊離型で存在し、アルブミンとは通常結合しません。さいケトン体を聞く過去問もありました - リン脂質
→リン脂質は、コレステロールやトリグリセリドとともにリポタンパク質(カイロミクロン、VLDL、LDL、HDLなど)を構成し、その一部として運搬されます。単独でアルブミンと結合して運搬されることはありません。 - 遊離脂肪酸 (Free Fatty Acids: FFA)
→正しい。 遊離脂肪酸は水に溶けにくい疎水性の物質であり、血液中で運搬される際には、そのほとんどがアルブミンと結合して運ばれます。アルブミンには脂肪酸を結合する多数の部位があります。 - コレステロール
→コレステロールも疎水性ですが、主にリポタンパク質の構成成分として運搬されます。単独でアルブミンと結合して運搬されることはありません。 - トリグリセライド (中性脂肪)
→トリグリセライドは最も疎水性の高い脂質であり、リポタンパク質(特にカイロミクロンやVLDL)の主要な構成成分として運搬されます。単独でアルブミンと結合して運搬されることはありません。
答え:3
35 血清クレアチニンが低下するのはどれか。
- 脱 水
- 妊 娠
- 腎不全
- 先端巨大症
- うっ血性心不全
血清クレアチニン値が低下する病態や生理的変化はどれかを聞いている問題です。
クレアチニンは、筋肉の代謝産物であり、主に腎臓から尿中に排泄されます。血清クレアチニン値は、腎機能の指標として広く用いられます。各選択肢について見ていきましょう。
- 脱水
→脱水により循環血液量が減少し、腎血流量が低下すると、糸球体ろ過量(GFR)が低下し、クレアチニンの排泄が滞るため、血清クレアチニン値は上昇します。
- 妊娠
→正しい。 妊娠中は、胎児への栄養供給などの生理的変化(循環血漿量の増加)により、腎血流量が増加し、糸球体ろ過量(GFR)が亢進します。これによりクレアチニンの排泄が促進されるため、血清クレアチニン値は低下します。
- 腎不全
→腎不全では、腎臓の機能が低下し、クレアチニンを適切に排泄できなくなるため、血清クレアチニン値は上昇します。これは腎機能低下の主要な指標です。(必然的にeGFRも低下する)
- 先端巨大症
→先端巨大症は成長ホルモンの過剰分泌による疾患です。成長ホルモンは筋肉量の増加を促す作用があるため、クレアチニンの産生量が増加する可能性があります。
- うっ血性心不全
→うっ血性心不全では、心臓のポンプ機能が低下し、腎臓への血流量が減少します(腎前性急性腎障害)。これにより、腎機能が低下し、クレアチニンの排泄が滞るため、血清クレアチニン値は上昇します。
答え:2
36 血清量0.05mL、試薬量3.1mL、光路長1.0cmの条件でLD活性を測定したところ、1分間当たりの吸光度変化量が0.020であった。
NADHのモル吸光係数を6.3×103L・mol-1・cm-1とすると、活性値(U/L)はどれか。
- 20
- 50
- 100
- 200
- 500
活性値(U/L)を求める公式:ランベルト・ベールの法則を使います。
$$\text{活性値 (U/L)} = \frac{\Delta OD/\text{min} \times \text{総液量 (mL)}}{\text{モル吸光係数} \times \text{光路長 (cm)} \times \text{検体量 (mL)}} \times \text{換算係数}$$
与えられた値は以下の通りです。
- ΔOD/min (1分間当たりの吸光度変化量) = 0.020
- Vs (血清量) = 0.05mL
- 試薬量 = 3.1mL
- Vt (全量) = 血清量 + 試薬量 = 0.05mL+3.1mL=3.15mL
- ϵ (NADHのモル吸光係数) = 6.3×103L⋅mol−1⋅cm−1
- b (光路長) = 1.0cm
それでは、値を代入して計算します。
$$\text{活性値 (U/L)} = \frac{0.020 \times 3.15 \, \text{mL}}{6.3 \times 10^3 \, \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1} \times 1.0 \, \text{cm} \times 0.05 \, \text{mL}} \times 1000$$
まず、分子を計算します。
6.3×103×1.0×0.05=6300×0.05=315
これらを式に代入します。
$$\text{活性値 (U/L)} = \frac{0.063}{315} \times 1000$$
$$\text{活性値 (U/L)} = 0.0002 \times 1000$$
$$\text{活性値 (U/L)} = 200$$
したがって、活性値は 200 U/Lです。
答え:4
37 肝細胞癌に対して特異性が高いのはどれか。2つ選べ。
- AFP
- CA15-3
- PIVKA-Ⅱ
- PSA
- SLX
肝細胞癌の診断や経過観察には、いくつかの腫瘍マーカーが用いられますが、特に特異性が高いとされるのは以下の2つです。
- AFP (α-フェトプロテイン)
AFPは、胎児期に肝臓や卵黄嚢で作られるタンパク質で、出生後はほとんど検出されなくなります。肝細胞癌や一部の胚細胞腫瘍で高値を示すことが知られています。特に肝細胞癌の診断や治療効果のモニタリング、再発の早期発見に広く用いられます。肝細胞癌の特異性が比較的高いマーカーの一つです。
- PIVKA-Ⅱ (Protein Induced by Vitamin K Absence or Antagonist-Ⅱ)
PIVKA-Ⅱ(ピーブカ・ツー)は、プロトロンビン(血液凝固因子の一つ)の前駆体であり、ビタミンK欠乏時やビタミンK拮抗薬服用時に生成されます。肝細胞癌では、がん細胞の分化度が低い場合にPIVKA-Ⅱが上昇することが多く、AFPとは異なるメカニズムで上昇するため、両者を併用することで診断精度が向上します。肝細胞癌に非常に特異性の高いマーカーとして知られています。
その他の選択肢
- CA15-3:主に乳がんの腫瘍マーカーとして用いられます。
- PSA:主に前立腺がんの腫瘍マーカーとして用いられます。
- SLX:Sialyl Lewis X-i抗原(シアリルLewis X-i抗原)のことで、消化器系のがん(特に膵臓がんや胆道がんなど)や肺、卵巣、膵臓がんなどで高値を示すことがある。
腫瘍マーカー一覧も参考までに載せておきます。
★腫瘍マーカー一覧
| 腫瘍マーカー | 主な対象疾患 | 補足事項 |
|---|---|---|
| AFP (α-フェトプロテイン) | 肝細胞がん、胚細胞腫瘍(卵黄嚢腫瘍など) | 肝炎、肝硬変、妊娠後期でも上昇する可能性あり |
| PIVKA-II | 肝細胞がん | AFPと併用されることが多い |
| AFP-L3分画 | 肝細胞がん | AFPの分画で、肝細胞がんの特異性が高いとされる |
| CEA (癌胎児性抗原) | 大腸がん、胃がん、肺がん、乳がん、膵臓がん、胆道がん、子宮がんなど | 幅広いがんで上昇。良性疾患や喫煙でも上昇する可能性あり |
| CA19-9 (糖鎖抗原19-9) | 膵臓がん、胆道がん、大腸がん、胃がん | 膵炎、胆管炎などの良性疾患でも上昇する可能性あり |
| Span-1 / DUPAN-2 / CA50 | 膵臓がん、胆道がん | CA19-9と併用されることがある |
| エラスターゼ1 | 膵臓がん | |
| CYFRA (サイトケラチン19フラグメント) | 非小細胞肺がん(特に扁平上皮がん) | |
| NSE (神経特異エノラーゼ) | 小細胞肺がん、神経芽細胞腫 | |
| ProGRP (ガストリン放出ペプチド前駆体) | 小細胞肺がん | |
| SCC抗原 (扁平上皮がん関連抗原) | 扁平上皮がん(肺、食道、子宮頸部など) | |
| PSA (前立腺特異抗原) | 前立腺がん | 前立腺肥大症、前立腺炎でも上昇する可能性あり |
| CA15-3 (糖鎖抗原15-3) | 乳がん | 治療効果判定や再発モニタリングに有用 |
| CA125 (糖鎖抗原125) | 卵巣がん、子宮体がん、膵臓がん、胃がん | 子宮内膜症、良性卵巣腫瘍、妊娠などでも上昇する可能性あり |
| HE4 | 卵巣がん(特に上皮性卵巣がん) | CA125と併用されることが多い |
| サイログロブリン | 甲状腺分化癌(乳頭がん、濾胞がん) | 手術後の再発モニタリングに用いられる |
| NMP22 (核マトリックスタンパク質22) | 膀胱がん、尿路上皮がん | |
| 可溶性インターロイキン-2受容体 (sIL-2R) | 悪性リンパ腫、成人T細胞白血病など | |
| p53抗体 | 大腸がん、乳がん、食道がんなど |
答え:1と3
38 血漿カルシウムで正しいのはどれか。2つ選べ。
- イオン型は電極法で測定する。
- アルカレミアではイオン型が上昇する。
- 生理活性として作用するのはイオン型である。
- 総カルシウム量の30%がイオン型として存在する。
- 蛋白結合型の多くはα1-グロブリンと結合している。
血漿中のカルシウムの形態とその性質に関する知識を聞いている問題です。
特に、カルシウムの様々な存在形態(イオン型、蛋白結合型など)と、それぞれの特徴や測定法について理解している必要があります。
以下に各選択肢の解説をします。
- イオン型は電極法で測定する。
正しい。
→イオン化カルシウム(遊離型カルシウム)は、カルシウム選択性電極を用いた電極法(直接測定法)で測定されます。
これは、pHやタンパク質濃度の影響を受けにくい利点があります。
- アルカレミアではイオン型が上昇する。
誤り。
→アルカレミア(血液がアルカリ性に傾く状態)になると、水素イオン(H+)が減少します。アルブミンなどのタンパク質は、H+とカルシウムイオン(Ca2+)の両方と結合する性質があります。H+が減少すると、より多くのカルシウムイオンがアルブミンに結合できるようになるため、イオン化カルシウムは低下します。
アシドーシスでは逆にH+が増加し、Ca2+がタンパク質から遊離するため、イオン化カルシウムは上昇します。
- 生理活性として作用するのはイオン型である。
正しい。
→血漿中のカルシウムは、イオン型(遊離型)、タンパク質結合型(主にアルブミンと結合)、複合体型(クエン酸やリン酸と結合)の3つの形態で存在します。
このうち、生理活性(筋収縮、神経伝達、血液凝固、ホルモン分泌など)を持つのは、イオン型のカルシウムのみです。
- 総カルシウム量の30%がイオン型として存在する。
誤り。
→血漿総カルシウムの約45~50%がイオン型(遊離型)として存在します。
残りの約40~45%がタンパク質結合型、約5~10%が複合体型(錯体)です。
- 蛋白結合型の多くはα1-グロブリンと結合している。
誤り。
→蛋白結合型カルシウムの主な結合蛋白はアルブミンです。
α1-グロブリンとはほとんど結合しません。
答え:1と3
39 血清アルブミンで正しいのはどれか。
- 劇症肝炎で上昇する。
- 半減期は約7日である。
- 座位よりも臥位での採血で低い。
- 総カルシウム濃度と負の相関がある。
- 健常人では1日1g程度が尿中に排出される。
血清アルブミンの性質、変動要因、および生理的役割に関する知識が必要な問題です。
選択肢の中には過去問と全く同じものもあります。各選択肢の解説をしていきます。
- 劇症肝炎で上昇する。
誤り。
→アルブミンは肝臓で合成されるタンパク質です。劇症肝炎では肝細胞が広範囲に破壊され、肝機能が著しく低下するため、アルブミンの合成能力も低下し、血清アルブミン値は低下します。
- 半減期は約7日である。
誤り。
→血清アルブミンの半減期は、一般的に約17~20日(約3週間)とされています。
7日は短すぎます。比較的長い半減期を持つため、栄養状態や肝機能の長期的な指標として用いられます。
- 座位よりも臥位での採血で低い。
正しい。
→座位から臥位に姿勢を変えると、体液が均等に再分配され、血管内の水分が組織間液に移動する圧力が変化します。
具体的には、座位から臥位になると血管内の静水圧が低下し、水分が血管外へ移動しにくくなるため、循環血漿量が増加します。この希釈効果により、血漿中のアルブミン濃度は相対的に低下します。これは体位性ヘモダイリューション(血液希釈)と呼ばれます。
- 総カルシウム濃度と負の相関がある。
誤り。
→アルブミンは血中カルシウムの約40~45%を結合して運搬します。
したがって、アルブミン濃度が低下すると、アルブミンと結合しているカルシウムの量も低下するため、総カルシウム濃度はアルブミン濃度に正の相関を示します。アルブミンが低ければ総カルシウムも低くなる傾向があります。負の相関ではありません。
- 健常人では1日1g程度が尿中に排出される。
誤り。
→健常人では、腎臓の糸球体がアルブミンの大部分をろ過しないため、尿中へのアルブミン排泄量は非常に少なく、1日30mg未満が正常とされています。
1g(1000mg)は、明らかな蛋白尿(ネフローゼ症候群では1日3.5g以上)に相当する異常な量です。
答え:3
40 酵素のKm値が10mmol/Lの場合、最大反応速度の95%で反応させるための基質濃度(mmol/L)はどれか。ただし、酵素反応速度はMichaelis-Mentenの式に従うものとする。
- 70
- 95
- 110
- 145
- 190
酵素反応速度はMichaelis-Menten(ミカエリス・メンテン)の式によって導くことができます。
Michaelis-Mentenの式
$$v = \frac{V_{\max} \cdot [S]}{K_m + [S]}$$
与えられている条件は
- Km=10mmol/L
- v=0.95Vmax
なので、式に代入していくと
$$
0.95 \cdot V_{\max} = \frac{V_{\max} \cdot [S]}{10 + [S]}
$$
両辺をVmaxで割ると
$$
0.95 = \frac{[S]}{10 + [S]}
$$
両辺に10+[S]を掛けて整理していきます。
$$
0.95(10 + [S]) = [S]
$$
$$
9.5+0.95 [S]=[S]
$$
$$
9.5=[S]-0.95[S]=0.05[S]
$$
$$
[S] = \frac{9.5}{0.05} = 190
$$
よって、190mmol/Lが答えとなります。
答え:5
41 ビタミンと欠乏症の組合せで正しいのはどれか。
- ビタミンA 新生児メレナ
- ビタミンC 夜盲症
- ビタミンD 巨赤芽球性貧血
- ビタミンE 新生児溶血性貧血
- ビタミンK 脚 気
各ビタミンの主な欠乏症に関する問題です。参考に水溶性ビタミンと脂溶性ビタミンの欠乏症をまとめた表をつけましたので参考にしてください。
★ビタミンと欠乏症一覧
【脂溶性ビタミン】
| ビタミン名 | 主な欠乏症 | 補足事項 |
|---|---|---|
| ビタミンA (レチノール) | 夜盲症、眼球乾燥症、角膜軟化症、皮膚乾燥 | 視覚、上皮細胞の分化、免疫機能に関与 |
| ビタミンD (カルシフェロール) | 小児:くる病 成人:骨軟化症 |
カルシウム・リンの代謝、骨形成に関与 |
| ビタミンE (トコフェロール) | 新生児溶血性貧血、神経症状(運動失調など) | 抗酸化作用、細胞膜の保護に関与 |
| ビタミンK (フィロキノン、メナキノン) | 出血傾向(新生児メレナ、血液凝固障害) | 血液凝固因子の合成に関与、胎盤通過性低い |
【水溶性ビタミン】
| ビタミン名 | 主な欠乏症 | 補足事項 |
|---|---|---|
| ビタミンB1 (チアミン) | 脚気(神経症状、心不全など)、ウェルニッケ脳症 | 糖代謝、神経機能に関与 |
| ビタミンB2 (リボフラビン) | 口角炎、口内炎、舌炎、脂漏性皮膚炎 | 酸化還元反応、エネルギー代謝に関与 |
| ナイアシン (ビタミンB3) | ペラグラ(皮膚炎、下痢、認知症の3D症状) | 糖質・脂質・タンパク質の代謝に関与 |
| ビタミンB6 (ピリドキシン) | 口角炎、舌炎、皮膚炎、貧血、けいれん | アミノ酸代謝、神経伝達物質合成に関与 |
| ビタミンB12 (コバラミン) | 巨赤芽球性貧血、神経症状(亜急性連合性脊髄変性症) | 葉酸とともにDNA合成、赤血球成熟に関与 |
| 葉酸 (ビタミンB9) | 巨赤芽球性貧血、神経管閉鎖障害(胎児) | DNA合成、赤血球成熟に関与 |
| ビタミンC (アスコルビン酸) | 壊血病(出血傾向、貧血、倦怠感) | コラーゲン合成、抗酸化作用、免疫機能に関与 |
| パントテン酸 (ビタミンB5) | 皮膚炎、成長停止、副腎機能低下(まれ) | 補酵素Aの構成成分、エネルギー代謝に関与 |
| ビオチン (ビタミンB7/H) | 皮膚炎、脱毛、神経症状(まれ) | 糖質・脂質・アミノ酸代謝に関与 |
表を参考に各選択肢を見ていきます。
- ビタミンA 新生児メレナ
誤り。
→ビタミンAの欠乏症は、夜盲症、眼球乾燥症などが主な症状です。新生児メレナ(新生児消化管出血)はビタミンKの欠乏と関連が深いです。
- ビタミンC 夜盲症
誤り。
→ビタミンCの欠乏症は壊血病が代表的です。夜盲症はビタミンAの欠乏症です。
- ビタミンD 巨赤芽球性貧血
誤り。
→ビタミンDの欠乏症は、小児ではくる病、成人では骨軟化症が主な症状です。巨赤芽球性貧血はビタミンB12や葉酸の欠乏によって引き起こされます。
- ビタミンE 新生児溶血性貧血
正しい。
→ビタミンEは抗酸化作用を持ち、特に未熟児において欠乏すると溶血性貧血を引き起こすことがあります。
- ビタミンK 脚気
誤り。
→ビタミンKの欠乏症は血液凝固能の低下による出血傾向(新生児メレナなど)が主な症状です。脚気はビタミンB1(チアミン)の欠乏症です。
答え:4
42 脂肪細胞から分泌されるのはどれか。2つ選べ。
- レプチン
- インスリン
- ガストリン
- インクレチン
- アディポネクチン
脂肪細胞から分泌される様々な生理活性物質(アディポサイトカイン)について理解する必要があります。
主なアディポサイトカインとその働き
- アディポネクチン
- 脂肪分解促進、インスリン感受性向上、抗炎症、動脈硬化抑制作用。肥満や糖尿病で減少。
- レプチン
- 摂食抑制、エネルギー消費亢進。飽満感を脳に伝える。肥満で抵抗性が生じることも。
- TNF-α (腫瘍壊死因子アルファ)・IL-6 (インターロイキン-6)
- インスリン抵抗性誘導、炎症促進、動脈硬化促進。肥満で過剰に分泌。
- PAI-1 (プラスミノーゲンアクチベーターインヒビター-1)
- 線溶系(血栓溶解)を抑制し、血栓形成を促進。肥満で増加。
- レジスチン
- インスリン抵抗性誘導。
インスリン、ガストリンなどのよく見るホルモンも選択肢にあるので、消去法でもいけそうですが、それでは完璧ではありません。この問題でしっかりと覚えておくようにしましょう。
選択肢を見ていきましょう。
- レプチン
→脂肪細胞から分泌されるホルモンで、食欲を抑制し、エネルギー消費を促進する働きがあります。「満腹ホルモン」とも呼ばれます。 - インスリン
→膵臓のランゲルハンス島のβ細胞から分泌されるホルモンで、血糖値を下げる働きがあります。 - ガストリン
→胃の幽門前庭部、十二指腸粘膜にあるG細胞から分泌される消化管ホルモンで、胃酸分泌を促進します。 - インクレチン
→主に小腸のK細胞やL細胞から分泌される消化管ホルモン(GIP、GLP-1など)の総称で、血糖値依存的にインスリン分泌を促進します。 - アディポネクチン
→脂肪細胞から分泌されるホルモンで、「善玉アディポサイトカイン」とも呼ばれ、脂肪燃焼の促進、インスリン感受性の向上、抗動脈硬化作用など、様々な健康効果があります。
答え:1と5
43 経口ブドウ糖負荷試験で正しいのはどれか。
- 検体は血清を用いる。
- 妊娠糖尿病の診断に用いられる。
- 試験2時間前まで飲食が可能である。
- 糖尿病と診断された患者に実施する。
- 病型診断に負荷後1時間値が用いられる。
経口ブドウ糖負荷試験(OGTT)について、まとめてみました。
★経口ブドウ糖負荷試験(OGTT)のポイント
- 目的: 糖尿病の診断、耐糖能異常の評価、妊娠糖尿病の診断。
- 前処置: 前日10時間以上絶食。検査中は禁飲食。
- 方法
①空腹時採血(血糖、インスリン)。
②ブドウ糖液(成人75g、小児1.75g/kg)を経口摂取。
③負荷後30分、60分、90分、120分で採血し、血糖値やインスリン値を測定。
(さらに150、180と続ける場合もあり) - 検体: 血漿または血清(フッ化ナトリウム採血管推奨)。
- 診断基準
→糖尿病型
空腹時血糖 ≥126 mg/dL または 2時間値 ≥200 mg/dL
→境界型
空腹時血糖 110 mg/dL≤X<126 mg/dL かつ2時間値140 mg/dL≤X<200 mg/dL
(またはどちらか一方のみ基準を満たす場合)
→正常型
空腹時血糖 <110 mg/dL かつ 2時間値 <140 mg/dL
→妊娠糖尿病
75gOGTTで空腹時 ≥92 mg/dL、1時間値 ≥180 mg/dL、2時間値 ≥153 mg/dL のいずれか1点以上を満たす場合
上記を参考にしつつ、各選択肢のを見ていきましょう。
- 検体は血清を用いる。
微妙(正しくもあるが、誤りでもない笑)
→血糖測定には血漿または血清が用いられますが、通常は血漿が推奨されます。
しかし、血清も使用されることがあるため、この記述が完全に誤りとは言い切れませんが、最も正確な選択肢ではありません。
- 妊娠糖尿病の診断に用いられる。
正しい。
→妊娠糖尿病の診断基準として、経口ブドウ糖負荷試験は国際的にも広く用いられています。
- 試験2時間前まで飲食が可能である。
誤り。
→正確な診断のためには、検査前夜から10時間以上の絶食が必要です。
- 糖尿病と診断された患者に実施する。
誤り。
→OGTTは主に糖尿病の診断や、糖尿病の疑い、または境界型(糖尿病予備群)のスクリーニングに用いられます。
- 病型診断に負荷後1間値が用いられる。
誤り。
→糖尿病の診断には、主に空腹時血糖値と負荷後2時間値が用いられます。(200mg/dL以上)
1時間値は糖尿病型を示すことがありますが、診断基準の中心ではありません。
補足:病型(1型糖尿病か2型糖尿病かなど)の診断には、抗体検査やインスリン分泌能評価などが用いられます。
答え:2
44 短期の栄養指標として用いられる血漿蛋白はどれか。2つ選べ。
- アルブミン
- ハプトグロビン
- セルロプラスミン
- トランスフェリン
- レチノール結合蛋白
栄養状態を評価する血漿タンパク質(栄養指標)の種類と、それぞれの半減期の問題です。
短期間の栄養状態を評価する指標として用いられる血漿タンパク質は、半減期が短いものが適しています。
半減期が長いタンパク質は、過去の栄養状態を反映しやすいため、短期の指標としては不向きです。
★主なrapid turnover protein(RTP)
- トランスサイレチン
- トランスフェリン
- レチノール結合蛋白
選択肢にあるタンパク質の半減期と栄養指標としての役割を見ていきましょう。
- アルブミン:半減期:約2~3週間(約19日)
→半減期が比較的長いため、過去から現在までの長期的な栄養状態の指標として用いられます。
- ハプトグロビン:半減期:約5日
→急性相反応物質であり、炎症や組織破壊などで変動するため、栄養指標としてはあまり用いられません。
- セルロプラスミン:半減期:約4日
→銅の輸送タンパク質であり、急性相反応物質でもあります。炎症などで変動するため、栄養指標としてはあまり用いられません。
- トランスフェリン:半減期:約8~10日
→鉄の輸送タンパク質であり、アルブミンよりも半減期が短いため、アルブミンよりは短期の栄養指標として用いられます。特に鉄欠乏と関連して変動します。
- レチノール結合蛋白 (RBP):半減期:約10~12時間(非常に短い)
→ビタミンA(レチノール)の輸送タンパク質であり、半減期が非常に短いため、数日単位の栄養状態の変化を敏感に反映する短期栄養指標として優れています。
答え:4と5
第71回(AM)病理組織細胞学(45〜58)
▼ クリックすると詳細が開きます
45 組織標本作製において脱灰の適温が最も高いのはどれか。
- 塩酸法
- 硝酸法
- トリクロロ酢酸法
- エチレンジアミン四酢酸〈EDTA〉法
- プランク・リクロ〈Plank-Rychlo〉法
組織標本作製における脱灰は、骨などの硬組織からカルシウムを除去し、薄切できるようにする操作です。
脱灰液の種類によって、作用機序や適温が異なります。
一般的に、酸性の強い脱灰液ほど反応が速く、室温やそれより低い温度で用いられることが多いです。
EDTA法はキレート作用を利用するため、比較的穏やかで時間がかかります。
各脱灰法の適温と特徴を比較してみましょう。
| 脱灰法 | 主な特徴 | 適温(目安) |
|---|---|---|
| 塩酸法 | 強酸性。比較的迅速だが組織損傷大。 | 室温〜30℃ |
| 硝酸法 | 最も強力な酸。非常に迅速だが組織損傷大。 | 室温〜30℃ |
| トリクロロ酢酸法 | 比較的穏やかな酸性。組織損傷が少ない。 | 室温〜30℃ |
| EDTA法 | キレート作用で穏やかに脱灰。組織形態・酵素活性保全に優れる。時間がかかる。 | 室温〜37℃(温度↑で速度↑も、組織損傷注意) |
| プランク・リクロ法 (電解脱灰法) | 電気分解を利用し、電流による発熱で脱灰を加速。迅速。 | 40〜50℃以上(最も高い) |
上表を参考に選択肢を見ていきます。
- 塩酸法
強酸性で作用が速いが、組織損傷のリスクも高い。
一般的に室温(20~25℃)以下で使用されることが多い。
- 硝酸法
非常に強酸性で、塩酸よりも作用が速い。
組織損傷のリスクも高いため、低温(4℃など)で使用されることが多い。
- トリクロロ酢酸法
比較的穏やかな酸性で、骨髄などの微細構造の保存に適している。
室温(20~25℃)で使用されることが多い。
- エチレンジアミン四酢酸〈EDTA〉法
キレート作用によりカルシウムを除去するため、非常に穏やかで組織損傷が少ない。酵素活性や抗原性の保存に優れる。
しかし、脱灰に非常に時間がかかる(数週間~数ヶ月)。
反応速度を上げるために、室温よりやや高い温度(37℃など)でインキュベートすることがある。ただし、高すぎると組織の劣化を招く。
- プランク・リクロ〈Plank-Rychlo〉法
40〜50℃、あるいはそれ以上の温度で効率的に脱灰が行われます。
一般的な酸脱灰法が室温〜30℃程度で行われるのに対し、プランク・リクロ法はより高温で処理されるのが特徴です。迅速な脱灰が可能です。
補足:プランク・リクロ法は電気分解という特殊な方法で強制的に脱灰を加速し、結果的に高温になります。
これは「適温を高く設定できる」というよりは、「高温になってしまうが、それでも迅速性を優先する」ということです。よって、回答としてはEDTA法が正しいことになります。
答え:4(厚労省)(5も答えになるかもしれません)
46 ヘマトキシリンの色出しに使用するのはどれか。2つ選べ。
- 酢 酸
- クエン酸
- アンモニア水
- 炭酸リチウム
- 塩酸アルコール
- ヘマトキシリンは、染色液の状態では赤色(酸性)ですが、組織を染色した後、アルカリ性の環境に置くことで青紫色に発色し、細胞核などを鮮明に染め出します。このアルカリ性の環境を作り出す操作が「色出し」と呼ばれます。
- 色出しの目的は、ヘマトキシリンで染色された組織の核を青色にすることです。これは、アルカリ性の環境で行われます。
上記を踏まえて選択肢を見てみましょう。
- 酢酸
弱酸性です。
→ヘマトキシリンの色出し(青化)はアルカリ性で行われるため、酢酸は色出しには使用しません。
- クエン酸
弱酸性です。
→これも酢酸と同様に、色出しには使用しません。
- アンモニア水
弱アルカリ性です。
→ヘマトキシリンの色出し剤として一般的に用いられます。
- 炭酸リチウム
アルカリ性です。
→ヘマトキシリンの色出し剤として、アンモニア水と同様に広く用いられます。
- 塩酸アルコール
酸性です。
→ヘマトキシリン染色では、分化(過剰に染まった色素を洗い流し、核と細胞質のコントラストを明確にする工程)に用いられます。
★ヘマトキシリンの色出しに使うもの(アルカリ性が多い)
→元々酸性のものを中性〜アルカリ性で中和することで行うことができる。
- 流水
- 温流水
- アンモニア水
- 炭酸リチウム液
- リン酸緩衝食塩液(PBS)
答え:3と4
47 喀痰のPapanicolaou染色標本(別冊No. 8)を別に示す。この細胞で判定するのはどれか。

- 感染の有無
- 腫瘍の組織型
- 病変の進行度
- 検査材料の適性
- 炭粉沈着の程度
写真の鑑別ポイントをまとめてみます。
- 写真の細胞は、淡く泡沫状の細胞質と円形から楕円形の偏在を有する細胞核組織です。
- この細胞は貪食能をもち、肺胞内の異物を除去する働きがあります。
- 細胞質にみられる黒い点状の物質は、 異物 (通常は炭粉など) を貪食しており、塵埃細胞 (ダストセル) とよばれる。
- この細胞は喀痰検体の検査における、検体材料の適性の指標となる。
- 細胞診検査における喀痰細胞診の判定基準において、
喀痰中に肺胞マクロファージ(組織球)を認めない場合は「判定区分A:材料不適、再検査」となる。
(参考)
★各単細胞診の判定クラス一覧
- Class I:陰性異型細胞を認めず、正常またはごく軽度の炎症性変化のみ。
- Class II:炎症性 / 良性異型炎症性変化による細胞の変性や、がん細胞とは断定できない程度の軽度な異型細胞を認める。
- Class III:疑陽性悪性を完全に否定できない異型細胞を認める。がん細胞の疑いがあるが確定できない。
- Class IV:陽性疑い悪性を強く疑わせる異型細胞を認める。ほぼがん細胞と判断される。
- Class V:陽性明らかに悪性細胞を認め、がん細胞と確定診断できる。
直接関係のない表まで出してしましましたが、喀痰細胞診の材料適格基準の一般的な考え方として、喀痰細胞診で重要なのは、「下気道由来の細胞が含まれているか」という点です。
下気道由来の細胞の存在の確認のため肺胞マクロファージ(組織級)を認めない場合は、検査材料の適正なのか不適正かを判定しなければいけません。
答え:4
48 完成した染色標本とパラフィンブロックの照合で確認できるのはどれか。
- 切片の厚さ
- 染色の状態
- 切片の取り違え
- 切片の折れ曲がり
- 脱パラフィン不足
完成した染色標本とパラフィンブロックの照合とは、染色が完了しプレパラートになった標本と、その元となったパラフィン包埋ブロックを比較することです。
この照合によって確認できるのは、両者が同じ患者、同じ組織であるか、という点です。
上記を踏まえて各選択肢について見ていきましょう。
- 切片の厚さ
切片の厚さは、ミクロトームで切る段階で設定されるものであり、染色後の標本やパラフィンブロックを目視で照合しても正確に確認することはできません。また、切片の厚さは染色標本上の組織の透明度などで間接的に推測できることはあっても、直接的な照合項目ではありません。
- 染色の状態
染色の状態(染めムラ、染まり具合など)は、完成した染色標本そのものを見ることで確認できますが、パラフィンブロックとの照合では確認できません。
パラフィンブロックは未染色の組織が含まれているためです。
- 切片の取り違え
パラフィンブロックには通常、患者IDや組織の種類などの情報が記されています。完成した染色標本のスライドにも同様の情報が記されています。この両者の情報を照合することで、異なる患者の組織が誤ってスライドに載っていないか、あるいは異なる組織が載っていないかといった「取り違え」を確実に確認することができます。
- 切片の折れ曲がり
切片の折れ曲がりは、薄切の際に発生するアーチファクトであり、染色標本を見ることで確認できます。パラフィンブロックとの照合で事前に知ることはできません。また、折れ曲がりの有無がブロックとの照合の目的ではありません。
- 脱パラフィン不足
脱パラフィン不足は、染色工程での問題であり、染色標本が白濁したり、染まりが悪かったりすることで判断できます。パラフィンブロックとの照合では、この問題は確認できません。
答え:3
49 肝前性黄疸の原因はどれか。
- 胆管癌
- 溶血性貧血
- 薬剤性肝障害
- アルコール性肝障害
- Dubin-Johnson症候群
- 肝前性黄疸は、肝臓が処理しきれないほどの多量のビリルビンが生成されることによって起こる黄疸です。
- これは、主に赤血球の過剰な破壊(溶血)によって間接ビリルビンが増加することで発生します。
各選択肢を見ていきましょう。
- 胆管癌
胆管が閉塞することで、胆汁の流れが滞り、直接ビリルビンが増加して黄疸を引き起こします。これは肝後性黄疸の原因です。 - 溶血性貧血
赤血球が異常に破壊される(溶血)ことで、ヘモグロビンから生成される間接ビリルビンの量が増加し、肝臓の処理能力を超えて血中に蓄積します。これにより黄疸が生じます。これは肝前性黄疸の典型的な原因です。 - 薬剤性肝障害
薬剤が原因で肝細胞が損傷し、ビリルビンの取り込み、抱合、排泄のいずれかの過程に異常が生じます。これは肝性黄疸の原因です。 - アルコール性肝障害
アルコールの過剰摂取により肝細胞が障害され、ビリルビンの代謝能力が低下します。これも肝性黄疸の原因です。 - Dubin-Johnson症候群
肝臓から胆汁中への直接ビリルビン排泄機能に遺伝的な異常があるため、直接ビリルビンが血中に逆流し、黄疸を引き起こします。これは肝性黄疸(より正確には抱合型高ビリルビン血症を伴う肝性黄疸の一種)に分類されます。
黄疸の分類と原因
| 種類 | 主な原因 | 概要 |
|---|---|---|
| 肝前性黄疸 (溶血性黄疸) |
溶血、自己免疫性溶血性貧血など | 肝臓に入る前にビリルビンが過剰産生される(間接型ビリルビン↑) |
| 肝性黄疸 (肝細胞性黄疸) |
肝炎、肝硬変、薬物性肝障害など | 肝臓でのビリルビンの取り込み・抱合・排泄障害(直接・間接どちらも↑) |
| 肝後性黄疸 (閉塞性黄疸) |
胆石、胆管がん、膵頭部がんなど | 胆道の閉塞により胆汁がうっ滞し、排出できなくなる(直接型ビリルビン↑) |
答え:2
50 PAS反応標本(別冊No. 9)を別に示す。この臓器はどれか。

- 肝 臓
- 食 道
- 腎 臓
- 大 脳
- 脾 臓
設問の写真を見ていきます。
★この写真のポイント
- 腎小体 (ボウマン嚢に囲まれた糸球体) が数多くみられることから腎臓の皮質部分の組織像である
- 周囲には近位尿細管、遠位尿細管も見られる。
- PAS反応により、糸球体、ボウマン嚢、尿細管の基底膜が赤紫色に呈色され、 陽性となっている。
- PAS反応での観察には、腎糸球体において、基底膜の微細な構造変化のみならず、基底膜上の免疫複合体沈着物や硝子様物質も含まれ、膜性糸球体腎炎 (膜性腎症) ではそれら両方が陽性になる。
他臓器の鑑別点としては、
- 肝臓:肝小葉構造、中心静脈、肝細胞索などが観察できる。
- 食道:重曹扁平上皮と粘膜筋腫が観察できる。
- 大脳:神経細胞(ニューロン)、神経膠細胞(グリア)、皮質層構造が観察できる。
- 脾臓:白脾髄と赤脾髄に分かれている様子が観察できる。
答え:3
51 FISH法による乳癌HER2検査の模式図(別冊No. 10)を示す。
HER2とCEP17のシグナル比(HER2/CEP17)で最も近いのはどれか。

- 0.5
- 1.0
- 3.0
- 10.0
- 50.0
HER2/CEP17比を求める
このFISH法によるHER2遺伝子検査図では、各灰色の円が1つの細胞核を表し、
黒丸(●)がHER2シグナル、白丸(○)がCEP17シグナルを表しています。
- 全細胞のHER2シグナルを数える。
- 全細胞のCEP17シグナルを数える。
- HER2/CEP17の比率を警査する。
実際に数えてみます。
黒丸数:49
白丸数:16
比率にすると、3.1となります。
答え:3
52 子宮頸部細胞診のPapanicoloau染色標本の弱拡大写真(別冊No. 11A)と強拡大写真(別冊No. 11B)を別に示す。適切な判定はどれか。


- NILM(陰性)
- LSIL(軽度扁平上皮内病変)
- HSIL(高度扁平上皮内病変)
- SCC(扁平上皮癌)
- Adenocarcinoma(腺癌)
写真のポイントを見ていきます。
- 核の大小不同(核異型)
- 核のクロマチン増加(濃染)
- 核形の不整(円形〜類円形に留まらず、不規則)
- 細胞の形はオタマジャクシ、蛇型を呈している
- 角化型扁平上皮癌の像
答え:4
53 自動固定包埋装置における標本作製工程にないのはどれか。
- 乾 燥
- 脱 脂
- 脱 水
- 脱アルコール
- パラフィン浸透
自動固定包埋装置は、組織をパラフィンブロックにするまでの一連の処理
(脱水、透徹、パラフィン浸透、冷却・包埋)を自動で行う装置です。
各工程について確認しましょう。
- 乾 燥
→組織を水からパラフィンに浸透させる過程で、アルコールで水分を置換するのが「脱水」であり、「乾燥」という独立した工程は通常ありません。 - 脱 脂
→脂肪を多く含む組織の場合に行われる特殊な工程であり、自動固定包埋装置の標準的なルーチンには含まれません。必要に応じて前処理として行われることがあります。 - 脱 水
→組織中の水分をアルコールで置換する必須の工程です。自動装置で行われます。 - 脱アルコール
→「透徹」とも呼ばれ、脱水で用いたアルコールをパラフィンと混ざる溶媒(キシレンなど)で置換する必須の工程です。自動装置で行われます。 - パラフィン浸透
→透徹された組織に融解パラフィンを浸透させる必須の工程です。自動装置で行われます。
また、乾燥させてしまうと組織や細胞へのダメージが大きく、染色性の低下に影響を与えてしまうため、基本的に乾燥は行わないです。
答え:1
54 Grocott染色に用いるのはどれか。2つ選べ。答え違う
- クロム酸
- シュウ酸
- 過ヨウ素酸
- アンモニア銀
- メセナミン銀
Grocott染色(グロコット染色)は、主に真菌やニューモシスチスなどを検出するために用いられる組織染色法です。
この染色は、炭水化物(多糖類)を酸化してアルデヒド基を生成し、そのアルデヒド基が銀液と反応して黒く染まるという原理に基づいています。
Grocott染色に用いられる主要な試薬は以下の通りです。
★グロコット染色(GMS染色)に用いられる主な試薬
| 試薬名 | 主な役割・作用 |
|---|---|
| クロム酸、過ヨウ素酸 | 組織成分を酸化し、アルデヒド基を生成させる。 |
| メテナミン銀溶液 | アルデヒド基と反応し、銀を還元・沈着させ黒褐色に染める。 |
| 塩化金 | 銀の沈着を強化し、背景のトーンを整える。 |
| チオ硫酸ナトリウム | 未反応の銀イオンを除去し、非特異的な染色を防ぐ(定着)。 |
| 対比染色液 | 背景の組織を染める(ライトグリーン、サフラニンなど)。 |
※六価クロム酸は毒性が強く、産業界では使用が禁止されつつある。
それぞれの選択肢を見ていきましょう。
- クロム酸
→菌体などの多糖類を酸化し、アルデヒド基を生成させる。 - シュウ酸
→Grocott染色では通常使用されません。 - 過ヨウ素酸
→多菌体などの多糖類を酸化し、アルデヒド基を生成させる(クロム酸の代替または改良法で使用される酸化剤)。 - アンモニア銀
→銀染色の一種ですが、Grocott染色では「メセナミン銀」が特異的に用いられます。 - メセナミン銀
→アルデヒド基と反応して真菌を黒く染める主要な試薬です。
したがって、Grocott染色に用いられるのは過ヨウ素酸とメセナミン銀です。
答え:1と5(厚労省の回答はそうなっていますが、3もだと思います)
55 発がん性が指摘されているのはどれか。
- キシレン
- メタノール
- パラフィン
- ホルムアルデヒド
- エチレンジアミン四酢酸(EDTA)
この問題では提示された化学物質の中から、発がん性が指摘されているものを特定します。
自身を守るためにも試薬に対する知識は必要です。この機会に覚えておきましょう。
★IARCによる発がん性分類
- グループ1: ヒトに対して発がん性がある
→ヒトでの発がん性を示す十分な証拠がある。
- グループ2A: ヒトに対しておそらく発がん性がある
→ヒトでの証拠は限定的だが、実験動物での十分な証拠がある。 - グループ2B: ヒトに対して発がん性があるかもしれない
→ヒトでの証拠も実験動物での証拠も限定的、または不十分。 - グループ3: ヒトに対する発がん性を分類できない
→ヒト、実験動物ともに発がん性を示す証拠が不十分。
※グループ1が最も発がん性があるとされる。
各選択肢を見ていきます。
- キシレン
組織処理における脱アルコール(透徹)工程で広く使用される有機溶媒です。
発がん性については、国際がん研究機関(IARC)による分類では、グループ3とされています。
- メタノール
溶解剤や燃料などに使用されるアルコールの一種です。
発がん性については、IARCではグループ3とされています。
毒性としては、視神経障害や中枢神経抑制などが知られています。
- パラフィン
組織包埋に使用されるワックスです。発がん性については、一般的に安全性が高いとされており、IARCによる発がん性分類の対象外です。
- ホルムアルデヒド
組織の固定液(10%中性ホルマリン溶液として)として広く使用されます。
発がん性が指摘されています。 IARCはホルムアルデヒドをグループ1に分類しており、特に鼻咽頭がんや白血病との関連が報告されています。
日本では「特定化学物質障害予防規則」における特定化学物質(第二類)にも指定されていて、作業環境中の管理濃度が0.1ppmとして定められている。
- エチレンジアミン四酢酸(EDTA)
脱灰剤やキレート剤として使用されます。
発がん性については、一般的に発がん性は低いとされており、IARCによる発がん性分類の対象外です。
選択肢の中で、発がん性が明確に指摘されており、IARCによってヒトに対する発がん性がある(グループ1)と分類されているのはホルムアルデヒドです。
答え:4
56 疾病の内因となるのはどれか。
- 遺 伝
- 温 度
- 感 染
- 紫外線
- 放射線
疾病の原因は大きく内因と外因に分けられます。
★疾病の原因:内因と外因
| 分類 | 定義 | 具体例 |
|---|---|---|
| 内因 | 個体の内部に存在する要因 | 人種、遺伝的素因、体質、免疫状態、年齢、性別など |
| 外因 | 個体の外部に存在する要因 |
|
表を参考に各選択肢を見ていきましょう。
- 遺 伝: 個体の持つ遺伝子情報であり、個体の内部に存在する素因です。これは内因です。
- 温 度: 外部環境の物理的因子です。これは外因です。
- 感 染: 細菌やウイルスなどの病原体(生物的因子)によるものです。これは外因です。
- 紫外線: 外部環境の物理的因子です。これは外因です。
- 放射線: 外部環境の物理的因子です。これは外因です。
以上より、疾病の内因となるのは遺伝です。
答え:1
57 アミロイドの染色法はどれか。
- Congo red染色
- Alcian blue染色
- Ziehl-Neelsen染色
- Sudan black B染色
- Masson trichrome染色
アミロイドは、体内で異常に蓄積するタンパク質性の物質で、様々な臓器に沈着し機能障害を引き起こします。アミロイドの診断には、特定の染色法が用いられます。
各選択肢を見ていきましょう。
- Congo red染色(コンゴーレッド染色)
アミロイドの検出に最も特異的かつ標準的に用いられる染色法です。
★Congo red染色(コンゴーレッド染色)
- 最も広く用いられる、アミロイドの検出に必須の染色法です。
- アミロイドが橙赤色に染まります。
- この染色像は、偏光顕微鏡で観察すると、アミロイドが黄緑色の偏光(アップルグリーンバイレフリンゼンス)を示すのが特徴です。
この黄緑色の複屈折は、アミロイドのβシート構造に由来するもので、アミロイド沈着の確定診断に非常に重要です。
- Alcian blue染色(アルシアンブルー染色)
→酸性ムコ多糖類を青色に染色するのに用いられます。粘液成分の検出に有効です。
- Ziehl-Neelsen染色(チール・ネルゼン染色)
→抗酸菌(結核菌など)の検出に用いられる染色法です。ミコール酸を含む細胞壁を持つ細菌が赤く染色されます。
- Sudan black B染色(ズダンブラックB染色)
→脂質を黒色に染色するのに用いられます。脂肪組織や脂肪滴の検出に有効です。
- Masson trichrome染色(マッソントリクローム染色)
→コラーゲン線維を青色または緑色に、筋線維や赤血球を赤色に、核を黒色に染色するのに用いられる、結合組織の線維成分を染め分ける染色法です。
アミロイドの染色法はCongo red染色です。他にもアミロイドの染色法はありますが、コンゴーレッド染色が最も頻出かと思います。
★その他アミロイド染色
- direct fast scarlet染色(DFS染色)(橙赤色)
- Dylon染色(橙赤色)
- toluidine bleu染色(赤紫色)
- thioflavinT(ThT)染色(黄色蛍光色)
などがあります。
答え:1
58 病理解剖時に摘出された臓器のホルマリン固定後の肉眼写真(別冊No. 12)を別に示す。臓器はどれか。

- 肺
- 肝 臓
- 腎 臓
- 膵 臓
- 脾 臓
設問の肉眼写真の特徴を挙げてみます。
- 肉眼写真が肺であることを示唆しています。
- 3葉であることから右肺と特定。
- 表面は臓側胸膜に覆われ滑らか。
- 色はベージュ〜淡いピンク色だが、喫煙で黒変することもある。
- 高さ24〜25cm、重さ男性で650〜720g、女性で480〜510g。
もう画像で覚えてしまった方が簡単だと思います。強いていうのであれば、三葉であることと、黒色変化していることから肺であることが推察できます。
他の選択肢の臓器の特徴を簡潔にまとめます。
- 肝臓: 赤褐色で幅25cm、重さ1,200gほど。
- 腎臓: そら豆形で長さ10cm、重さ130gほど。
- 膵臓: 長さ15cm前後の細長い構造、重さ74gほど。
- 脾臓: 腎臓に比べてやや扁平な長楕円形、110g前後の臓器。
答え:1
第71回(AM)臨床血液学(59〜67)
▼ クリックすると詳細が開きます
59 血栓形成を抑制するのはどれか。
- ADP
- セロトニン
- エピネフリン
- トロンボキサンA2
- プロスタサイクリン
- 血栓形成は、血管損傷部位で血液が凝固し、血小板が凝集して血栓が作られる複雑なプロセスです。
- このプロセスには、血小板の活性化と凝集を促進する因子と、それを抑制する因子が存在します。
選択肢の物質はそれらの役割を担うものです。
それでは、各選択肢を見ていきましょう。
- ADP (アデノシン二リン酸)
血小板の顆粒から放出され、他の血小板を活性化し、凝集を促進する強力な因子です。
血栓形成を促進します。
- セロトニン
血小板が活性化されると放出され、血管収縮作用を持ち、血小板凝集を促進します。
血栓形成を促進します。
- エピネフリン
カテコールアミンの一種で、血小板の凝集を増強する作用があります。
血栓形成を促進します。
- トロンボキサンA2 (TXA2)
血小板自身で産生されるプロスタグランジンの一種で、強力な血管収縮作用と血小板凝集作用を持ちます。
血栓形成を促進します。
- プロスタサイクリン (PGI2)
主に血管内皮細胞から産生されるプロスタグランジンの一種です。
強力な血管拡張作用と、血小板凝集抑制作用を持っています。
血管内皮細胞が健康な状態ではプロスタサイクリンを産生し、血栓形成を抑制して血管内での血栓を防ぐ役割を果たします。
以上のことから、血栓形成を抑制するのはプロスタサイクリンです。
答え:5
60 髄塗抹標本の染色法と対象細胞の組合せで陽性とならないのはどれか。
- 鉄染色 環状鉄芽球
- PAS染色 正常赤芽球
- ペルオキシダーゼ染色 好酸球
- 特異的エステラーゼ染色 好中球
- 非特異的エステラーゼ染色 巨核球
骨髄塗抹標本の染色法とその対象細胞について、各組み合わせの正誤を判断します。
特殊染色をどの鑑別に使用するかをまとめておきましょう。
★骨髄塗抹標本:特殊染色と関連情報
| 染色法 | 染色対象 | 反応細胞(陽性) | 反応色調 | 主な対象疾患/目的 |
|---|---|---|---|---|
| 鉄染色 | 細胞内鉄 | 環状鉄芽球、鉄芽球、マクロファージ | 青色 | 鉄芽球性貧血、MDSにおける環状鉄芽球検出 |
| PAS染色 | ムコ多糖類(グリコーゲン) | 正常赤芽球、リンパ芽球(ALL)、巨核球 | 赤紫色~赤褐色 | ALL診断(粗大顆粒状)、赤白血病診断(びまん性) |
| ペルオキシダーゼ染色 | ペルオキシダーゼ活性 | 顆粒球系細胞、好酸球、一部単球 | 黒褐色 | AMLの顆粒球系分化同定 |
| 特異的エステラーゼ染色 | 顆粒球系特異エステラーゼ活性 | 顆粒球系細胞 | 赤褐色 | AMLの顆粒球系分化同定(M1, M2, M3) |
| 非特異的エステラーゼ染色 | 単球系特異エステラーゼ活性 | 単球系細胞、組織球 | 赤褐色 | AMLの単球系分化同定(M4, M5)※NaF阻害あり |
- 鉄染色 (Perls’ Prussian blue stain) – 環状鉄芽球
鉄染色は、細胞内の鉄(特にヘモジデリン)を検出するのに用いられます。
環状鉄芽球(核周の1/3以上に5個以上の鉄顆粒が分布するもの)は、鉄染色で核の周囲にリング状に鉄顆粒が染まります。
- PAS染色 (Periodic acid-Schiff stain) – 正常赤芽球
PAS染色は、細胞内の糖原(グリコーゲン)やムコ多糖などを赤紫色に染める染色です。
正常な赤芽球は、成熟するにつれて糖原がほとんどなくなり、PAS染色では陰性または非常に弱い陽性を示します。
一方で、赤白血病(M6型AML)の赤芽球は異常に糖原を蓄積し、PAS強陽性を示すことがあります。質問は「正常赤芽球」であるため、陽性とはなりません。
- ペルオキシダーゼ染色 (Peroxidase stain) – 好酸球
ペルオキシダーゼ染色は、ミエロペルオキシダーゼ(MPO)活性を検出する染色です。
好酸球は、顆粒内にMPOとは異なる特異的なペルオキシダーゼを持つため、この染色で強く陽性に染まります(好中球も陽性)。
- 特異的エステラーゼ染色 (Specific esterase stain) – 好中球
特異的エステラーゼ染色は、骨髄球系の細胞、特に”好中球系”の細胞(骨髄芽球、前骨髄球、骨髄球、後骨髄球、桿状核球、分葉核球)が強く陽性を示します。
- 非特異的エステラーゼ染色 (Non-specific esterase stain; NSE) – 巨核球
非特異的エステラーゼ染色は、単球系細胞が強く陽性を示しますが、NaF(フッ化ナトリウム)で活性が抑制されます。巨核球は、この非特異的エステラーゼ染色で陽性を示すことがあります。
答え:2
61 JAK2変異の検出が診断に有用なのはどれか。
- 骨髄異形成症候群
- 真性赤血球増加症
- 慢性骨髄性白血病
- 慢性リンパ性白血病
- 原発性マクログロブリン血症
JAK2 (Janus kinase 2) 遺伝子変異は、特定の血液疾患(骨髄増殖性腫瘍:MPN)の病態形成に深く関与しており、これらの疾患の診断において非常に重要なマーカーとなります。
- 真性赤血球増加症
- 本態性血小板血症
- 原発性骨髄線維症
これらの疾患では、”JAK2 V617F変異”が高頻度で検出され、診断マーカーとして非常に重要です。
各選択肢について見ていきましょう。
- 骨髄異形成症候群 (MDS)
MDSは造血幹細胞のクローン性疾患ですが、JAK2変異が直接的な診断基準となることは稀です。
- 真性赤血球増加症
真性赤血球増加症は、骨髄増殖性腫瘍の一つで、赤血球、白血球、血小板のすべてが増加する特徴があります。90%以上の真性赤血球増加症の患者 ”JAK2 V617F” 変異が検出されます。 この変異は、エリスロポエチンなどのサイトカインがなくても造血細胞が異常に増殖する原因となります。
- 慢性骨髄性白血病 (CML)
CMLの診断には、特徴的な遺伝子異常である “BCR-ABL融合遺伝子”(フィラデルフィア染色体)の検出が必須です。
- 慢性リンパ性白血病 (CLL)
CLLはリンパ球系の腫瘍であり、診断には細胞表面マーカー解析や特定の染色体異常
(13q欠失、11q欠失など)が用いられます。
- 原発性マクログロブリン血症:
B細胞系のリンパ形質細胞性リンパ腫の一種で、IgMモノクローナル蛋白を産生します。
この疾患の主要なドライバー変異はMYD88 L265P変異です。
答え:2
62 巨核球で誤っているのはどれか。
- 正常成熟巨核球は多倍体となる。
- 巨核球の平均直径は200μmである。
- トロンボポエチンは巨核球を分化成熟させる。
- 1つの巨核球は2,000個程度の血小板を産生する。
- 巨核球は血小板糖蛋白質〈GP〉Ⅱb/Ⅲaを発現する。
巨核球は血小板の産生を担う骨髄の非常に大きな細胞です。その特徴を以下にまとめましたので参考にしてください。
★巨核球の特徴
- 多倍体(Polyploidy)
→正常成熟巨核球の最も特徴的な性質の一つです。DNA複製が複数回行われるにもかかわらず細胞分裂が起こらないため、核が肥大し、多倍体(例: 8N, 16N, 32N, 64N)となります。これにより、巨大な細胞質が形成され、大量の血小板を産生できるようになります。 - 巨核球の平均直径は約40~56μmとされます。
- 血小板産生: 巨核球は血小板の唯一の産生細胞です。成熟した巨核球の細胞質から、細胞膜がちぎれるようにして約2,000~4,000個の血小板が産生されます。
- トロンボポエチン(TPO)
→肝臓や腎臓などで産生されるホルモンで、巨核球系の造血幹細胞から巨核球への分化、増殖、成熟を強力に促進します。 - 血小板糖タンパク質(GP)の発現
→巨核球は、最終的に血小板となる細胞質膜に、血小板の機能に不可欠な様々な糖タンパク質を発現しています。
代表的なものとして、GPⅡb/Ⅲa(フィブリノゲン受容体)やGPⅠb/Ⅸ/Ⅴ(フォン・ヴィルブランド因子受容体)などがあります。
これらの糖タンパク質は、血小板凝集や接着に重要な役割を果たします。
上記を参考に各選択肢の正誤を判断していきましょう。
- 正常成熟巨核球は多倍体となる。
巨核球は、核内倍加(DNA複製は行うが、細胞分裂は行わない)という特殊なプロセスを経て成熟し、非常に大きな細胞となります。これにより、核のDNA量が増え、倍数性が高まります(多倍体化)。
- 巨核球の平均直径は200μmである。
成熟した巨核球は体内で最も大きな細胞の一つですが、その平均直径は一般的に約40〜56μm程度です。200μmは大きすぎます。
- トロンボポエチンは巨核球を分化成熟させる。
トロンボポエチン(TPO)は、主に肝臓や腎臓で産生されるサイトカインで、巨核球の増殖、分化、成熟、そして血小板産生を強力に促進します。
- 1つの巨核球は2,000個程度の血小板を産生する。
1つの成熟した巨核球から、数千個(一般的には2,000〜4,000個程度)の血小板が産生されると言われています。
- 巨核球は血小板糖蛋白質〈GP〉Ⅱb/Ⅲaを発現する。
GPⅡb/Ⅲa(インテグリンαIIbβ3)は、血小板の表面に存在する主要な接着分子であり、血小板凝集においてフィブリノゲンと結合する受容体です。巨核球は血小板の前駆細胞であるため、このGPⅡb/Ⅲaなどの血小板特異的な表面抗原を発現しています。
以上より誤っているのは、その平均直径が200μmであるとする記述です。
答え:2
63 血液細胞数測定の模式図(別冊No. 13)を別に示す。
この測定で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 交流電流を用いる。
- 破砕赤血球と血小板を区別できる。
- パルス電圧は細胞の重量に比例する。
- 溶血処理した後に白血球を計測する。
- 細孔を通過するときの電気抵抗の変化を測定する。
電気抵抗法(コールカウンター原理)についての問題です。
選択肢を正しく直していきます。
誤っている箇所を正しく直すと以下になります。
- 直流電流を用いる。
- 破砕赤血球と血小板は体積が同じなので区別ができないことがある。
- 細胞の体積に比例し、パルス電圧も比例する。
④と⑤は正しいです。
答え4と5
64 赤血球の封入体でないのはどれか。
- Cabot環
- Heinz小体
- Russell小体
- 好塩基性斑点
- Howell-Jolly小体
赤血球の封入体とは、赤血球内に存在する異常な構造物のことです。これらは、特定の疾患や状態を示唆することがあります。
- Cabot環(カボット環)
赤血球内に見られるリング状または8の字型の好塩基性の封入体です。
核膜の残存物または有糸分裂紡錘体の残存物と考えられており、重症貧血、骨髄異形成症候群などで見られます。
- Heinz小体(ハインツ小体)
変性したヘモグロビンが赤血球内に凝集したものです。
通常、超生体染色(New Methylene Blue染色など)で青色顆粒として確認されます。溶血性貧血、不安定ヘモグロビン症などで見られます。
- 好塩基性斑点(Basophilic stippling)
未成熟な赤血球(網赤血球)内に見られるリボソームの凝集物で、不規則な青紫色の斑点として見えます。
鉛中毒、重症貧血、骨髄異形成症候群、サラセミアなどで増加します。
- Howell-Jolly小体(ハウェル・ジョリー小体)
赤血球内に残存するDNAの断片です。
脾臓で通常除去されますが、脾臓摘出後、脾機能低下、重症貧血、巨赤芽球性貧血などで見られます。
各選択肢について見ていきましょう。
- Cabot環 (Cabot rings)
赤血球内に見られる、ループ状または8の字型の青紫色の構造物です。核分裂の異常な残骸や、微小管の残存物と考えられており、重症貧血や骨髄異形成症候群などで見られます。
- Heinz小体 (Heinz bodies)
変性したヘモグロビンが凝集してできる封入体です。通常、超生体染色(例えばブリリアントクレシルブルー染色)で観察されます。G6PD欠損症や不安定ヘモグロビン症、酸化ストレスによって引き起こされます。
- Russell小体 (Russell bodies)
形質細胞の細胞質内に見られる、過剰に産生された免疫グロブリンが蓄積した均一な好酸性小体です。
多発性骨髄腫(MDS)などの形質細胞性疾患で観察されます。これは赤血球の封入体ではありません。
- 好塩基性斑点 (Basophilic stippling)
赤血球内に見られる、青紫色の微細な顆粒状の封入体です。リボソームやRNAの凝集物と考えられており、鉛中毒や重症貧血、サラセミアなどで見られます。
- Howell-Jolly小体 (Howell-Jolly bodies)
赤血球内に見られる、円形または卵円形の濃染性の小体です。核分裂後に残存したDNAの断片と考えられており、脾臓摘出後、溶血性貧血、骨髄異形成症候群などで見られます。
したがって、赤血球の封入体でないのはRussell小体です。
答え:3
65 胎生中期において主要な造血組織はどれか。
- 肝 臓
- 脾 臓
- 卵黄囊
- 骨髄(脊椎骨)
- 骨髄(大腿骨)
胎生期の造血組織は、発生段階によってその主要な部位が変化します。
増結組織の主要な部位
- 胎生初期(妊娠3週~3か月頃): 卵黄嚢で造血が始まります。
- 胎生中期(妊娠3か月~7か月頃): 造血の中心は肝臓へと移行し、最も主要な造血組織となります。
この時期には、脾臓でも造血が見られますが、肝臓ほど活発ではありません。 - 胎生後期~出生後: 造血の中心は骨髄へと移行します。出生後は骨髄が主要な造血組織となります。
選択肢を見てみましょう。
- 肝 臓: 胎生中期において、主要な造血組織となります。
- 脾 臓: 胎生中期に一部造血を行いますが、肝臓ほど主要ではありません。
- 卵黄囊: 胎生ごく初期の主要な造血組織です。
- 骨髄(脊椎骨): 胎生後期から出生後にかけての主要な造血組織です。
- 骨髄(大腿骨): 胎生後期から出生後にかけての主要な造血組織であり、特に長管骨の骨髄は成人では徐々に造血機能を失い脂肪髄に置き換わります(近位部を除く)。
胎生中期において主要な造血組織は肝臓です。
答え:1
66 血中半減期が最も短いのはどれか。
- プロトロンビン
- 第Ⅴ因子
- 第Ⅶ因子
- 第Ⅸ因子
- 第Ⅹ因子
血液凝固因子はそれぞれ異なる半減期を持っています。血中半減期が短いほど、その因子が血中に留まる時間が短く、欠乏症や薬剤(ワルファリンなど)の影響が早期に現れやすいとされます。
★血液凝固因子の半減期
| 凝固因子 | 半減期(目安) | 補足事項 |
|---|---|---|
| 第Ⅶ因子 | 約3〜6時間 | 最も短い半減期。ワルファリンの効果が最初に現れる。 |
| 第Ⅸ因子 | 約24時間 | ビタミンK依存性凝固因子。血友病Bで欠損。 |
| 第Ⅹ因子 | 約24〜48時間 | ビタミンK依存性凝固因子。 |
| プロトロンビン (第Ⅱ因子) | 約60〜72時間 | ビタミンK依存性凝固因子。半減期が最も長い。 |
| 第Ⅴ因子 | 約12〜36時間 | ビタミンK非依存性凝固因子。 |
上表を参考にこれらの凝固因子の半減期を比較すると、第Ⅶ因子が最も短いことがわかります。
この短い半減期のため、ビタミンK欠乏症やワルファリン投与の初期に、PT(プロトロンビン時間)が延長する原因となります(PTは第Ⅶ因子の外因系凝固経路を反映するため)。
答え:3
67 血小板数をBrecher-Cronkite法にて目視した。用いた計算板(Burker-Turk)の区画(別冊No. 14)を別に示す。100倍に希釈した血液を用いた図中オレンジ色枠内の任意の5つの中区画のカウントは(14,16,13,12,15)であった。血液1μL中の血小板数で正しいのはどれか。

- 3,500
- 7,000
- 70,000
- 350,000
- 700,000
★問題におけるBrecher-Cronkiteの考え方
- 中区画の五個の容積は0.2[mm]×0.2[mm]×0.1[mm]×5で0.02μLとなる。
- 中区画5個の血小板数(14+16+13+12+15=70)
- 合計70個の血小板があれば、希釈倍数の100と、1μLへの容積換算の50を掛けて70×50×100=350000/μLの血小板数となる。
※容積換算が肝かなと考えます。以下に考え方を載せます。
- 数えた容積の計算
- Brecher-Cronkite法で血小板を数えるのは、血球計算盤の「中区画の5個の容積」です。
- 1つの中区画の容積は、0.2mm × 0.2mm × 0.1mm = 0.004 mm³ です。
- これが5個分なので、合計の容積は 0.004 mm³ × 5 = 0.02 mm³ となります。
- 単位換算
- 1 mm³ (立方ミリメートル) は 1 μL (マイクロリットル) と同じです。
- したがって、血小板を数えた合計容積は 0.02 μL です。
- 1μLへの換算係数
- 私たちは「1μLあたりの血小板数」を求めたいわけです。
- 実際に数えたのは0.02μL分の血小板です。
- 0.02μLを1μLにするには、何倍すればよいかを考える。
- 1 μL ÷ 0.02 μL = 50
答え:4
第71回(AM)臨床微生物学(68〜78)
▼ クリックすると詳細が開きます
68 原核生物はどれか。
- Aspergillus fumigatus
- Cryptococcus neoformans
- Microsporum canis
- Mycoplasma pneumoniae
- Pneumocystis jirovecii
生物は大きく原核生物と真核生物に分類されます。
- 原核生物 (Prokaryote)
→核膜を持たない細胞で、DNAは細胞質中に分散しています。ミトコンドリアやその他の膜結合オルガネラも持ちません。- 細菌、マイコプラズマ、リケッチア、クラミジアなど
- 真核生物 (Eukaryote)
→核膜を持つ細胞で、DNAは核の中にあります。ミトコンドリア、小胞体、ゴルジ体などの膜結合オルガネラも持ちます。- 動物、植物、藻類、真菌、原虫など
各選択肢の生物がどちらに分類されるかを見ていきましょう。
- Aspergillus fumigatus (アスペルギルス・フミガータス)
カビの一種です。カビは真菌であり、真核生物です。
- Cryptococcus neoformans (クリプトコッカス・ネオフォルマンス)
酵母型真菌の一種です。真菌であるため、真核生物です。
- Microsporum canis (ミクロスポルム・カニス)
皮膚糸状菌(白癬菌)の一種です。真菌であるため、真核生物です。
- Mycoplasma pneumoniae (マイコプラズマ・ニューモニエ)
細菌の一種で、細胞壁を持たないのが特徴です。細菌は原核生物です。
- Pneumocystis jirovecii (ニューモシスチス・イロベチイ)
以前は原虫に分類されていましたが、現在は遺伝子解析の結果から真菌の仲間であることがわかっています。真菌であるため、真核生物です。
答え:4
69 オキシダーゼ試験陰性を示すのはどれか。2つ選べ。
- Acinetobacter baumannii
- Bordetella pertussis
- Burkholderia cepacia
- Pseudomonas aeruginosa
- Stenotrophomonas maltophilia
オキシダーゼ試験は、細菌がシトクロムcオキシダーゼという酵素を持っているかどうかを調べる検査です。
この酵素を持つ菌は陽性、持たない菌は陰性となります。グラム陰性桿菌の鑑別に重要な試験の一つです。
★オキシダーゼ試験陰性を示す主な細菌グループ
語呂:腸内細菌科は「NO」!
- 腸内細菌科(Enterobacteriaceae)のほとんど
- 大腸菌 (Escherichia coli)
- サルモネラ (Salmonella spp.)
- 赤痢菌 (Shigella spp.)
- クレブシエラ (Klebsiella spp.)
- プロテウス (Proteus spp.)
- など 腸内細菌科は、グラム陰性桿菌の中でも特に重要なグループであり、オキシダーゼ陰性がその鑑別点の一つとなります。
- 嫌気性菌の一部
★オキシダーゼ試験陽性を示す主な細菌グループ
語呂:「偽ビーカー(ギビーかー)」
- 偽(ギ) → Pseudomonas (シュードモナス属)
- ビ → Vibrio (ビブリオ属)
- ー → (特に意味なし、音合わせ)
- カ → Campylobacter (カンピロバクター属)
- ー → (特に意味なし、音合わせ)
- カ → Neisseria (ナイセリア属) (こちらは「カ」を「コッカス」と連想してナイセリアの「球菌」と繋げる人もいます)
- シュードモナス属 (Pseudomonas spp.)
- ナイセリア属 (Neisseria spp.)
- ビブリオ属 (Vibrio spp.)
- カンピロバクター属 (Campylobacter spp.)
- ヘリコバクター属 (Helicobacter spp.)
- パストゥレラ属 (Pasteurella spp.)
- ボルドテラ属 (Bordetella spp.)
- 好気性菌の多く
★まとめ
オキシダーゼ試験は、特にグラム陰性桿菌の鑑別において非常に重要なスクリーニング検査です。腸内細菌科の多くの菌がオキシダーゼ陰性であるという点が、国家試験で頻繁に問われるポイントとなります。
各菌のオキシダーゼ試験の結果は以下の通りです。
- Acinetobacter baumannii (アシネトバクター・バウマンニ)
オキシダーゼ試験陰性の菌です。非発酵グラム陰性桿菌ですが、Pseudomonas属などとはこの点で鑑別されます。
- Bordetella pertussis (ボルデテラ・パータシス)
オキシダーゼ試験陽性の菌です。百日咳の原因菌として知られています。
- Burkholderia cepacia (ブルクホルデリア・セパシア)
オキシダーゼ試験陽性の菌です。多剤耐性菌として知られ、嚢胞性線維症患者などで問題となります。
- Pseudomonas aeruginosa (シュードモナス・アエルギノーサ)
オキシダーゼ試験陽性の菌です。非発酵グラム陰性桿菌の代表的なもので、緑膿菌としてよく知られています。
- Stenotrophomonas maltophilia (ステノトロフォモナス・マルトフィリア)
オキシダーゼ試験陰性の菌です。非発酵グラム陰性桿菌で、これも多剤耐性を示すことがあります。
したがって、オキシダーゼ試験陰性を示すのは、Acinetobacter baumanniiとStenotrophomonas maltophiliaです。
答え:1と5
70 Geckler分類を行う場合の顕微鏡倍率はどれか。
- 40倍
- 100倍
- 200倍
- 400倍
- 1,000倍
★Geckler分類
- Geckler分類は、喀痰(痰)の品質評価に用いられる方法で、顕微鏡下で扁平上皮細胞と白血球の数をカウントしてグループ1〜6に判定します。
- Geckler分類を行う際の顕微鏡倍率は、100倍(対物レンズ10倍 × 接眼レンズ10倍)と定められています。
- この倍率で視野内の細胞数を評価することで、検体が上気道の唾液で汚染されているか、それとも下気道からの良質な喀痰であるかを判断します。
※参考(他の倍率の使い方)とまとめた表
- 40倍: さらに低倍率で、全体像を把握するのに使われることがあります。
- 200倍、400倍: 細菌の形態観察や細胞の詳細な観察に用いられる倍率です。
- 1000倍: 油浸レンズを使用する倍率で、個々の細菌の詳細な形態や配列を確認するのに使われます。

上記より、GecKler分類を行う場合の顕微鏡倍率は100倍です。
答え:2
71 有芽胞菌はどれか。
- Bacillus anthracis
- Bordetella pertussis
- Cutibacterium acnes
- Klebsiella pneumoniae
- Moraxella catarrhalis
有芽胞菌とは、過酷な環境条件下でも生き残るために芽胞を形成する能力を持つ細菌のことです。芽胞は、非常に耐久性が高く、熱、乾燥、消毒薬などに対して強い抵抗性を示します。
★有芽胞菌一覧
- Bacillus属(バチルス属): 好気性または通性嫌気性のグラム陽性桿菌。
- Bacillus anthracis(炭疽菌): 病原性が高く、バイオテロ対策としても重要。
- Bacillus cereus(セレウス菌): 食中毒の原因菌(嘔吐型と下痢型)。
- Bacillus subtilis(枯草菌、納豆菌): 環境中に広く存在し、納豆菌としても利用される。
- Clostridium属(クロストリジウム属): 偏性嫌気性のグラム陽性桿菌。
- Clostridium tetani(破傷風菌): 破傷風の原因菌。
- Clostridium botulinum(ボツリヌス菌): ボツリヌス症(食中毒)の原因菌。毒素は医療にも利用される。
- Clostridium perfringens(ウェルシュ菌): ガス壊疽や食中毒の原因菌。
- Clostridioides difficile(クロストリディオイデス・ディフィシル): 偽膜性大腸炎の原因菌として近年注目されている。
各選択肢の菌について見ていきましょう。
- Bacillus anthracis (バチルス・アントラシス)
炭疽菌として知られ、グラム陽性の桿菌です。この菌は芽胞を形成します。土壌中に芽胞として存在し、感染源となります。
- Bordetella pertussis (ボルデテラ・パータシス)
百日咳菌として知られるグラム陰性の球桿菌です。
- Cutibacterium acnes (クチバクテリウム・アクネス)
以前はPropionibacterium acnesと呼ばれ、尋常性ざ瘡(ニキビ)の原因菌として知られるグラム陽性の桿菌です。嫌気性菌。
- Klebsiella pneumoniae (クレブシエラ・ニューモニエ)
肺炎桿菌として知られるグラム陰性の桿菌です。日和見感染症の原因菌としてよく見られます。
- Moraxella catarrhalis (モラクセラ・カタラーリス)
グラム陰性の球菌で、中耳炎や副鼻腔炎、気管支炎などの原因菌となります。
表にもありますが、有芽胞菌はBacillus anthracisです。
答え:1
72 細菌と分離培地の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。
- Aeromonas hydrophila TCBS寒天培地
- Bacteroides fragilis BBE寒天培地
- Campylobacter jejuni NAC寒天培地
- Clostridioides difficile CCFA培地
- Neisseria meningitidis PPLO寒天培地
細菌を特定の培地で分離・培養することは、微生物検査において重要なステップです。それぞれの細菌に適した分離培地を選びましょう。
- Aeromonas hydrophila (エロモナス・ハイドロフィラ) – TCBS寒天培地
- TCBS寒天培地(Thiosulfate-Citrate-Bile Salts-Sucrose Agar)は、主にVibrio属(ビブリオ属)細菌の分離に用いられる選択分離培地です。
Vibrio属はスクロースを分解して黄色コロニーを形成することが特徴です。
Aeromonas属は普通寒天培地、DHL寒天培地、SS寒天培地に発育する。
- TCBS寒天培地(Thiosulfate-Citrate-Bile Salts-Sucrose Agar)は、主にVibrio属(ビブリオ属)細菌の分離に用いられる選択分離培地です。
- Bacteroides fragilis (バクテロイデス・フラジリス) – BBE寒天培地
- BBE寒天培地(Bacteroides Bile Esculin Agar)は、嫌気性菌であるBacteroides fragilis groupの選択分離培地です。
この培地にはエスクリンが含まれており、B. fragilisがエスクリンを加水分解して培地を黒く変色させる特徴を利用しています。
- BBE寒天培地(Bacteroides Bile Esculin Agar)は、嫌気性菌であるBacteroides fragilis groupの選択分離培地です。
- Campylobacter jejuni (カンピロバクター・ジェジュニ) – NAC寒天培地
- NAC寒天培地(Nalidixic acid-Amphotericin B-Cephalothin Agar)は、緑膿菌(Pseudomonas aeruginosa)の選択培地です。
カンピロバクターはスキロー寒天培地やバツラー寒天培地が用いられます。
- NAC寒天培地(Nalidixic acid-Amphotericin B-Cephalothin Agar)は、緑膿菌(Pseudomonas aeruginosa)の選択培地です。
- Clostridioides difficile (クロストリディオイデス・ディフィシル) – CCFA培地
- CCFA培地(Cycloserine-Cefoxitin Fructose Agar)は、Clostridioides difficileの選択分離培地として広く用いられます。
フルクトースの分解と独特なコロニー形態が特徴です。
- CCFA培地(Cycloserine-Cefoxitin Fructose Agar)は、Clostridioides difficileの選択分離培地として広く用いられます。
Neisseria meningitidis (ナイセリア・メニンギティディス) – PPLO寒天培地
- PPLO寒天培地(Pleuropneumonia-like Organism Agar)は、主にマイコプラズマ属の培養に用いられる培地です。
Neisseria meningitidis(髄膜炎菌)は、チョコレート寒天培地やThayer-Martin寒天培地などの富栄養培地で培養されます。
上記より、正しい組み合わせはBacteroides fragilis – BBE寒天培地とClostridioides difficile – CCFA培地です。
答え2と4
73 抗真菌薬はどれか。
- アシクロビル
- イソニアジド
- フルコナゾール
- ミノサイクリン
- リファンピシン
選択肢の薬剤について簡単に説明します。
- アシクロビル (Acyclovir)
- 抗ウイルス薬です。ヘルペスウイルス感染症(帯状疱疹、単純ヘルペスなど)の治療に用いられます。
- イソニアジド (Isoniazid)
- 抗結核薬です。結核菌の治療に用いられる主要な薬剤の一つです。
- フルコナゾール (Fluconazole)
- 抗真菌薬です。アゾール系の薬剤で、カンジダ症、クリプトコッカス症など、広範囲の真菌感染症の治療に用いられます。
- ミノサイクリン (Minocycline)
- テトラサイクリン系の抗生物質です。細菌感染症の治療に用いられ、ニキビ治療などにも使われます。
- リファンピシン (Rifampicin)
- 抗結核薬であり、一部の細菌感染症にも用いられる抗菌薬です。
抗真菌薬はフルコナゾールです。
★抗真菌薬
- フルコナゾール
- アムホテリシンB
- イトラコナゾール
- ミカファンギン
などがある。
答え:3
74 血液培養にて検出された菌のGram染色所見(別冊No. 15A)とヒツジ血液寒天培地の集落(別冊No. 15B)を別に示す。本菌はCAMPテストおよび馬尿酸塩加水分解試験が陽性であった。考えられるのはどれか。


- Bacillus cereus
- Clostridium perfringens
- Enterococcus faecalis
- Listeria monocytogenes
- Streptococcus agalactiae
設問と写真AとBから所見を見ていきましょう。
- グラム陽性桿菌(紫色の杆状)
- ヒツジ血液寒天培地にてスムース状の弱いβ溶血あり
- CAMPテスト(+)
- 馬尿酸塩加水分解試験(+)
以上より、Listeria monocytogenes が鑑別に上がる。
他の選択肢を見ていくと
- Bacillus cereus
グラム陽性の大桿菌、ヒツジ血液寒天培地で強いβ溶血、レシチナーゼ(+) - Clostridium perfringens
偏性嫌気性菌で5%CO2培養では発育不可。 - Enterococcus faecalis
グラム陽性球菌でヒツジ血液寒天培地にて溶血を示さない。 - Streptococcus agalactiae
グラム陽性球菌、ヒツジ血液寒天培地で溶血、CAMPテスト(+)、馬尿酸塩加水分解試験(+)
答え:4
75 感染症と原因微生物の組合せで正しいのはどれか。
- 類鼻疽(るいびそ) Burkholderia pseudomallei
- オウム病 Bacillus anthracis
- 放線菌症 Bartonella henselae
- ライム病 Chlamydia psittaci
- ネコひっかき病 Rickettsia japonica
感染症と原因微生物の組み合わせについて、正しいものを選びます。
- 類鼻疽 (Melioidosis) – Burkholderia pseudomallei(ブルクホルデリア・シュードマレイ)
- 類鼻疽は、土壌や水中に生息するグラム陰性桿菌であるBurkholderia pseudomalleiによって引き起こされる感染症です。熱帯・亜熱帯地域、特に東南アジアやオーストラリア北部で多く見られます。
- オウム病 (Psittacosis) – Bacillus anthracis(バチルス・アントラシス)
- オウム病は、鳥類を宿主とする細菌であるChlamydia psittaciによって引き起こされる人獣共通感染症です。Bacillus anthracis(炭疽菌)は炭疽の原因菌です。
- 放線菌症 (Actinomycosis) – Bartonella henselae(バルトネラ・ヘンゼレ)
- 放線菌症は、主に口腔内の常在菌であるActinomyces属(例: Actinomyces israelii)などの嫌気性グラム陽性桿菌によって引き起こされる慢性的な化膿性炎症疾患です。Bartonella henselaeはネコひっかき病の原因菌です。
- ライム病 (Lyme disease) – Chlamydia psittaci(クラミジア・シッタシ)
- ライム病は、マダニによって媒介されるスピロヘータであるBorrelia burgdorferiによって引き起こされる感染症です。Chlamydia psittaciはオウム病の原因菌です。
- ネコひっかき病 (Cat scratch disease) – Rickettsia japonica(リケッチア・ジャポニカ)
- ネコひっかき病は、ネコにひっかかれたり噛まれたりすることで感染するBartonella henselaeによって引き起こされる感染症です。Rickettsia japonicaは日本紅斑熱の原因菌です。
感染症と原因微生物の組合せで正しいのは類鼻疽 – Burkholderia pseudomalleiです。
答え:1
76 治療薬物モニタリング〈TDM〉が必要なのはどれか。
- アンピシリン
- エリスロマイシン
- セファゾリン
- バンコマイシン
- メロペネム
治療薬物モニタリング(TDM: Therapeutic Drug Monitoring)とは、血中薬物濃度を測定し、個々の患者に合わせて薬物の投与量や投与方法を最適化することで、有効性と安全性を高める手法です。TDMが必要とされる薬物は、主に以下の特徴を持つものです。
- 有効血中濃度範囲が狭い(治療域が狭い)。
- 個人差が大きい。
- 治療効果や副作用が血中濃度と相関する。
- 重篤な副作用がある。
★TDM(治療薬物モニタリング)が必要な主な薬剤
| 薬剤の分類 | 主な薬剤名 |
|---|---|
| 強心薬 | ジゴキシン |
| 抗不整脈薬 | ジソピラミド、プロカインアミド、メキシレチン、リドカイン、フレカイニドなど |
| 抗てんかん薬 | フェニトイン、フェノバルビタール、カルバマゼピン、バルプロ酸、エトスクシミドなど |
| アミノ配糖体抗生物質 | ゲンタマイシン、アミカシン、トブラマイシンなど |
| グリコペプチド系抗生物質 | バンコマイシン、テイコプラニン |
| 免疫抑制剤 | シクロスポリン、タクロリムス、ミコフェノール酸、エベロリムス |
| 気管支拡張薬 | テオフィリン |
| 精神科治療薬 | リチウム(炭酸リチウム) |
| トリアゾール系抗真菌剤 | ボリコナゾール |
| 抗悪性腫瘍薬 | メトトレキサート |
上表を参考にしつつ、各選択肢の薬物について見ていきましょう。
- アンピシリン (Ampicillin)
- ペニシリン系抗生物質です。比較的安全域が広く、血中濃度と効果・副作用の相関が非常に強いわけではないため、通常TDMは行いません。
- エリスロマイシン (Erythromycin)
- マクロライド系抗生物質です。比較的安全域が広く、経口投与時の吸収に個人差はありますが、TDMが必須とされる薬物ではありません。
- セファゾリン (Cefazolin)
- セフェム系抗生物質です。安全域が広く、通常TDMは行いません。
- バンコマイシン (Vancomycin)
- グリコペプチド系抗生物質です。腎排泄型であり、腎機能によって血中濃度が大きく変動します。有効血中濃度範囲が狭く、高濃度になると腎毒性や聴器毒性(耳鳴り、難聴)といった重篤な副作用のリスクが高まります。そのため、血中濃度を適切に管理するためにTDMが必須とされています。
- メロペネム (Meropenem)
- カルバペネム系抗生物質です。腎排泄型ですが、比較的安全域が広く、重篤な副作用が血中濃度と強く相関するわけではないため、通常TDMは行いません。
したがって、TDMが必要なのはバンコマイシンです。
答え:4
77 インターフェロンγ遊離試験〈IGRA〉が診断に有用なのはどれか。
- 結 核
- B型肝炎
- ネコひっかき病
- 成人T細胞白血病
- 後天性免疫不全症候群
- IGRAとは、Interferon-Gamma Release Assay(インターフェロン-γ遊離試験)の略で、主に結核菌への感染の有無を調べる血液検査です。
- 結核菌に特異的な抗原(BCGワクチン株には存在しない「ESAT-6」や「CFP-10」などのタンパク質)を利用して検査を行います。
- 日本で主に使われているIGRAには、以下の2種類があります。
- クォンティフェロンTBゴールド(QFT):結核菌特異抗原で刺激した血液中のインターフェロン-γの総量を測定します。
- T-スポット.TB(T-SPOT):インターフェロン-γを産生した細胞(スポット)の数を測定します。
- クォンティフェロンTBゴールド(QFT):結核菌特異抗原で刺激した血液中のインターフェロン-γの総量を測定します。
各選択肢について見ていきましょう。
- 結 核
IGRAは、結核菌(Mycobacterium tuberculosis)に感染しているかどうかを調べるために開発された検査です。結核菌特異的な抗原(ESAT-6やCFP-10など)をT細胞に提示することで、T細胞が産生するインターフェロンγの量を測定します。活動性結核だけでなく、潜在性結核感染症の診断にも有用です。
- B型肝炎
B型肝炎はB型肝炎ウイルス(HBV)による感染症であり、診断にはHBV抗原や抗体、HBV-DNAの測定などが行われます。
- ネコひっかき病
ネコひっかき病は細菌であるBartonella henselae(バルトネラ・ヘンゼレ)によって引き起こされる感染症であり、診断には血清学的検査(抗体検査)やPCR法などが行われます。
- 成人T細胞白血病
成人T細胞白血病(ATL)は、ヒトT細胞白血病ウイルス1型(HTLV-1)によって引き起こされる悪性腫瘍です。診断にはHTLV-1抗体検査やウイルスDNAの検出、リンパ球の形態学的検査などが行われます。
- 後天性免疫不全症候群 (AIDS)
後天性免疫不全症候群(エイズ)は、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)によって引き起こされる疾患です。診断にはHIV抗体検査やHIV-RNAの測定などが行われます。I
したがって、インターフェロンγ遊離試験(IGRA)が診断に有用なのは結核です。
答え:1
78 偏性細胞内寄生性を有するのはどれか。
- Bacteroides fragilis
- Cryptococcus neoformans
- Mycobacterium tuberculosis
- Mycoplasma pneumoniae
- Orientia tsutsugamushi
微生物には、細胞内でしか増殖できない「偏性細胞内寄生性」のものと、細胞外でも増殖できるものがあります。
★偏性細胞内寄生性微生物の代表例
| 分類 | 主な微生物(属・種) | 特徴・補足 |
|---|---|---|
| ウイルス |
|
自己増殖せず、宿主細胞の仕組みを利用して増殖 |
| クラミジア属 |
|
ATP産生能力が低く、宿主細胞からATP供給が必要 |
| リケッチア属 |
|
主にダニ・シラミなど節足動物が媒介、血管内皮細胞に親和性 |
| バルトネラ属 |
|
主に血管内皮細胞や赤血球に寄生 |
参考:通性細胞内寄生性微生物(混同しやすいので注意)
| 分類 | 主な微生物(属・種) | 特徴・補足 |
|---|---|---|
| 細菌 |
|
細胞内でも増殖できるが、人工培地でも増殖可能 |
それぞれの選択肢について、その増殖様式を確認しましょう。
- Bacteroides fragilis (バクテロイデス・フラジリス)
消化管の常在菌である嫌気性菌です。宿主細胞の外でも増殖できる非細胞内寄生性の細菌です。
- Cryptococcus neoformans (クリプトコッカス・ネオフォルマンス)
酵母型真菌の一種です。通常は細胞外で増殖しますが、一部、宿主細胞(特にマクロファージ)内での生存能力を持つことも知られています。しかし、偏性細胞内寄生性ではありません。
- Mycobacterium tuberculosis (マイコバクテリウム・ツベルクローシス)
結核菌です。これはマクロファージなどの細胞内で増殖することができる通性細胞内寄生性の細菌です。偏性ではありません。
- Mycoplasma pneumoniae (マイコプラズマ・ニューモニエ)
細菌の一種で、細胞壁を持ちません。気道上皮細胞に吸着して増殖しますが、偏性細胞内寄生性ではありません。細胞外でも培養可能です。
- Orientia tsutsugamushi (オリエンティア・ツツガムシ)
ツツガムシ病(つつが虫病)の原因菌で、リケッチアの一種です。リケッチアは、ATPなどのエネルギー源を宿主細胞に依存しており、人工培地では培養できない偏性細胞内寄生性の細菌です。
したがって、偏性細胞内寄生性を有するのはOrientia tsutsugamushiです。
答え:5
第71回(AM)臨床免疫学(79〜89)
▼ クリックすると詳細が開きます
79 抗体で正しいのはどれか。
- IgAは分子量が最も大きい。
- IgGには2つのサブクラスがある。
- 補体の結合部位はFab部分にある。
- H鎖には5種類のアイソタイプがある。
- 2本のH鎖と1本のL鎖で形成される。
★抗体の特徴
抗体(免疫グロブリン:Ig)は、B細胞が産生するY字型の糖タンパク質で、体液性免疫において特異的な抗原と結合し、様々なエフェクター機能を発揮する分子です。
- 構造: 基本単位は2本の重鎖(H鎖)と2本の軽鎖(L鎖)がジスルフィド結合で連結したY字型分子。
- 可変部(Fab部分): Y字の先端部分。抗原と特異的に結合する部位。
- 定常部(Fc部分): Y字の脚の部分。補体結合、Fc受容体結合などのエフェクター機能に関与。
- クラス(アイソタイプ): H鎖の定常部の構造に基づき、IgG, IgA, IgM, IgD, IgEの5種類に分類される(H鎖にはμ, γ, α, δ, εの5種のアイソタイプがあるため)。
- IgGには4つのサブクラス(IgG1, IgG2, IgG3, IgG4)がある。
- 主な機能:
- 中和: 毒素やウイルスの感染能力を阻害。
- オプソニン化: 食細胞による貪食を促進。
- 補体活性化: 補体系を活性化し、病原体の溶解や炎症反応を誘導。
- ADCC: 抗体依存性細胞傷害。
- その他: 粘膜防御(IgA)、アレルギー反応(IgE)、胎盤通過(IgG)、初期免疫応答(IgM)など。
上記を参考にしつつ各選択肢の正誤を判断していきましょう。
- IgAは分子量が最も大きい。
抗体の中で分子量が最も大きいのはIgMです。IgMは通常ペンタマー(5量体)として存在し、その分子量は約900,000です。IgAは主にダイマー(2量体)またはモノマー(単量体)として存在し、分子量はモノマーで約160,000です。
- IgGには2つのサブクラスがある。
IgGには、IgG1、IgG2、IgG3、IgG4の4つのサブクラスが存在します。
- 補体の結合部位はFab部分にある。
C1qが結合するのは、抗体のFc部分です。Fab部分は抗原と結合する部位です。
- H鎖には5種類のアイソタイプがある。
H鎖(重鎖)には、μ(ミュー)、γ(ガンマ)、α(アルファ)、δ(デルタ)、ε(イプシロン)の5種類のアイソタイプがあります。
これらがそれぞれIgM、IgG、IgA、IgD、IgEといった異なるクラスの抗体を構成します。
- 2本のH鎖と1本のL鎖で形成される。
免疫グロブリンの基本的な構造は、2本のH鎖(重鎖)と2本のL鎖(軽鎖)がジスルフィド結合でつながったY字型をしています。
したがって、抗体で正しいのは「H鎖には5種類のアイソタイプがある」です。
答え;4
80 免疫比濁法で誤っているのはどれか。
- 透過光の強度を測定する。
- Lambert-Beerの法則に従う。
- サイトカインの測定に適している。
- 地帯現象による偽低値が見られる。
- 化学発光分析法より測定感度が低い。
★免疫比濁法(Turbidimetry Immunoassay)
液中の抗原と抗体が結合して免疫複合体を形成し、その凝集塊による濁度(光の透過率の変化)を測定することで、検体中の特定成分(抗原または抗体)を定量する方法。
★原理
- 抗原抗体反応: 検体中の測定対象物質(抗原)と、それに対する特異的な抗体(またはその逆)を反応させる。
- 免疫複合体形成: 抗原と抗体が結合し、不溶性の免疫複合体(凝集塊)を形成する。
- 光の減衰(濁度の測定): この凝集塊が光を散乱・吸収するため、光の透過率が減少する(濁度が上昇する)。
- 定量: 自動分析装置で光の減衰度(吸光度)を測定し、既知濃度の標準液(検量線)と比較することで、検体中の測定対象物質の濃度を算出する。
★特徴
- 高濃度プロゾーン現象(抗原過剰現象): 検体中の抗原が非常に高濃度の場合、抗体との結合部位が飽和し、凝集塊が小さくなるため、見かけ上の濁度が低く測定され、実際よりも低い値が出てしまうことがある。
この現象を回避するため、検体希釈や再測定が必要となる場合がある。 - 感度は、ELISAなどの酵素免疫測定法に比べると劣ることがある。
上記を参考にしつつ、選択肢を見ていきます。
- 透過光の強度を測定する。
免疫比濁法は、検体中の抗原と抗体が反応して不溶性の免疫複合体を形成し、溶液が濁る現象を利用します。この濁りの程度は、光の透過を妨げることで測定されます。つまり、透過してきた光の強度(吸光度)を測定することで、濁りの程度、目的物質の濃度を算出します。
- Lambert-Beerの法則に従う。
ランベルト・ベールの法則は、物質が光を吸収する際の、光の透過距離と物質濃度との関係を示す法則です。免疫比濁法は、濁りによる光の散乱・吸収を利用するため、この法則に基づいて吸光度と濃度の関係が成り立ちます。
- サイトカインの測定に適している。
サイトカインは通常、非常に微量(ピコグラム/mLレベル)で生体内に存在するため、免疫比濁法のような感度が比較的低い方法では検出が困難です。サイトカインの測定には、化学発光免疫測定法 (CLIA) やELISA(酵素免疫測定法)など、より高感度な免疫測定法が適しています。
- 地帯現象による偽低値が見られる。
地帯現象(プロゾーン現象、フック現象とも呼ばれる)は、抗原または抗体が過剰に存在する場合に、最適な免疫複合体が形成されず、濁度が予想より低く測定されてしまう現象です。これにより、実際の濃度よりも低い値(偽低値)として報告される可能性があります。これは免疫比濁法だけでなく、免疫測定法全般で見られる注意点です。
- 化学発光分析法より測定感度が低い。
免疫比濁法は、光の透過(吸光度)を測定するため、原理的に光シグナルを増幅する化学発光分析法や酵素免疫測定法に比べて感度が劣ります。化学発光分析法は非常に微量の物質でも検出できる高感度な方法です。
以上より、免疫比濁法について誤っている記述は、「サイトカインの測定に適している」です。
答え:3
81 EBウイルスで正しいのはどれか。2つ選べ。
- ヘルペスウイルス科に属する。
- ウイルスはB細胞に潜伏する。
- EBNA抗体は初感染で陽性となる。
- 再活性化により伝染性単核球症を発症する。
- 抗体検査はラテックス凝集反応が用いられる。
EBウイルスについて、選択肢を含めながら見ていきます。
- ヘルペスウイルス科に属する。
EBウイルスは、DNAウイルスであり、ヘルペスウイルス科ガンマヘルペスウイルス亜科に分類されます。ヒトヘルペスウイルス4型(HHV-4)とも呼ばれます。
- ウイルスはB細胞に潜伏する。
EBウイルスは主にCD21分子を介してBリンパ球に感染し、その中で潜伏感染を確立します。これが、EBウイルスが関連するリンパ増殖性疾患の病態に関与します。
- EBNA抗体は初感染で陽性となる。
EBNA (EBウイルス核抗原:Epstein-Barr Nuclear Antigen) 抗体は、EBV感染後に比較的遅れて(回復期から)出現し、生涯にわたって持続することが多い抗体です。
初感染の急性期には通常陰性であり、VCA (Viral Capsid Antigen) 抗体やEA-D (Early Antigen-diffuse) 抗体が早期に陽性となります。よって誤りです。
- 再活性化により伝染性単核球症を発症する。
伝染性単核球症は、EBVの初感染時に発症する代表的な疾患です。再活性化は、免疫が低下した状態などで起こることがありますが、通常、伝染性単核球症のような症状は引き起こしません。再活性化が問題となるのは、移植後のリンパ増殖性疾患などです。よって、この記述は誤りです。
- 抗体検査はラテックス凝集反応が用いられる。
EBウイルスの抗体検査には、通常、ELISA法などが用いられます。
したがって、EBウイルスで正しいのは「ヘルペスウイルス科に属する」と「ウイルスはB細胞に潜伏する」です。
答え:1と2
82 免疫電気泳動法で正しいのはどれか。
- 電気浸透現象の影響を受けない。
- 分子量が大きいほど拡散速度が速い。
- 検査の所要時間はおよそ2時間である。
- トランスフェリンはβ領域に泳動される。
- 免疫固定法よりM蛋白の検出感度が高い。
★免疫電気泳動法(Immunoelectrophoresis, IEP)の特徴(簡潔まとめ)
免疫電気泳動法は、血清や尿中のタンパク質を電気泳動で分離した後、特定の抗血清を用いて免疫沈降線として可視化する検査法です。
原理
- 電気泳動: 検体中のタンパク質を寒天ゲルなどの支持体上で電荷と分子量に基づいて分離(アルブミン、α1, α2, β, γグロブリンなど)。
- 免疫沈降反応: 電気泳動後、ゲル上に抗血清(特定のタンパク質に対する抗体)を添加すると、対応する抗原タンパク質と結合して弓状の免疫沈降線を形成する。
- 可視化: 染色することで沈降線を可視化し、タンパク質の量や異常を評価する。
目的
- M蛋白(モノクローナルガンマパチー)のスクリーニング: 多発性骨髄腫などの形質細胞疾患で産生される異常な免疫グロブリン(M蛋白)の有無や種類(IgG, IgA, IgMなど)を定性的に確認する。
- 免疫グロブリン欠損症: 特定の免疫グロブリンの欠損を確認する。
- その他の異常タンパク質の検出: アルブミン、トランスフェリンなどの異常を確認する。
特徴
- 定性・半定量的な検査: タンパク質の存在や移動度、沈降線の形態から異常を判断する。
- 時間と手間: 電気泳動と免疫沈降に時間がかかり、手技も比較的複雑。
- 電気浸透現象の影響: 寒天ゲルなどを用いるため、電気浸透現象の影響を受ける。
- 免疫固定法との比較: M蛋白の検出においては、より感度の高い免疫固定法(IFE)が現在では主流となっている。
免疫電気泳動法は、免疫固定法よりも感度が低いが、全体的なタンパク質パターンを把握しやすいという側面もある。
免疫電気泳動法は、異常な免疫グロブリンのスクリーニングやクラスの特定に用いられる重要な検査法ですが、M蛋白の精密な検出には免疫固定法が優れています。
上記を参考にしつつ、免疫電気泳動法に関する各選択肢を見ていきましょう。
- 電気浸透現象の影響を受けない。
誤りです。 免疫電気泳動法はアガロースゲルなどの担体を使用するため、電気浸透現象の影響を受けます。電気浸透現象は、ゲル中の荷電基によって溶液の移動が生じる現象で、特にガンマグロブリンの移動度などに影響を与えます。
- 分子量が大きいほど拡散速度が速い。
誤りです。 拡散速度は分子量に反比例します。分子量が小さいほど、ゲル中での拡散速度は速くなります。分子量が大きいほど拡散は遅くなります。
- 検査の所要時間はおよそ2時間である。
誤りです。 免疫電気泳動法は、電気泳動の後に抗血清を添加し、免疫複合体の沈降線が形成されるまで長時間(通常、一晩かけて18〜24時間程度)インキュベートする必要があります。そのため、検査の全所要時間は2時間よりもはるかに長いです。
- トランスフェリンはβ領域に泳動される。
正しいです。 血清蛋白電気泳動では、蛋白はアルブミン、α1、α2、β、γの各領域に分離されます。トランスフェリンは主にβグロブリン領域に泳動されます。
- 免疫固定法よりM蛋白の検出感度が高い。
誤りです。 免疫電気泳動法は免疫固定法(IFE)と比較して、M蛋白(モノクローナル蛋白)の検出感度が低いです。
免疫固定法は、電気泳動後に特定の抗血清を直接ゲル上に乗せて固定するため、よりシャープなバンドが得られ、微量のM蛋白も検出可能です。現在では、M蛋白の検出には感度の高い免疫固定法が広く用いられています。
したがって、免疫電気泳動法で正しい記述は「トランスフェリンはβ領域に泳動される」です。
答え:4
83 ヒトT細胞白血病ウイルス1型(HTLV-1)感染症の確認検査はどれか。
- PA法
- EIA法
- HPLC法
- MAST法
- LIA(line immunoassay)法
★ヒトT細胞白血病ウイルス1型(HTLV-1)感染症の確認検査
ヒトT細胞白血病ウイルス1型(HTLV-1)感染症の検査は、まずスクリーニング検査(一次検査)を行い、陽性または判定保留となった場合に、より特異性の高い確認検査(二次検査)を実施します。
★具体的な確認検査
- LIA法(ラインブロット法)
→現在、日本で主に用いられている確認検査法です。(WB法より判定保留が少ない) - HTLV-1の複数のウイルス抗原(Env, Gagなど)を膜上に固定し、検体中の抗体がこれらと結合するかどうかを検出します。
- WB法(ウエスタンブロット法)
→以前は広く用いられていましたが、現在はLIA法が主流です。
ウイルスタンパク質を電気泳動で分離し、膜に転写した後、検体中の抗体と反応させて検出します。LIA法と同様に抗体パターンで判定します。 - 核酸検出法(PCR法)
→LIA法やWB法で判定保留(indeterminate)となった場合、または感染の有無をより確実に診断する必要がある場合に実施されます。
上記を参考に選択肢を見ていきましょう。
- PA法 (Particle Agglutination assay)
粒子凝集法。HTLV-1抗体のスクリーニング検査として用いられます。感度は高いですが、特異性がやや劣るため、確認検査には向きません。
- EIA法 (Enzyme Immunoassay)
酵素免疫測定法。HTLV-1抗体のスクリーニング検査として広く用いられます。PA法と同様に、感度は高いですが、確認検査としては不十分な場合があります。
- HPLC法 (High Performance Liquid Chromatography)
高速液体クロマトグラフィー。これは主に物質の分離・定量に用いられる分析法であり、HTLV-1感染症の診断に直接用いられる検査ではありません。
- MAST法 (Multiple Allergen Simultaneous Test)
多項目同時アレルゲン特異的IgE抗体測定法。アレルギー検査に用いられる方法であり、HTLV-1感染症の診断とは関係ありません。
- LIA (line immunoassay) 法
ラインイムノアッセイ法。HTLV-1感染症の確認検査として広く用いられます。複数のHTLV-1特異的な抗原(p19、p24、gp21、envなど)を膜上にライン状に固定し、患者血清中の抗体がどの抗原に反応するかを検出することで、より詳細かつ特異的な診断が可能です。
したがって、HTLV-1感染症の確認検査はLIA法です。
答え:5
84 Lewis血液型がLe(a-b-)の場合、産生されないのはどれか。
- AFP
- CEA
- PSA
- CA19-9
- ProGRP
Lewis血液型は、フコース転移酵素の遺伝子(FUT3遺伝子、Lewis遺伝子)によって制御されるABH式血液型物質の修飾に関わるものです。
このLewis遺伝子の働きにより、ルイス抗原(Le^aやLe^b)が体液や赤血球上に発現します。
- Le(a+b-): Lewis遺伝子(FUT3)が活性で、かつ分泌型遺伝子(FUT2)が不活性な場合。Le^a抗原が発現します。
- Le(a-b+): Lewis遺伝子(FUT3)が活性で、かつ分泌型遺伝子(FUT2)も活性な場合。Le^b抗原が発現します。
- Le(a-b-): Lewis遺伝子(FUT3)が不活性(ルイス式血液型が劣性ホモ接合型)の場合。Le^a抗原もLe^b抗原も産生されません。
- CA19-9は、消化器系がんの腫瘍マーカーとして広く用いられる糖鎖抗原(シアリルルイスA抗原)です。このCA19-9(シアリルルイスA)は、ルイス抗原(Le^a)とフコース転移酵素の作用によって生合成されます。
- したがって、Lewis血液型がLe(a-b-)、つまりルイス遺伝子(FUT3)が不活性でLe^a抗原が産生されない個体では、CA19-9も産生されません。
各選択肢とCA19-9の関係を見てみましょう。
- AFP (α-フェトプロテイン):肝細胞がんや卵黄嚢腫瘍の腫瘍マーカー。Lewis血液型とは関係ありません。
- CEA (癌胎児性抗原):消化器系がんなどの腫瘍マーカー。Lewis血液型とは関係ありません。
- PSA (前立腺特異抗原):前立腺がんの腫瘍マーカー。Lewis血液型とは関係ありません。
- CA19-9 (シアリルルイスA抗原):膵臓がんや胆道がんなどの腫瘍マーカー。ルイス血液型がLe(a-b-)の個体では産生されません。
- ProGRP (ガストリン放出ペプチド前駆体):肺小細胞がんの腫瘍マーカー。Lewis血液型とは関係ありません。
したがって、Lewis血液型がLe(a-b-)の場合に産生されないのはCA19-9です。
内容がややこしいので、Lewis血液型がLe(a-b-)の場合はCA19-9は産生されないと覚えておきましょう。
答え:4
85 ABO血液型検査の結果(別冊No. 16)に示す。血液型はどれか。

- A型RhD陰性
- A型RhD陽性
- B型RhD陰性
- B型RhD陽性
- ABO・RhD判定保留
写真より判定していきます。
- オモテ試験(赤血球上の抗原を調べる)
抗A試薬(ー)、抗B試薬が(4+)
→B型 - ウラ試験(血清中の抗体を調べる)
A1赤血球(4+)、B赤血球(ー)
→B型 - RhD検査(赤血球上のRhD抗原を調べる)
抗D試薬(4+)、Rhコントロール(ー)
→RhD(+)
上記より、オモテ・ウラ一致でB型RhD陽性です。
答え:4
86 緊急輸血あるいは患者と同じABO血液型の赤血球液が不足した場合、患者と輸血する赤血球液のABO血液型で輸血可能な組合せはどれか。2つ選べ。
- A型の患者 B型
- B型の患者 A型
- O型の患者 AB型
- AB型の患者 B型
- 血液型不明の患者 O型
- 赤血球上の抗原と、患者の血漿中の抗体との反応を避けるという原則に基づいて考える。
- 赤血球輸血の場合、患者の血漿中にある抗体と、ドナー(輸血する血液)の赤血球表面にある抗原の反応が問題となります。
- O型赤血球は抗原を持たないため、誰にでも輸血できる「ユニバーサルドナー」とみなされます(もちろん例外あり)。
- AB型患者は血漿中に抗A抗体も抗B抗体も持たないため、どの型の赤血球でも受け入れやすい「ユニバーサルレシピエント」とみなされます。
各選択肢を見ていきましょう。
- A型の患者 – B型
A型の患者は血漿中に抗B抗体を持っています。B型の赤血球は表面にB抗原を持っています。患者の抗B抗体とB型赤血球のB抗原が反応し、溶血を引き起こすため、輸血不可です。
- B型の患者 – A型
B型の患者は血漿中に抗A抗体を持っています。A型の赤血球は表面にA抗原を持っています。患者の抗A抗体とA型赤血球のA抗原が反応し、溶血を引き起こすため、輸血不可です。
- O型の患者 – AB型
O型の患者は血漿中に抗A抗体と抗B抗体の両方を持っています。AB型の赤血球は表面にA抗原とB抗原の両方を持っています。患者の抗A抗体とA抗原、抗B抗体とB抗原が反応し、溶血を引き起こすため、輸血不可です。
- AB型の患者 – B型
AB型の患者は血漿中に抗A抗体も抗B抗体も持っていません。B型の赤血球は表面にB抗原を持っています。患者の血漿中にはB抗原に対する抗体がないため、B型赤血球を輸血しても原則として抗原抗体反応は起こりません。
よって、この組み合わせは輸血可能です。
- 血液型不明の患者 – O型
血液型不明の場合、最も安全な赤血球液は、すべての患者(A, B, AB, O型)の血漿中抗体と反応しない赤血球です。O型の赤血球は表面にA抗原もB抗原も持たないため、どのような血液型の患者にも(例外を除いて)凝集反応を起こしません。このため、「ユニバーサルドナー」として緊急時に選択されます。
よって、この組み合わせは輸血可能です。
したがって、輸血可能な組み合わせ「AB型の患者 – B型」 と「血液型不明の患者 – O型」 です。
答え:4と5
87 末梢血幹細胞採取で臨床検査技師が行うことができないのはどれか。
- 静脈路確保
- 成分採血装置の操作
- 採取中の静注薬投与
- 採取後の抜針
- 採取細胞の保存処理
末梢血幹細胞採取において、臨床検査技師が行うことができないのは、医師または看護師の業務とされる「医行為」です。
選択肢を見ていきましょう。
- 静脈路確保: 静脈カテーテルの挿入や維持など、採血のための穿刺以上の広範な血管確保は医行為であり、技師はできません。(ややこしいので注意)
- 成分採血装置の操作: 医療機器の操作は医師の指示のもと技師も行えます。
- 採取中の静注薬投与: 薬剤の投与は医行為であり、技師はできません。
- 採取後の抜針: 採血行為の終了後の抜針はできる。技師は採血業務も担当します。
- 採取細胞の保存処理: 検体管理の一部であり、技師の業務範囲です。
上記のうち、詳しく考えていくと「技師が行うことができない」ものは複数あるように思えますが、特に「静脈路確保」と「採取中の静注薬投与」は明確な医行為として技師の業務範囲外です。
しかしそこまで深く考えずに、ここでは「採取中の静注薬投与」が最も適切な答えとなります。
答え:3
88 新鮮凍結血漿投与の目的で正しいのはどれか。
- 貧血の改善
- 血小板の補充
- 凝固因子の補充
- アルブミンの補充
- 血漿浸透圧の維持
新鮮凍結血漿(FFP: Fresh Frozen Plasma)の投与目的は、その成分に由来します。FFPは、血液から赤血球、白血球、血小板を除いた血漿成分を、採血後速やかに凍結保存したものです。これにより、不安定な凝固因子などの成分が比較的良好に保持されます。(凝固因子の補充)
各選択肢について見ていきましょう。
- 貧血の改善
貧血は赤血球の不足によって起こります。FFPは血漿であり、赤血球は含まれていません。貧血の改善には、赤血球濃厚液などが用いられます。
よって、この記述は誤りです。
- 血小板の補充
血小板はFFPには含まれていません(遠心分離で除去されるため)。血小板の補充には、血小板濃厚液などが用いられます。
よって、この記述は誤りです。
- 凝固因子の補充
FFPは、すべての凝固因子(特に不安定な第V因子や第VIII因子など)を良好な活性で含んでいます。肝不全、DIC(播種性血管内凝固症候群)、ビタミンK欠乏、ワルファリン過量投与などによる凝固因子欠乏症や、多量出血時の凝固能低下に対する補充療法として最も重要な目的となります。
よって、この記述は正しいです。
- アルブミンの補充
FFPにはアルブミンが含まれていますが、アルブミン濃度が低い状態(低アルブミン血症)を改善することが主な目的ではありません。低アルブミン血症に対する治療には、アルブミン製剤が用いられます。FFPはアルブミン補充目的で大量に投与すると循環血液量過多になるリスクが高く、また特定の凝固因子欠乏がない限り推奨されません。
よって、この記述は誤りです。
- 血漿浸透圧の維持
FFPのタンパク質成分は血漿浸透圧の維持に寄与しますが、FFP投与の第一の目的ではありません。血漿浸透圧の維持が主な目的である場合は、アルブミン製剤や晶質液などが優先的に選択されます。FFPは凝固因子の補充という特定の目的のために使用されます。
よって、この記述は誤りです。
したがって、新鮮凍結血漿投与の目的で正しいのは凝固因子の補充です。
答え:3
89 能動免疫はどれか。2つ選べ。
- 感染による抗体獲得
- 生ワクチン接種による抗体獲得
- 免疫グロブリン製剤による抗体獲得
- 胎盤を介したIgG抗体の胎児への移行
- 母乳に含まれるIgA抗体の児への移行
能動免疫と受動免疫は、免疫の獲得経路による分類です。
- 能動免疫(Active Immunity)
生体が抗原に接触し、自らの免疫系が活性化されて抗体や免疫細胞を産生することで獲得される免疫です。長期的な免疫が期待できます。例:自然感染、ワクチン接種 - 受動免疫(Passive Immunity)
既に作られた抗体や免疫細胞を外部から与えられることで獲得される免疫です。即効性がありますが、効果は一時的で、持続期間は短いです。
例:免疫グロブリン製剤の投与、母体から胎児・乳児への抗体移行
各選択肢を見ていきましょう。
- 感染による抗体獲得
病原体に感染することで、体が自ら抗体を産生します。これは能動免疫です。
- 生ワクチン接種による抗体獲得
弱毒化した病原体(抗原)を接種することで、体が病原体に感染したかのように反応し、自ら抗体を産生します。これは能動免疫です。
- 免疫グロブリン製剤による抗体獲得
他者(または動物)が産生した抗体を含む製剤を投与することで免疫を獲得します。これは受動免疫です。
- 胎盤を介したIgG抗体の胎児への移行
母親が持つ抗体(IgG)が胎盤を通過して胎児に移行し、胎児が免疫を獲得します。これは受動免疫です(母体由来抗体)。
- 母乳に含まれるIgA抗体の児への移行
母乳に含まれる抗体(IgA)が乳児の消化管に移行し、感染防御に役立ちます。これも受動免疫です。
したがって、能動免疫は「感染による抗体獲得」と「生ワクチン接種による抗体獲得」です。
答え:1と2
第71回(AM)公衆衛生学(90〜94)
▼ クリックすると詳細が開きます
90 以下は日本国憲法第25条の条文である。
「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び ( )の向上及び増進に努めなければならない。」
( )に入るのはどれか。
- 健康力
- 公衆衛生
- 国民衛生
- 公共の福祉
- 社会経済状況
日本国憲法第25条「生存権」の正確な条文
「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」
もう答えは書かれていますが、各選択肢を見ていきます。
- 健康力: 憲法条文の表現ではありません。
- 公衆衛生: 憲法第25条後段に明記されている語句です。
- 国民衛生: 憲法条文の表現ではありません。
- 公共の福祉: 憲法第12条や第22条などで用いられる重要な概念ですが、第25条の空欄には入りません。
- 社会経済状況: 憲法条文の表現ではありません。
したがって、空欄に入るのは公衆衛生です。
答え:2
91 環境基本法に基づいて環境基準が設定されているのはどれか。
- 悪 臭
- 振 動
- 酸性雨
- 地盤沈下
- 水質汚濁
環境基本法は、日本の環境保全に関する基本的な枠組みを定めた法律です。
この法律に基づいて、様々な環境分野において環境基準が設定されています。
環境基準は、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として定められています。
各選択肢について見ていきましょう。
- 悪 臭
悪臭は環境基本法に基づく環境基準の対象ではありません。悪臭については、悪臭防止法に基づいて、特定悪臭物質の規制基準などが定められています。
- 振 動
振動は環境基本法に基づく環境基準の対象ではありません。振動については、振動規制法に基づいて、規制基準や要請限度などが定められています。
- 酸性雨
酸性雨は、広域的な大気汚染の問題であり、環境基準として直接的に「酸性雨」の項目が設定されているわけではありません。
酸性雨の原因となる物質(硫黄酸化物、窒素酸化物など)は大気汚染物質として環境基準の対象となっています。
- 地盤沈下
地盤沈下は、地下水の過剰な汲み上げなどによって引き起こされる現象であり、環境基本法に基づく環境基準の対象ではありません。地盤沈下に関しては、工業用水法や建築物用地下水の採取の規制に関する法律などによって対策が講じられています。
- 水質汚濁
環境基本法では、人の健康の保護に関する要件や生活環境の保全に関する要件として、水質汚濁に係る環境基準が詳細に定められています。
★環境中の有害物質は、その性質から主に「健康項目」と「生活環境項目」に分類される。
健康項目(有害物質)
- カドミウム、鉛、ヒ素、六価クロム、水銀など
生活環境項目
- BOD(生物化学的酸素要求量)、COD(化学的酸素要求量)、SS(浮遊物質)、大腸菌群数など
したがって、環境基本法に基づいて環境基準が設定されているのは水質汚濁です。
答え:5
92 食中毒予防の原則である「中心温度75℃以上1分以上の加熱」が有効なのはどれか。
- フグ毒
- ボツリヌス菌
- 黄色ブドウ球菌
- サルモネラ属菌
- ツキヨタケ(毒キノコ)
食中毒予防の「中心温度75℃以上1分以上の加熱」は、主に細菌が原因となる食中毒に対して有効な方法です。
この加熱条件は、ほとんどの食中毒菌を死滅させるために設定されています。
この問題では、加熱でが無効となる選択肢を知っておかないといけないので、おさらいしておきましょう。
それでは、各選択肢を見ていきましょう。
- フグ毒
フグ毒(テトロドトキシン)は、フグの体内に蓄積される自然毒です。熱に非常に強く、通常の加熱調理では分解されません。
- ボツリヌス菌
ボツリヌス菌自体は熱に比較的強い芽胞を形成しますが、食中毒を引き起こすのは菌が産生するボツリヌス毒素です。この毒素は神経毒であり、100℃で数分間の加熱(一般的なガイドラインでは85℃で5分以上、あるいは100℃で数分とされていることが多い)によって失活します。
75℃1分という条件では不十分な可能性があります。特に芽胞はさらに高温での加熱が必要です。
- 黄色ブドウ球菌
黄色ブドウ球菌による食中毒は、菌が産生するエンテロトキシン(毒素)が原因です。
この毒素は耐熱性が高く、通常の加熱調理(75℃1分)では分解されません。菌自体は加熱で死滅しますが、すでに産生された毒素は残るため、食中毒は防げません。
- サルモネラ属菌
サルモネラ属菌は、動物の腸管などに生息する細菌で、食中毒の主要な原因の一つです。熱に弱く、中心温度75℃以上1分以上の加熱により容易に死滅します。
- ツキヨタケ(毒キノコ)
ツキヨタケは、食べると消化器症状などを引き起こす自然毒を持つキノコです。キノコの毒は熱に安定なものが多く、通常の加熱調理では分解されません。
したがって、中心温度75℃以上1分以上の加熱が有効なのは、サルモネラ属菌による食中毒です。この加熱は、菌そのものを死滅させることで食中毒を防ぎます。
答え:4
93 プライマリヘルスケアの理念が採択されたのはどれか。
- オタワ憲章
- バンコク憲章
- リスボン宣言
- ヘルシンキ宣言
- アルマ・アタ宣言
★プライマリ・ヘルス・ケア(Primary Health Care: PHC)の理念
すべての人々が、その居住地で、その生活条件に応じて、地域社会の参加のもとに、その費用をまかなえる方法で、健康を維持するために必要なケアを受けられるようにすること」
これは1978年のアルマ・アタ宣言で提唱されたもので、以下の要素が重要視されます。
- 公平性(Equity): 誰もが差別なく医療を受けられること。
- 住民参加(Community Participation): 地域住民が自らの健康問題解決に積極的に関わること。
- 学際的協力(Intersectoral Collaboration): 医療分野だけでなく、教育、農業、社会福祉など様々な分野が協力すること。
- 適切な技術(Appropriate Technology): 高度で高価な医療だけでなく、地域の実情に合った、効果的で費用対効果の高い技術を用いること。
それぞれの選択肢について見ていきましょう。
- オタワ憲章(Ottawa Charter for Health Promotion)
1986年にカナダのオタワで開催された第1回ヘルスプロモーション国際会議で採択されました。ヘルスプロモーションの概念とその戦略的アプローチを提唱し、健康の増進を社会全体で取り組むべき課題としました。プライマリ・ヘルス・ケアの理念とは直接的に異なる概念ですが、関連性はあります。
- バンコク憲章(Bangkok Charter for Health Promotion in a Globalized World)
2005年にタイのバンコクで開催された第6回ヘルスプロモーション国際会議で採択されました。グローバル化が進む世界におけるヘルスプロモーションの新たな課題と機会に対応するための枠組みを示しました。オタワ憲章の発展形です。
- リスボン宣言(Lisbon Declaration)
医師と患者の関係に関する国際的な原則を定めたもので、世界医師会(WMA)が1981年に採択しました。患者の権利などが主な内容です。
- ヘルシンキ宣言(Declaration of Helsinki)
世界医師会(WMA)が1964年に採択した、人間を対象とする医学研究の倫理的原則を定めたものです。
- アルマ・アタ宣言(Declaration of Alma-Ata)
1978年にソビエト連邦(当時)のカザフ・ソビエト社会主義共和国(現在のカザフスタン)のアルマ・アタで開催された国際プライマリ・ヘルス・ケア会議で採択されました。この宣言は、2000年までにすべての人々に健康を(Health for All by the year 2000)」をスローガンに、プライマリ・ヘルス・ケアを世界中の健康目標達成の鍵と位置づけ、その重要性と概念を明確にしました。
したがって、プライマリ・ヘルス・ケアの理念が採択されたのはアルマ・アタ宣言です。
答え:5
94 世界保健機関〈WHO〉の活動はどれか。
- 二国間協力を行う。
- 識字率を向上させる。
- 難民の帰還支援を行う。
- 国際疾病分類〈ICD〉を作成する。
- 労働者の健康保護について勧告する。
世界保健機関(WHO)は、国連の専門機関として、「すべての人々が可能な最高の健康水準に到達すること」を目的とし、多岐にわたる活動を行っています。
具体的には以下の活動が挙げられる。
- 国際保健事業の指導・調整: グローバルな健康問題に対し、リーダーシップを発揮し、各国間の調整を行います。
- 技術協力: 加盟国に対し、保健事業の強化のための技術的支援や助言を行います。労働者の健康保護について勧告することも含まれる。
- 疾病対策・撲滅: 感染症(例: HIV/AIDS, 結核, マラリア, 新型コロナウイルス感染症)やその他の疾病の予防、管理、撲滅に向けた取り組みを推進します。
- 規範・基準の設定: 医薬品、ワクチン、食品の安全性などに関する国際的な基準やガイドラインを策定・発展させます。
主な活動内容の一つとして知られているのが国際疾病分類〈ICD〉を作成すること。CDは、疾病や健康状態を分類するための国際的な基準であり、世界の健康統計や疫学調査のための情報整理に不可欠なツールです。 - 研究の促進・指導: 健康に関する研究課題を設定し、研究活動を促進・指導します。
- 情報提供と監視・評価: 医学情報の総合調整を行い、健康動向を監視・評価し、エビデンスに基づいた政策選択肢を各国に提供します。
- 緊急事態への対応: パンデミックなどの国際的な保健緊急事態において、迅速な対応と支援を調整します。
上記を参考に、各選択肢を見ていきましょう。
- 二国間協力を行う。
二国間協力は国際協力機構(JICA)が取り組んでいます。
- 識字率を向上させる。
識字率の向上は教育分野の課題であり、主に国連教育科学文化機関(UNESCO)などの機関が取り組んでいます。
- 難民の帰還支援を行う。
難民支援は、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)や国際移住機関(IOM)などの役割です。
- 国際疾病分類〈ICD〉を作成する。
正しいです。 WHOは、疾病や傷害、死因の国際的な統計を比較できるように、国際疾病分類 (International Classification of Diseases and Related Health Problems: ICD) を作成し、定期的に改訂しています。これは、世界の健康動向や疫学データの収集・分析の基盤となる非常に重要な活動です。最新版はICD-11です。
- 労働者の健康保護について勧告する。
国際労働機関(ILO)の活動です。
上記より「国際疾病分類(ICD)を作成する」が正しいです。
答え:4
第71回(AM)医用工学概論(95〜100)
▼ クリックすると詳細が開きます
95 図の回路で12Ωの抵抗に流れる電流I[A]はどれか。

- 0.1
- 0.2
- 0.4
- 0.6
- 0.8
図の回路を見ていきます。
- 合成抵抗が16Ω(12+4)の抵抗と4Ωの抵抗の並列回路。
- 並列回路では電圧が一定なので電流と抵抗は反比例となる。
- 回路全体の電流の1Aは、0.2Aと0.8Aに分かれる。(4Ωと16Ωなので)
したがって、回答は0.2Aとなります。
答え:2
96 酸化エチレンガスで正しいのはどれか。
- 毒性はない。
- 引火性はない。
- 機材を腐食させる。
- 高温滅菌法である。
- 微生物を死滅させる。
おそらく酸化エチレンガス(Ethylene Oxide Gas: EOG)は滅菌に使用される。ということだけを聞いているのでしょうが、近年の国家試験は無駄に深い知識を求められることもあるため、簡単にですがまとめていきます。
★酸化エチレンガス滅菌(EOG滅菌)の特徴
酸化エチレンガス滅菌(Ethylene Oxide Gas Sterilization, EOG滅菌)は、低温で熱に弱い医療器具の滅菌に用いられるガス滅菌法です。
- 滅菌原理: 酸化エチレンガスが持つアルキル化作用により、微生物のタンパク質や核酸を不可逆的に変化させ、機能を失わせることで微生物を死滅させます。芽胞にも有効です。
- 温度: 低温滅菌(通常30〜60℃)。
- 利点:
- 熱に弱い医療器具(プラスチック、ゴム、光ファイバーなど)の滅菌が可能。
- 多くの素材を腐食させない。
- 複雑な形状の器具やルーメン(内腔)のある器具も滅菌可能。
- 欠点・注意点:
- 強い毒性: ヒトに対して発がん性、変異原性、催奇形性などの毒性があるため、厳重な安全管理(排気、換気、ガス検知など)が必要。
- 引火性・爆発性: 可燃性ガスであるため、不活性ガス(CO2など)で希釈して使用。
- 残留毒性: 滅菌後、器具にガスが吸着・残留することがあるため、十分なエアレーション(曝気:ばっき)が必要。この曝気に時間がかかる。(数時間〜数日)
- 環境負荷: オゾン層破壊物質や地球温暖化ガスとなる懸念から、フロンガスとの混合ガスは規制されている。
選択肢を見ていきましょう。
- 毒性はない。
誤りです。 酸化エチレンガスは、人体に対して毒性があり、吸入すると眼や呼吸器の刺激、吐き気、嘔吐などを引き起こし、高濃度では神経症状や遺伝毒性、発がん性も指摘されています(国際がん研究機関IARCではグループ1に分類)。そのため、使用には厳重な管理が必要です。
- 引火性はない。
誤りです。 酸化エチレンガスは、非常に引火性が高く、爆発性も持ちます。そのため、通常は不燃性のガス(二酸化炭素など)と混合して使用されます。
- 機材を腐食させる。
誤りです。 酸化エチレンガス滅菌の大きな利点の一つは、機材をほとんど腐食させないことです。熱に弱いプラスチック、ゴム製品、精密機器などの滅菌に適しています。
- 高温滅菌法である。
誤りです。 酸化エチレンガス滅菌は、一般的に低温滅菌法(通常30℃〜60℃程度)に分類されます。このため、オートクレーブのような高温・高圧に耐えられない医療機器の滅菌に用いられます。
- 微生物を死滅させる。
正しいです。 酸化エチレンガスは、微生物のタンパク質や核酸に作用し、それらの機能を阻害することで、細菌、ウイルス、真菌、芽胞を含むあらゆる微生物を死滅させる強力な滅菌剤です。
したがって、酸化エチレンガスで正しいのは「微生物を死滅させる」です。
答え:5
97 通信プロトコルの階層のうち、アプリケーション層の規格はどれか。
- Ethernet
- HTTPS
- IP
- TCP
- Wi-Fi
★通信プロトコルの階層と各プロトコルの該当層
| プロトコル | OSI参照モデルの層(主な該当層) | 役割の簡潔な説明 |
|---|---|---|
| Ethernet | 第1層(物理層) / 第2層(データリンク層) | 有線LANの物理接続と隣接ノード間のデータ転送(エラー検出含む)。 |
| HTTPS | 第7層(アプリケーション層) | Webページの安全な送受信(HTTPの暗号化版)。ユーザーが直接利用するアプリのデータ形式や機能。 |
| IP | 第3層(ネットワーク層) | 異なるネットワーク間でのデータパケットの経路選択(ルーティング)。 |
| TCP | 第4層(トランスポート層) | アプリケーション間の信頼性の高いデータ転送(順序保証、再送制御など)。 |
| Wi-Fi | 第1層(物理層) / 第2層(データリンク層) | 無線LANの物理接続と隣接ノード間のデータ転送(ワイヤレス)。 |
★通信プロトコルの階層と各プロトコルの役割
| 層 | 名称 | 役割(簡潔) | 関連プロトコル例 |
|---|---|---|---|
| 第1層 | 物理層 | 物理的な接続と電気信号の送受信を規定 | Wi-Fi(物理部分)、Ethernet(物理部分) |
| 第2層 | データリンク層 | 隣接する機器間のデータ転送とエラー検出を規定 | Ethernet、Wi-Fi(MAC層) |
| 第3層 | ネットワーク層 | 異なるネットワーク間でのパケットの経路選択を規定 | IP |
| 第4層 | トランスポート層 | アプリケーション間の信頼性のあるデータ転送を規定 | TCP、UDP |
| 第5層 | セッション層 | セッションの確立・維持・終了を規定 | (TCP/IPモデルではトランスポート層・アプリケーション層に統合) |
| 第6層 | プレゼンテーション層 | データの表現形式(暗号化、圧縮など)を規定 | (TCP/IPモデルではアプリケーション層に統合) |
| 第7層 | アプリケーション層 | ユーザーが利用するアプリのためのサービスを規定 | HTTPS、HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、DNS |
この手の問題はまとめて整理して、覚えてしまうのが手っ取り早いです。
選択肢の中でアプリケーション層はHTTPSだけが該当します。
答え:2
98 測定対象の物理量変化に対応して電気抵抗が変化するセンサはどれか。2つ選べ。
- 圧電素子
- サーミスタ
- ストレンゲージ
- 熱電対
- ホール素子
各センサの役割をまとめました。
★電気抵抗が変化するセンサーとその他のセンサー
| センサー名 | 原理・測定対象の物理量 | 主な用途例 |
|---|---|---|
| サーミスタ | 温度の変化に応じて電気抵抗が変化する半導体素子。 | 温度計、温度制御、温度補償 |
| ストレンゲージ | 物体にひずみ(変形)が生じると、それに伴い電気抵抗が変化する素子。 | 荷重計、圧力計、トルク計、ひずみ測定 |
| 圧電素子 | 圧力や力を加えると電圧を発生する(圧電効果)。 | マイク、スピーカー、振動センサー、超音波探傷 |
| 熱電対 | 2種類の異なる金属の接点に温度差が生じると電圧を発生する(ゼーベック効果)。 | 高温測定(工業炉、排気ガスなど) |
| ホール素子 | 電流が流れる半導体に磁場を加えると、磁場に垂直な方向に電圧を発生する(ホール効果)。 | 磁気センサー、電流センサー、非接触スイッチ、モーター制御 |
上表より、測定対象の物理量変化に対応して電気抵抗が変化するセンサーは、サーミスタとストレンゲージです。
答え:2と3
99 64種類の項目をコード化する場合、必要最低限の記憶容量[bit]はどれか。
- 4
- 5
- 6
- 8
- 16
計算式と考え方
各項目を一意に識別するために必要なビット数(n)は、以下の関係式で求められます。
2n≥項目の種類数
この式は、「n ビットで表現できる情報の数は 2n個である」ということを意味しています。
この 2nが、コード化したい項目の種類数以上であれば、すべての項目を一意に識別できることになります。
★計算
- 項目の種類数: 64種類
- 必要なビット数 (n) を求める。
2n≥64
選択肢で試算してみます。
24=16 (64種類に足りない)
25=32 (64種類に足りない)
26=64 (64種類をちょうど識別できる)
28=256 (64種類を識別できるが、必要最低限ではない)
216=65536 (64種類を識別できるが、必要最低限ではない)
必要最低限なので、26=64が回答となる。
答え:3
100 生体組織の電気的性質で誤っているのはどれか。
- 血液は脂肪に比べ導電率が低い。
- 体液の導電率には温度依存性がある。
- 骨格筋組織では導電率の異方性が強い。
- 細胞外液は細胞膜に比べ導電率が高い。
- 電流の周波数が高いほど導電率が高い。
生体組織の電気的性質は、それぞれの組織の組成や構造によって異なります。誤っている記述を見つけましょう。
★生体組織の電気的性質
- 血液と脂肪: 血液は電解質を多く含むため、脂肪に比べて導電率が高いです。脂肪は水分が少なく、電気を通しにくいです。
- 体液と温度: 体液中のイオンの動きは温度に影響されるため、導電率は温度に依存します(温度が高いほど導電率が高い傾向)。
- 骨格筋: 筋繊維の配列により、電流の流れやすさに方向性があるため、導電率の異方性が強いです。
- 細胞内外液と細胞膜: 細胞外液はイオンが豊富で導電率が高いですが、細胞膜は脂質二重層でできており、電気をほとんど通さないため導電率が非常に低いです。
- 電流の周波数: 細胞膜の性質により、電流の周波数が高いほど、生体組織の導電率は高くなります
上記を参考に選択肢を見ていきます。
- 血液は脂肪に比べ導電率が低い。
血液には電解質が豊富に含まれており、非常に導電性が高いです。一方、脂肪は水分や電解質が少なく、電気を通しにくい(抵抗が高い)ため、導電率は低いです。したがって、血液は脂肪に比べて導電率が高いです。
- 体液の導電率には温度依存性がある。
体液中の電解質は、温度が上昇するとイオンの運動性が活発になるため、導電率も増加します。これは一般的な溶液の性質と同様です。
- 骨格筋組織では導電率の異方性が強い。
骨格筋組織は、筋線維が一定方向に配列しているため、電流が線維の走行方向(長軸方向)に沿って流れやすいですが、線維と垂直方向(横軸方向)には流れにくいという性質があります。このように、方向によって電気的性質が異なることを「異方性」と言います。
- 細胞外液は細胞膜に比べ導電率が高い。
細胞外液には電解質が豊富に含まれており、比較的自由にイオンが移動できるため、導電性が高いです。一方、細胞膜は脂質二重層を主成分とし、疎水性であるため、イオンの透過を厳しく制限します(高い電気抵抗を持つ)。したがって、細胞外液は細胞膜に比べて導電率が高いです。
- 電流の周波数が高いほど導電率が高い。
生体組織、特に細胞膜は、低周波の電流に対しては高い抵抗を示します(コンデンサのような挙動)。しかし、周波数が高くなると、細胞膜を介した電流の流れが容易になるため、抵抗が低下し、見かけ上の導電率が上昇します。
したがって、生体組織の電気的性質で誤っているのは、「血液は脂肪に比べ導電率が低い」です。実際には血液の方が導電率が高いです。
答え:1
さいのエックスリンクを下記に載せていますので、よかったらDMにて教えてください。