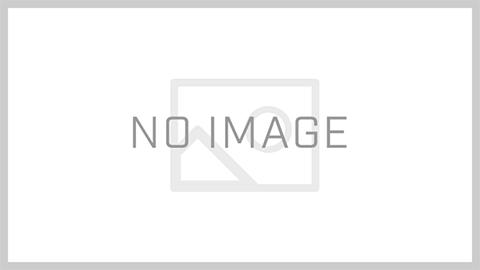【国試対策】寄生虫学は1記事でOK!?
過去問から学ぶ原虫・線虫・条虫の完全攻略
今回は、多くの受験生が「暗記地獄…」と頭を抱えるであろう「寄生虫学」を、過去問を引っ張り出して集めましたので、集中的に解説していこうと思います!
📝 引用元について
この記事で解説している国家試験の問題文は、厚生労働省のウェブサイトで公開されているものを、学習目的で引用しています。(医療トピックス一覧に国家試験過去問のリンクがあります)
けど、寄生虫学は、「誰が(寄生虫)、どこで(中間宿主)、どうやって(感染経路)、人の体で何をするか(症状)」ということを理解していけば、得点源にもなりえます!
教科書を開くと膨大な寄生虫がズラズラと記されていて、やる気が出ないと思うので、過去に出題されたポイントに特化して説明していきます!(めちゃ調べました)
原虫:小さくても侮れない単細胞の侵入者
まずは、体長数μm〜数十μmほどの、単細胞の小さな寄生虫「原虫」から。小さいからといって侮ってはいけません。中には命に関わる危険なやつもいます。
マラリア原虫:最も有名な「王様」
成人男性がアフリカから帰国後に発熱した。末血厚層塗抹のGiemsa染色標本(別冊No.1)を別に示す。この感染症について正しいのはどれか。(第67回 午前 問6)

- 1.自然治癒する。
- 2.治療薬はない。
- 3.ツェツェバエが媒介する。
- 4.感染初期に肝臓で増殖する。
- 5.細胞内寄生細菌感染症である。
致死率が最も高いのはどれか。(第68回 午後 問7)
- 1.サルマラリア
- 2.卵形マラリア
- 3.熱帯熱マラリア
- 4.三日熱マラリア
- 5.四日熱マラリア
ここをクリックして答えと解説を見る
【67回】正解:4
【68回】正解:3

画像解説のポイント:赤血球内に複数の輪状体(リングフォーム)や、特徴的な三日月形(バナナ型)の生殖母体が見られるのが熱帯熱マラリアの特徴です。
🦟(ハマダラカ)
↓ スポロゾイトが注入
👨(ヒトの体内へ)
↓ 血流に乗って…
① 肝臓で増殖
↓ メロゾイトに変身!
② 赤血球に感染・増殖 → 発熱
↓ 一部が生殖母体に
🦟(別の蚊が吸血)
↓ 蚊の体内で有性生殖
【67回】各選択肢の解説
- 4.感染初期に肝臓で増殖する → 正しい:上の図の通り、マラリア原虫はまず肝臓の細胞内で増殖します。
- 1.自然治癒する。/ 2.治療薬はない。 → 誤り:マラリアは放置すれば重症化し、特に熱帯熱マラリアは死に至る危険な感染症です。有効な治療薬(抗マラリア薬)が存在します。
- 3.ツェツェバエが媒介する → 誤り:マラリアを媒介するのはハマダラカです。ツェツェバエはアフリカ睡眠病(トリパノソーマ)を媒介します。
- 5.細胞内寄生細菌感染症である。→ 誤り:マラリアは「原虫」による感染症です。細菌ではありません。
★5種のマラリア原虫 徹底比較表
| 種類 | 発熱周期 | 特徴 | 危険度 |
|---|---|---|---|
| 熱帯熱マラリア | 不規則 (毎日) | 多重感染、バナナ型生殖母体、脳マラリア | ★★★★★ (最も高い) |
| 三日熱マラリア | 48時間 (3日目ごと) | 感染赤血球が腫大、Schüffner斑点 | ★☆☆☆☆ (再発あり) |
| 卵形マラリア | 48時間 (3日目ごと) | 感染赤血球が卵形に、Schüffner斑点 | ★☆☆☆☆ (再発あり) |
| 四日熱マラリア | 72時間 (4日目ごと) | 帯状栄養体、感染赤血球は正常大 | ★★☆☆☆ (腎症合併) |
| サルマラリア | 24時間 (毎日) | 熱帯熱マラリアに似て重症化しやすい | ★★★★☆ |
この表から、【68回】の答えが「3.熱帯熱マラリア」であることが一目瞭然です。
腸管寄生原虫:口から入る小さな脅威
Lambl〈ランブル〉鞭毛虫の主な寄生部位はどれか。(第71回 午前 問5)
- 1.胃
- 2.肺
- 3.大腸
- 4.脳脊髄
- 5.十二指腸
Kinyoun〈キニヨン〉抗酸染色が用いられるのはどれか。(第71回 午後 問6)
- 1.マラリア
- 2.トリパノソーマ
- 3.リーシュマニア
- 4.ミクロフィラリア
- 5.クリプトスポリジウム
ここをクリックして答えと解説を見る
【71回 午前5】正解:5
【71回 午後6】正解:5
主な腸管寄生原虫 比較表
| 原虫名 | 主な寄生部位 | 症状 | 検査・染色法 |
|---|---|---|---|
| ランブル鞭毛虫 | 十二指腸 | 水様下痢、脂肪便 | 糞便検査 (シスト、栄養型) |
| 赤痢アメーバ | 大腸 | イチゴゼリー状粘血便 | 糞便検査 (シスト、栄養型) |
| クリプトスポリジウム | 小腸 | 激しい水様下痢 | 糞便検査 (オーシスト)、抗酸染色 |
各問題の解説
- 【71回 午前5】:上の表の通り、ランブル鞭毛虫の主な寄生部位は「5.十二指腸」です。
- 【71回 午後6】:クリプトスポリジウムのオーシストは、結核菌などと同様の抗酸性という性質を持つため、検出にはKinyoun染色などの「5.抗酸染色」が用いられます。
泌尿生殖器系原虫:特殊なライフサイクル
腟トリコモナス症で誤っているのはどれか。(第71回 午前 問6)
- 1.尿沈渣で虫体が検出される。
- 2.栄養型による接触感染である。
- 3.腟分泌物から囊子が検出される。
- 4.患者とパートナーを同時に治療する。
- 5.塗抹標本ではGiemsa染色が用いられる。
ここをクリックして答えと解説を見る
正解:3
🏃♂️
(栄養型)
↓ 性交渉などで直接接触
🏃♀️
(栄養型)
↓ 分裂して増殖
シスト(囊子)を形成しない!
腟トリコモナスの生活環は非常にシンプルです。囊子(シスト)を形成せず、運動性のある栄養型のみで増殖・感染します。乾燥や環境の変化に弱いため、主に性交渉によって直接粘膜から粘膜へと感染が広がります。
各選択肢の解説
- 3.腟分泌物から囊子が検出される。 → 誤り:上記の通り、シストを形成しないため、検出されることはありません。これは誤りです。
- 1.尿沈渣で虫体が検出される。 → 正しい:特に男性では尿道に感染することが多く、尿沈渣中に運動性のある栄養型が見つかることがあります。(白血球と鑑別が必要)
- 2.栄養型による接触感染である。 → 正しい:これが基本的な感染様式です。
- 4.患者とパートナーを同時に治療する。 → 正しい:ピンポン感染(互いにうつし合うこと)を防ぐため、パートナーの同時治療が原則です。
- 5.塗抹標本ではGiemsa染色が用いられる。 → 正しい:検出には、無染色の生食懸濁液で運動性を確認する方法や、ギムザ染色、パパニコロウ染色などが用いられます。
線虫:身近に潜む「the 虫」たち
線虫は、その名の通り「線」のように細長い体を持つ寄生虫のグループです。僕たちが「寄生虫」と聞いてイメージする、いわゆる「虫」らしい形をしています。アニサキスや回虫など、食中毒や衛生環境と密接に関わるものが多く、国試でも頻繁に登場します。
食歴から寄生虫を推理する問題
それぞれの線虫が「どんな食べ物に潜んでいるか」という事を知っているかが、重要です。
夕食にしめ鯖を摂取後、深夜に激烈な腹痛を訴えた。上部消化管の内視鏡像(別冊No. 1)を別に示す。この寄生虫について正しいのはどれか。(第67回 午後 問4)
- 1.病変は胃に限局する。
- 2.生の牛肉でも感染する。
- 3.ヒトを終宿主としている。
- 4.-20℃保存で虫体は死滅する。
- 5.有効な抗寄生虫薬が存在する。
ここをクリックして答えと解説を見る
正解:4

画像解説のポイント:内視鏡で、白い糸状の虫体(アニサキス幼虫)が胃の粘膜に頭を突き刺している様子が確認できます。
アニサキスの特徴
- 4.-20℃保存で虫体は死滅する → 正しい:アニサキスは-20℃で24時間以上冷凍するか、70℃以上で加熱することで死滅します。酢(しめ鯖)や塩、ワサビでは死なないので注意が必要です。
- 1.病変は胃に限局する → 誤り:腸にも感染します(腸アニサキス症)。
- 2.生の牛肉でも感染する → 誤り:生の牛肉で感染するのは有鉤/無鉤条虫です。
- 3.ヒトを終宿主としている → 誤り:アニサキスの終宿主はクジラやイルカです。ヒトは終宿主ではない(間違って入っただけ)ため、人の体内では成虫になれません。
- 5.有効な抗寄生虫薬が存在する → 誤り:有効な駆虫薬はなく、治療は内視鏡による虫体の摘出が基本です。
40歳女性。生しらうおの食歴がある。皮膚病変(別冊No. 1)を別に示す。考えられる寄生虫はどれか。(第70回 午後 問1)
- 1.鞭虫
- 2.肝吸虫
- 3.顎口虫
- 4.東洋毛様線虫
- 5.日本海裂頭条虫
ここをクリックして答えと解説を見る
正解:3.顎口虫

画像解説のポイント:皮膚の下を虫が這い回った跡のような、線状の赤い腫れ(皮膚爬行症)が見られます。
顎口虫の物語
顎口虫は、淡水魚(ドジョウ、ライギョ、しらうお等)に潜んでいる幼虫を、生で食べることで感染します。人の体内では成虫になれず、幼虫のまま体内をさまよい続けます。これを幼虫移行症と呼びます。
- 3.顎口虫 → 正しい:皮膚の下を移動して「皮膚爬行症」を起こすのが典型的な症状です。
- 1, 4 (鞭虫, 東洋毛様線虫):これらは土壌経由で感染する線虫です。
- 2, 5 (肝吸虫, 日本海裂頭条虫):これらも魚介類から感染しますが、皮膚症状は起こしません。
虫卵の形態から寄生虫を推察する問題
それぞれの虫卵の特徴を知っているかが問われます。
61歳の女性。有機農業従事者。腹痛で来院し、虫卵検査を行った。糞便の直接塗抹標本(別冊No.2)を別に示す。考えられるのはどれか。(第69回 午前 問6)
- 1.回虫卵
- 2.鉤虫卵
- 3.条虫卵
- 4.鞭虫卵
- 5.横川吸虫卵
ここをクリックして答えと解説を見る
正解:1.回虫卵

画像解説のポイント:楕円形で、表面がゴツゴツとした蛋白膜で覆われているのが特徴です。これは「回虫」の受精卵です。
虫卵の特徴
主要な線虫卵の鑑別ポイント
| 虫卵 | 特徴 |
|---|---|
| 回虫卵 | 表面がゴツゴツ(蛋白膜) |
| 鞭虫卵 | 樽(たる)型で、両端に栓(極栓)がある |
| 鉤虫卵 | 無色で卵殻が薄い。中に細胞(卵細胞)が見える。 |
この問題の画像は、ゴツゴツした表面から「1.回虫卵」が正解と分かります。「有機農業従事者」というキーワードも、野菜などを介して土壌中の虫卵を摂取するリスクを示唆しています。
回虫には、ゴツゴツした蛋白膜を持たない「脱殻受精卵」や、細長い形の「不受精卵」といったバリエーションもあります。国試では典型像が出やすいですが、色々な顔があることも知っておくと、臨床で役立ちます。
吸虫:複雑な旅をする「葉っぱ」たち
吸虫は、その名の通り「吸盤」を持ち、平たい葉っぱのような形をした寄生虫のグループです。吸虫の生活環は特に複雑で、2つ以上の中間宿主を移行してから、ようやく僕たちヒトの体にたどり着きます。(辿り着かないでほしいけど)
【第71回 午後 問4】寄生部位で症状を推理!住血吸虫
血尿をきたすのはどれか。
- 1.広東住血線虫
- 2.東洋毛様線虫
- 3.日本住血吸虫
- 4.Manson〈マンソン〉住血吸虫
- 5.Bilharz〈ビルハルツ〉住血吸虫
ここをクリックして答えと解説を見る
正解:5.Bilharz〈ビルハルツ〉住血吸虫
そして、種によって好んで住み着く場所(寄生部位)が違う。その違いが、症状の違いに直結すると言われています。
3大住血吸虫 比較表
| 種類 | 主な寄生部位 | 虫卵の特徴 | 主な症状 |
|---|---|---|---|
| 日本住血吸虫 | 門脈(肝臓) | 側棘なし | 肝硬変、腹水 |
| マンソン住血吸虫 | 門脈(肝臓) | 側棘あり (Lateral spine) | 肝硬変、腹水 |
| ビルハルツ住血吸虫 | 膀胱静脈叢 | 終棘あり (Terminal spine) | 血尿、膀胱がん |
各選択肢の解説
- 5.Bilharz〈ビルハルツ〉住血吸虫 → 正しい:上の表の通り、膀胱の血管に寄生し、その壁に産卵するため、膀胱を傷つけて血尿を引き起こします。
- 3, 4 (日本住血吸虫, マンソン住血吸虫) → 誤り:これらは肝臓に繋がる血管(門脈)に寄生するため、主な症状は肝障害です。虫卵は主に便中に排泄されます。
- 1, 2 (広東住血線虫, 東洋毛様線虫) → 誤り:これらは線虫であり、住血吸虫の仲間ではありません。広東住血線虫は好酸球性髄膜炎を、東洋毛様線虫は腸閉塞などを引き起こします。
条虫:長大な体を持つ「サナダムシ」たち
条虫は、僕たちヒトの腸の中で数メートルにも成長することがある、平たくて長い寄生虫です。「サナダムシ」という名前の方が有名かもしれませんね。彼らの物語では、誰が「中間宿主」で、誰が「終宿主」なのか、という役割分担が非常に重要になります。
【第71回 午前 問7】条虫の基本構造
条虫で正しいのはどれか。
- 1.雌雄異体である。
- 2.消化管を有する。
- 3.神経細胞はない。
- 4.中間宿主内で増殖する。
- 5.頭部、頸部、片節の3部位からなる。
ここをクリックして答えと解説を見る
正解:5
条虫の体のつくり
- 5.頭部、頸部、片節の3部位からなる。 → 正しい:条虫の体は、腸壁に吸い付くための頭節、新しい節を作る頸節、そして卵が詰まった多数の片節が鎖状に連なって構成されています。
- 1.雌雄異体である。 → 誤り:多くの条虫は雌雄同体で、一つの片節の中に雄と雌の両方の生殖器を持っています。
- 2.消化管を有する。 → 誤り:条虫は、僕たちが消化した栄養分を体の表面から直接吸収するため、口や肛門、消化管を持ちません。
- 3.神経細胞はない。 → 誤り:原始的ではありますが、神経系(神経節や神経索)は存在します。
- 4.中間宿主内で増殖する。 → 誤り:中間宿主内では、虫卵から孵化した幼虫が発育しますが、無性生殖などで増殖するのは主にエキノコックスなど一部の例外です。
【第69回 午後 問5 / 第70回 午後 問3】最も危険な条虫感染「囊虫症」
囊虫症をきたすのはどれか。(第69回, 第70回共通の内容で、選択肢のみ異なる問題)
- 多包条虫 / 小形条虫
- 単包条虫 / 無鉤条虫
- 無鉤条虫 / 有鉤条虫
- 有鉤条虫 / 日本海裂頭条虫
- 日本海裂頭条虫 / クジラ複殖門条虫
ここをクリックして答えと解説を見る
正解:有鉤条虫
これは、有鉤条虫だけで起こる、非常に危険な「ルート逸脱」です。
【通常の感染ルート(有鉤条虫症)】
🐖(豚の筋肉)
↓ 囊虫(幼虫)がいる
👨(ヒトが生で食べる)
↓ 腸で成虫になる
→ ただの腸管寄生
【危険な感染ルート(囊虫症)】
🥚(成虫の虫卵)
↓ ヒトが口にしてしまう
👨(ヒトの体内)
↓ 幼虫が孵化し、血流で全身へ
🧠👁️💪(脳・眼・筋肉)
↓ 囊虫を形成!
→ 全身性の重篤な疾患
つまり、ヒトが豚の代わりに「中間宿主」の役割を乗っ取ってしまうのが囊虫症です。特に脳に寄生する神経囊虫症は、てんかん発作などを引き起こし、命に関わります。
※無鉤条虫の虫卵をヒトが食べても、囊虫症は起こしません。この違いが、国試で繰り返し問われる最重要ポイントです。
【第68回 午前 問7 / 第69回 午前 問5】幼虫移行症と人獣共通感染症
幼虫移行症をきたすのはどれか。(第68回)
- 1. 小形条虫
- 2. 無鉤条虫
- 3. 日本海裂頭条虫
- 4. マンソン裂頭条虫
- 5. クジラ複殖門条虫
人獣共通感染症をきたすのはどれか。(第69回)
- 1. 蟯虫
- 2. ズビニ鉤虫
- 3. 三日熱マラリア原虫
- 4. ガンビアトリパノソーマ
- 5. エキノコックス〈多包条虫〉
ここをクリックして答えと解説を見る
【68回】正解:4
【69回】正解:5
幼虫移行症とは?
ヒトが本来の終宿主ではない寄生虫の幼虫に感染した場合、その幼虫は成虫になれず、体内をさまよい続けます。これが幼虫移行症です。
- 4. マンソン裂頭条虫 →正しい。:カエルやヘビを生で食べると、その中にいる幼虫(プレロセルコイド)に感染します。この幼虫が体内を移行し、マンソン孤虫症という幼虫移行症を引き起こします。
- 他の選択肢 → 誤り。:小形条虫、無鉤条虫、日本海裂頭条虫などでは、ヒトが終宿主であり、腸管で成虫になります。
人獣共通感染症(ズーノーシス)とは?
ヒトと他の脊椎動物の両方に感染する病原体による感染症のことです。
- 5. エキノコックス〈多包条虫〉 → 正しい。:終宿主はキツネやイヌで、ヒトは中間宿主として虫卵に感染します。肝臓で幼虫(包虫)が増殖し、重篤な肝障害を引き起こします。典型的な人獣共通感染症です。
- 1, 2, 3, 4 → 誤り。:蟯虫やズビニ鉤虫、三日熱マラリア、ガンビアトリパノソーマ(アフリカ睡眠病)は、主にヒトからヒトへ、あるいは媒介動物を介してヒトへ感染するもので、人獣共通感染症の典型例ではありません。
衛生動物と媒介感染症
寄生虫の生活環には、病原体を運ぶ「運び屋」が登場することがあります。それが蚊、ダニ、ノミなどの「衛生動物」です。どの動物が、どの病気を運ぶのか、そのペアリングを覚えることが国試対策の鍵となります。
【第69回 午後 問6 / 第71回 午後 問5】運び屋と病気の正しいペアは?
77歳の男性。西日本在住。農作業で虫に刺されたため診療所を受診し、マダニ咬症と診断された。3日後に39℃の発熱があり再診した。考えられる疾患はどれか。(第69回)
- 1.日本脳炎
- 2.発疹チフス
- 3.ツツガムシ病
- 4.デング出血熱
- 5.重症熱性血小板減少症候群〈SFTS〉
衛生動物と疾患の組合せで誤っているのはどれか。(第71回)
- 1.ノミ – ペスト
- 2.ブユ – 疥癬
- 3.キチマダニ – 野兎病
- 4.コロモジラミ – 回帰熱
- 5.コナヒョウダニ – アトピー性皮膚炎
ここをクリックして答えと解説を見る
【69回】正解:5
【71回】正解:2
【69回】は「マダニに刺されて発熱」という状況から、マダニが媒介する疾患を推理する問題。近年、西日本で発生が報告されているSFTSが正解です。
【71回】は、知識をストレートに問う組み合わせ問題です。
国試頻出!衛生動物と媒介疾患ペアリング
🦟
蚊
マラリア (ハマダラカ)
日本脳炎 (コガタアカイエカ)
デング熱 (ネッタイシマカ)
🕷️
ダニ
SFTS (マダニ)
ツツガムシ病 (ツツガムシ)
日本紅斑熱 (マダニ)
回帰熱 (マダニ)
🐜
ノミ・シラミ
ペスト (ノミ)
発疹チフス (コロモジラミ)
各問題の解説
- 【69回】:「マダニ」が媒介する疾患として最も適切なのは「5.重症熱性血小板減少症候群〈SFTS〉」です。
- 【71回】:「2.ブユ – 疥癬」が誤った組み合わせです。疥癬の原因はヒゼンダニであり、ブユは媒介しません。他の組み合わせ(ノミ-ペスト、マダニ-野兎病、コロモジラミ-回帰熱)はすべて正しいです。また、コナヒョウダニは病気を媒介はしませんが、その死骸や糞がアレルゲンとなりアトピー性皮膚炎などを引き起こします。
寄生虫検査法・総論
最後に、寄生虫学の知識を横断的に問う「総論」の問題です。虫卵の大きさ、染色法、診断法など、これまで学んだ知識が試されます。
【第67回 午前 問5 / 第70回 午前 問6】虫卵の大きさ比べ
最もサイズが小さいのはどれか。(第67回 午前 問5)
- 1.鉤虫卵
- 2.鞭虫卵
- 3.横川吸虫卵
- 4.日本住血吸虫卵
- 5.Westerman肺吸虫卵
回虫卵(受精卵)より大きい虫卵はどれか。(第70回 午前 問6)
- 1.肝蛭卵
- 2.鞭虫卵
- 3.肝吸虫卵
- 4.無鉤条虫卵
- 5.横川吸虫卵
ここをクリックして答えと解説を見る
【67回】正解:3
【70回】正解:1
しかし、国試で問われるのは、だいたい「一番大きいグループ」と「一番小さいグループ」ななので、そこを押さえておけば大丈夫です👍
●
赤血球(7μm)
🥚
横川吸虫
(約30μm)
🥚
回虫
(約60μm)
🥚
肝蛭
(約140μm)
「“ひる”はでっかい、“よこ”小さい」
肝蛭(かんしつ)や肥大吸虫(ひだいきゅうちゅう)など、「ひる」がつくグループは虫卵が大きい(100μm以上)。
一方、横川吸虫(よこがわきゅうちゅう)は、主要な虫卵の中で最も小さい(約30μm)と覚えておきましょう!
このイメージと語呂合わせがあれば、【67回】で最も小さいのが「3.横川吸虫卵」、【70回】で回虫卵より大きいのが「1.肝蛭卵」だとすぐに分かります。
- 【67回】:選択肢の中で最も小さいのは「3.横川吸虫卵」です。
- 【70回】:回虫卵(約60μm)より大きいのは、選択肢の中で最大の「1.肝蛭卵」です。
【第68回 午後 問6 / 第70回 午前 問7】複雑な旅路:中間宿主
中間宿主を有するのはどれか。(第68回 午後 問6)
- 1.回虫
- 2.蟯虫
- 3.鉤虫
- 4.鞭虫
- 5.糸状虫
寄生虫と中間宿主の組合せで正しいのはどれか。(第70回 午前 問7)
- 1.肝吸虫 – イカ
- 2.単包条虫 – イヌ
- 3.宮崎肺吸虫 – サワガニ
- 4.日本住血吸虫 – サケ
- 5.日本海裂頭条虫 – ブタ
ここをクリックして答えと解説を見る
【68回】正解:5
【70回】正解:3
まずは「中間宿主がいないグループ」をしっかり覚えるのが、効率的な学習のコツです。
【68回】中間宿主が「いない」寄生虫を覚える!
この問題は「中間宿主がいるのはどれ?」と問うていますが、逆に「いないのはどれか」を覚える方が簡単です。
以下の土壌媒介性線虫たちは、中間宿主を介さず、虫卵や幼虫が口や皮膚から直接ヒトに感染します。
- 回虫 (虫卵を経口摂取)
- 鞭虫 (虫卵を経口摂取)
- 蟯虫 (虫卵を経口摂取)
- 鉤虫 (幼虫が皮膚から侵入)
したがって、選択肢1〜4はすべて中間宿主を持ちません。一方、「5.糸状虫(フィラリア)」は、その生活環の途中で必ず蚊を中間宿主として必要とするため、これが正解となります。
【70回】主要な中間宿主の組み合わせ
国試頻出!中間宿主ペアリング
| 寄生虫 | 第1中間宿主 | 第2中間宿主 |
|---|---|---|
| 肝吸虫 | マメタニシ | 淡水魚 (コイ科) |
| 肺吸虫 | カワニナ | 淡水ガニ・ザリガニ |
| 日本海裂頭条虫 | ケンミジンコ | サケ・マス |
| 日本住血吸虫 | ミヤイリガイ | なし (経皮感染) |
肝吸虫:「マメな鯉(こい)に夢中(むちゅう)」
→ マメタニシ → コイ → 肝吸虫
肺吸虫:「川蟹(かわがに)に夢中(むちゅう)」
→ カワニナ → カニ → 肺吸虫
日本海裂頭条虫:「ケンちゃん、酒(さけ)ます?」
→ ケンミジンコ → サケ・マス
各選択肢の正誤
- 3.宮崎肺吸虫 – サワガニ → 正しい:肺吸虫は、サワガニやザリガニを生食することで感染します。
- 1.肝吸虫 – イカ → 誤り:イカではなく淡水魚です。
- 2.単包条虫 – イヌ → 誤り:イヌは終宿主です。中間宿主はヒツジやヒトです。
- 4.日本住血吸虫 – サケ → 誤り:サケではなくミヤイリガイです。
- 5.日本海裂頭条虫 – ブタ → 誤り:ブタではなくサケ・マスです。ブタを中間宿主とするのは有鉤条虫です。
【第68回 午前 問8】マラリア染色の最適pH
マラリア患者の血液塗抹標本のGiemsa染色に適するバッファーのpHはどれか。
- 1.6.2
- 2.6.8
- 3.7.4
- 4.8.0
- 5.8.6
ここをクリックして答えと解説を見る
正解:3.7.4
通常の血液塗抹標本(末梢血一般)のギムザ染色は、白血球の核や顆粒を染め分けるために、pH 6.4〜6.8の弱酸性の緩衝液を用います。
しかし、マラリア原虫の染色では、赤血球内の原虫の核(赤紫色)と細胞質(青色)のコントラストを明瞭にする必要があります。そのためには、血液の生理的pHに近いpH 7.2〜7.4の中性〜弱アルカリ性の緩衝液を用いるのが最適とされています。
まとめ
【結論】寄生虫学をマスターする4つの鉄則
寄生虫学は暗記ではなく、物語として勉強を進めると楽に頭に入るはずです。
それぞれのキャラクター(寄生虫)の物語を読み解くための4つの鉄則をマスターしましょう。
「何を食べたか?」「何に刺されたか?」が最大のヒント
| 感染源(キーワード) | 犯人(寄生虫)はこいつだ! |
|---|---|
| 生魚(サバ、アジなど) | アニサキス |
| 生肉(ブタ) | 有鉤条虫 |
| 蚊(ハマダラカ) | マラリア原虫 |
| マダニ | SFTSウイルス、日本紅斑熱リケッチア |
命に関わる「Sランク」の寄生虫は3種類!
🦟
熱帯熱マラリア
→ 脳マラリアで死に至る
🧠
有鉤条虫
→ 囊虫症(特に神経囊虫症)
🦊
エキノコックス
→ 肝臓で増殖し、肝不全に
複雑な生活環の「乗り物」を整理する
| 寄生虫 | 第1中間宿主 | 第2中間宿主 |
|---|---|---|
| 肝吸虫 | マメタニシ | 淡水魚 (コイ) |
| 肺吸虫 | カワニナ | 淡水ガニ・ザリガニ |
| 日本海裂頭条虫 | ケンミジンコ | サケ・マス |
大きさ・形・蓋の有無が鑑別の3大ポイント
🥚
横川吸虫
(最小グループ)
🥚
回虫
(ゴツゴツ)
🥚
鞭虫
(樽型+栓)
🥚
肝蛭
(最大グループ)
寄生虫学は、知れば知るほど、僕たちの生活がいかに多くの生物と関わり合っているかを教えてくれる、壮大な学問です。
今日の学びが、皆さんの知的好奇心を刺激し、国試の得点力アップに繋がることを願っています!