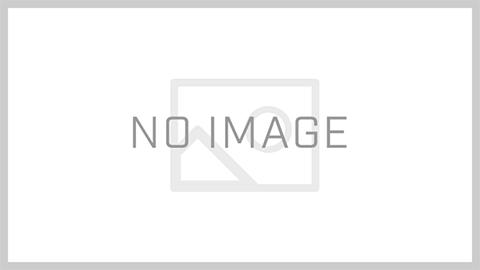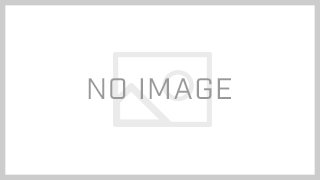過去問は厚労省ホームページより引用しております。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics_150873_139_140.html
第68回医用工学概論PM95~100
95 2byte で表せる状態の数はどれか。
- 16通り
- 256通り
- 1,024通り
- 16,384 通り
- 65,536 通り
解説:byteとbitの問題です。頻出問題でもあるので対策は必須でしょう。
- 「bit」は情報量の最小単位であり、「1bit」は「1桁の二進数」の情報量で「0」「1」の2通りの値しか表現することができない
- 「1byte」は「8bit」なので、8桁の二進数の情報量です
1byteは8bitなので28、すなわち256通り
2byteは16bitなので216、すなわち65536通り
冷静に考えて210が1024というのは周知事項と思いますが、216は計算すること自体が大変です。
★この問題のポイント(覚えておきましょう)
- 1byteは8bitなので28、計算すると256通り
- 2byteは16bitなので216、計算すると65536通り
答え:5
96 臨床検査情報の一次利用はどれか。
- 保健所への報告
- 医学研究への利用
- 教育用資料の作成
- 疾患の診断への利用
- データベースへの利用
解説:設問における医療情報に関する一次利用と二次利用を一覧にしました。
★一次利用
(患者さん毎の診療録としての本来の情報の使い方のこと)
- 保健所への報告
★二次利用
(既に他の臨床研究で収集されたデータを、別の目的の研究での解析等に使用すること)
- 医学研究への利用
- 教育用資料の作成
- 疾患の診断への利用
- データベースへの利用
答え:1
97 滅菌について正しいのはどれか。2つ選べ。
- γ線は包装後の滅菌に有効である。
- 濾過滅菌は血清の滅菌に適さない。
- 乾熱滅菌はエンドトキシンを無毒化する。
- 高圧蒸気滅菌は芽胞を有する細菌に無効である。
- 過酸化水素プラズマ滅菌はカテーテルの滅菌に無効である。
解説:滅菌についての基礎知識問題です。何にどの滅菌が有効かを知っていればOKです。
- γ線滅菌は主に医療用プラスチック製品の滅菌に使われている。個別包装し箱に梱包したままγ線を照射し滅菌する
- 血清は綿ブランフィルターを用いてろ過滅菌をする
- エンドトキシンは250℃、30分の乾熱滅菌で無毒化される
- 高圧蒸気滅菌は芽胞にも有効
- 過酸化水素プラズマ滅菌は、「非耐熱性のカテーテルやゴム製品」「精密医療機器」などに適している
答え:1と3
98 トランスデューサでないのはどれか。
- 圧電素子
- OPアンプ
- サーミスタ
- ストレンゲージ
- ポテンショメータ
解説:トランスデューサーとは何かを知っておきましょう。
★トランスデューサとは
「変換器」のことで、あるエネルギー信号を、別のエネルギー信号に変えるものをいう
- 圧電素子
⇒圧力を起電力に変換 - サーミスタ
⇒温度変化を抵抗に変換 - ストレンゲージ
⇒ひずみを抵抗に変換 - ポテンショメータ
⇒変位を抵抗に変換
など
OPアンプは演算増幅器のことで、変換機ではない。
答え:2
99 カラーRGB各1byteの階調、1,000×1,000画素、60フレーム/秒、15秒の動画がある。データを圧縮しない場合、動画ファイルのおよそのサイズ(byte)はどれか。
- 2.7 ×106
- 9×106
- 2.7 ×109
- 9×109
- 9×1012
解説:動画のファイルサイズの求め方には決まりがあります。RGBというのはRED、GREEN、BLUEの頭文字のことです。
★動画のファイルサイズの求め方
- 階調×解像度×フレーム数×秒
上式に当てはめてみると
3(階調)×{1000×1000(画素)}×60(フレーム)×15(秒)
=3×106×900
=2.7×109
答え:3
100 光学顕微鏡について正しいのはどれか。
- 開口数が大きいほど分解能が低下する。
- 尿沈渣の観察はコンデンサを上げて行う。
- 像の明るさは対物レンズの開口数の乗に比例する。
- 総合倍率は接眼レンズと対物レンズの倍率の和で表される。
- 実視野は接眼レンズの視野数と対物レンズの倍率の積で表される。
解説:顕微鏡を使っていれば、何となく解けますが、座学だけだと思えるのは大変です。
誤った設問を正しく直します。
- 開口数が大きいほど分解能は良くなる
- 尿沈査のような厚みのある標本はコントラストが必要になるのでコンデンサを少し下げると見やすくなる
(暗い方が見やすい) - 総合倍率は接眼レンズと対物レンズの倍率の積
- 実視野は接眼レンズの視野数を対物レンズの倍率の商
答え:3