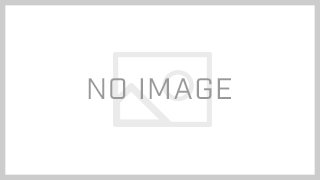過去問は厚労省ホームページより引用しております。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics_150873_139_140.html
第68回臨床微生物学PM68~78
68 髄液のGram染色標本別冊No. 16 を別に示す。分離菌はヒツジ血液寒天培地に発育し、グルコース及びマルトースを分解した。推定されるのはどれか。

- Haemophilus influenzae
- Moraxella catarrhalis
- Neisseria meningitidis
- Neisseria gonorrhoeae
- Pseudomonas aeruginosa
解説:68グラム陰性球菌(一部双球菌状)が見られ、好中球に貪食されている。設問の細菌をグラム染色で大別していくと以下の通りになる。
- ①H.influenzae(インフルエンザ菌:ヘモフィルス・インフルエンザ)はグラム陰性桿菌
- ②M.catarrhalis(モラクセラ・カタラーリス)はグラム陰性双球菌
- ③N.meningitidis(髄膜炎菌:ナイセリア・メニンギティディス)はグラム陰性双球菌
- ④N.gonorrhoeae(淋菌:ナイセリア・ゴノレエ)はグラム陰性双球菌
- ⑤Pseudomonas aeruginosa(緑膿菌:シュードモナス・エルギノーザ)はブドウ糖非発酵グラム陰性桿菌群
グラム染色像として見ると②、③、④が該当(ピンク色で球菌状)するので、この中からさらに選別していかなければならない。
ヒツジ血液寒天培地には3菌種とも発育する。
グルコース分解は髄膜炎菌と淋菌のみで、マルトース分解は髄膜炎菌のみである。
答え:3
69 エンベロープを持つのはどれか。
- ノロウイルス
- ロタウイルス
- アデノウイルス
- ポリオウイルス
- インフルエンザウイルス
解説:まず、エンベローブとは何かを知る必要があります。
★エンベローブとはウイルスカプシドの外側に脂質二重膜からなる構造物のこと
エンベロープ上にはスパイクと呼ばれる糖蛋白質があり、宿主細胞に吸着や侵入したり、宿主の免疫機構から逃れるための生理的作用を持っている
そのエンベロープを持つウイルスにはアルコール消毒薬は感受性がある
★エンベローブを持つウイルス
- インフルエンザウイルス
- コロナウイルス
- C型肝炎ウイルス
- 風疹ウイルス
- 麻疹ウイルス
- HIVウイルス
など
設問ではインフルエンザウイルスのみエンベローブを持つ、エンベローブを持たないウイルスにはアルコールは効かない。
答え:5
70 微生物検査結果について緊急報告が必要でないのはどれか。
- 静脈血からEscherichia coliが検出された場合
- 髄液からCryptococcus neoformans が検出された場合
- 皮膚からStaphylococcus epidermidis が検出された場合
- 喀痰からMycobacterium tuberculosis が検出された場合
- 胸水からカルバペネム耐性腸内細菌科細菌が検出された場合
解説:細菌検査における緊急報告は3パターンあります。
★細菌検査における緊急報告
- 無菌的材料からの検出(重症感染症や髄膜炎などのリスク)
- 感染症法で定められた微生物が検出された場合
- 院内感染対策上、重要な薬剤耐性菌などが検出された場合
従って、設問でいうところの静脈血や髄液など、通常無菌の材料から検出された場合や、二塁感染症である結核菌、カルバペネム耐性腸内細菌科細菌(CRE)のような多剤薬剤耐性菌が出現した場合は一刻も早く治療や予防策を講じる必要があるため緊急報告が必要とされる。
S.epidermidisは皮膚常在菌なので、緊急報告は要らない。
答え:3
71 喀痰のGram染色で染まりにくいのはどれか。
- Haemophilus influenzae
- Klebsiella pneumoniae
- Legionella pneumophila
- Moraxella catarrhalis
- Streptococcus pneumoniae
解説:グラム染色で染まりにくい菌種を覚えておきましょう。
★グラム染色で染まりにくい菌
- Legionella属(レジオネラ属)
細胞内寄生菌のためGram染色で染まりにくい
⇒Gimenes染色(ヒスメス染色) - Mycobacterium属(マイコバクテリウム属:結核菌など)
脂質に富む厚い細胞壁を有しているため、色素の通過が妨げられる
⇒Ziehl-Neelsen染色(チール・ネルゼン染色)
答え:3
72 5%炭酸ガス培養下のヒツジ血液寒天培地に発育するのはどれか。2つ選べ。
- Fusobacterium nucleatum
- Haemophilus influenzae
- Legionella pneumophila
- Moraxella catarrhalis
- Streptococcus pneumoniae
解説:それぞれの細菌がどういった環境で発育するのかを確認します。
- Fusobacterium nucleatumは偏性嫌気性菌のため、嫌気培養でないと発育しない
- Moraxella catarrhalis、Streptococcus pneumoniaeは、5%炭酸ガス培養下でないと発育しない
- Haemophilus influenzaeの発育には、耐熱性のⅩ因子および昜熱性のⅤ因子が必要であり、チョコレート寒天培地に発育する。
- Legionella pneumophilaの発育にはアミノ酸の『L-システインと可溶性のピロリン酸鉄』を必要とするため、それらを含んでいるB-CYE寒天培地やWYO寒天培地に発育する
答え:4と5
73 血液培養の採血時に皮膚の消毒に用いるのはどれか。2つ選べ。
- 過酢酸
- フタラール
- ポビドンヨード
- 次亜塩素酸ナトリウム
- グルコン酸クロルヘキシジンアルコール
解説:血液培養検体の採血時には推奨された消毒手順があります。
★血液培養採血時の消毒手順
- 穿刺部位を2回アルコール綿で消毒したのち(この場合、アルコール綿は単包化されたものを使用)
- 10%ポビドンヨードまたは、0.5~1%クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール綿で消毒する
従って、『アルコール、ポビドンヨード、グルコンサンクロルヘキシジンアルコール(グルコンサンクロルヘキシジン塩をアルコール水溶液で調整したもの)』が使用されます。
過酢酸、フラタールは主に器具の消毒に使われます。
次亜塩素酸ナトリウムは、環境や排泄物などの消毒に使われます。
答え:3と5
74 多剤耐性緑膿菌MDRPの判定に使用される抗菌薬はどれか。
- イミペネム
- オキサシリン
- セフォキシチン
- テイコプラニン
- バンコマイシン
解説:多剤耐性緑膿菌(MDRP)の判定は、感染症法で規定されています。
★多剤耐性緑膿菌(MDRP)の判定基準
- イミペネム(カルバペネム系b)のMICが16μg/mL以上またはディスク拡散法で耐性
- アミカシン(アミノグリコシド系)のMICが32μg/mL以上またはディスク拡散法で耐性
- シプロフロキサシン(ニューキノロン系)のMICが4μg/mL以上、またはディスク拡散法で耐性
3薬剤での耐性が条件となっている
- オキサシリンとセフォキシチンはメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)の判定
- テイコプラニン、バンコマイシンはバンコマイシン耐性腸球菌(VRE)の判定に用いられる抗菌薬
答え:1
75 偏性細胞内寄生性を有するのはどれか。
- Cryptococcus neoformans
- Listeria monocytogenes
- Mycobacterium tuberculosis
- Mycoplasma pneumoniae
- Rickettsia prowazekii
解説:偏性細胞内寄生性に属する微生物をまとめました。
★偏性細胞内寄生性とは
別の生物の細胞内でのみ増殖可能で、自身が単独では増殖できない微生物
- Rickettsia属(リケッチア属)
- Chlamydia属(クラミジア属)
- ウイルス
リケッチアが該当します。
答え:5
76 スライド培養の顕微鏡写真別冊No. 17 を別に示す。大分生子を矢印で示す。考えられるのはどれか。

- Aspergillus fumigatus
- Epidermophyton floccosum
- Microsporum canis
- Sporothrix schenckii
- Trichophyton rubrum
解説:分生子が見られるので真菌の鑑別です。ごちゃごちゃ特徴を覚えるよりも教本で確認し、形態として覚えてしまった方がいいです。(結局、形態は視覚で覚えてなんぼなので)
- ゴマ状の小分生子
- ソーセージ様形態の大分生子
これらの特徴からTrichophyton rubrumが鑑別となります。
その他設問真菌の特徴はこちら
- Aspergillus fumigatus(アスペルギルス・フミガーツス)は頂嚢(伸びた菌糸(分生子柄)の先端が膨む形態)分生子、分生子柄を形成
- Epidermophyton floccosum(エピデルモフィトン・フロッコサム)はこん棒上の大分生子を形成、小分生子はない
- Microsporum canis(ミクロスポルム・カニス)は紡錘形の大分生子を形成する
- Sporothrix schenckii(スポロトリックス・シェンキイ)はシンポジオ型分生子を形成する
答え:5
77 TSI培地に腸内細菌科細菌を接種して日後の写真別冊No. 18 を別に示す。判定として誤っているのはどれか。

- 白糖分解
- 乳糖非分解
- ブドウ糖発酵
- 硫化水素産生
- ブドウ糖からのガス産生
解説:TSI寒天培地が何を見るためのものかを整理しておきましょう。
★TSI(Triple Suger Iron Agar)寒天培地の判定
※高層部=斜面より下の部分です
- 糖分解能:ブドウ糖のみ分解する菌は高層部を黄変し、斜面部は赤色を呈する
- ブドウ糖および乳糖、白糖の両方、またはいずれか一方を分解する菌は、高層・斜面部とも黄変する
- いずれの糖も分解しない菌は高層・斜面部とも無変化または赤色を呈する
- ガス産生があれば、高層部に気泡または亀裂を生じる
- 硫化水素産生能:陽性菌は高層部を黒変する
写真の判定として
- 白糖は非分解(斜面部が赤色)
- 乳糖は非分解(斜面部が赤色)
- ブドウ糖は発酵(腸内細菌科細菌)
- 硫化水素は産生(高層部が黒色)
- ブドウ糖からのガスは産生(高層部に亀裂)
答え:1
78 Listeria monocytogenes について誤っているのはどれか。
- Gram陽性短桿菌である。
- CAMPテスト陽性である。
- 馬尿酸塩加水分解試験陽性である。
- エスクリン加水分解試験陽性である。
- ヒツジ血液寒天培地でα溶血性を示す。
解説:L.monocytogenesについて、主に設問の範囲でまとめました。
★ Listeria.monocytogenes(リステリア・モノサイトゲネス)
- グラム陽性短桿菌
- CAMPテスト陽性
- 馬尿酸塩加水分解試験陽性
- エスクリン加水分解試験陽性
- ヒツジ血液寒天培地でβ溶血性
- 人獣共通感染症であるリステリア症の原因菌
特徴をあげだすときりがないですが、こういった問題は数をこなしてその都度覚えていきましょう。
答え:5