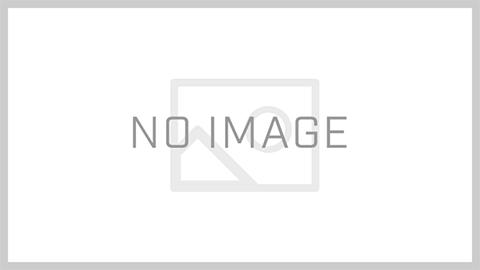【PR】この記事にはプロモーションが含まれています。
【7年分・1400問分析】臨床検査技師国家試験「出る順」TOP30!ここだけは絶対に押さえろ!
まさか…
非効率な勉強してませんか?
- ✔膨大な試験範囲を前に、何から手をつければいいか分からない…
- ✔勉強してもしても、模試の点数が伸び悩んでいる…
- ✔「出るところ」だけを効率的に勉強して、最短で合格したい!
臨床検査技師国家試験の合格を左右するのは、才能ではありません。
正しい「戦略」です。そして、その最強の戦略とは、「出るところから、順番に、完璧に叩く」こと。これに尽きます。
そこでこの記事では、私が持つ過去7年分(第65回〜第71回、合計1400問)の過去問データをすべてを解析し、本当に出題されまくっている頻出テーマTOP30を、ランキング形式で発表します。
この記事をあなたの「勉強の最強のアシスト」にすれば、もう勉強の順番で迷うことはありません。さあ、最短ルートで合格を掴み取りましょう!
【速報】過去7年間の分野別出題数データ
まず、1400問を分野別に集計したデータをご覧ください。このグラフを見るだけでも、どの分野に時間をかけるべきかが一目瞭然です。
ご覧の通り、「臨床化学」「血液学」「微生物学」の3大分野と、侮れない「生理学」が全体の半数近くを占めています。これらの分野の攻略が合格への鍵となります。もちろん、免疫学、病理学、臨床検査総論なども割合的には近いので重要です。
ここでは、半数をその4分野が占めているという点に着目しましょう。
臨床検査技師国家試験 頻出テーマTOP30
(★は画像問題での出題が多いテーマを示します)
第30位:染色体分染法(G/C/R/Qバンドなど)(7年で11問)
第29位:ビタミン(特にビタミンK, B12, D)(7年で11問)
第28位:フローサイトメトリー(CDマーカー・ゲーティング)(7年で12問)★
第27位:質量分析(MALDI-TOF-MSなど)(7年で12問)
第26位:消毒・滅菌(高水準消毒薬、EOGなど)(7年で12問)
第25位:尿沈渣(結晶・円柱)(7年で13問)★
第24位:肝炎ウイルス(B型・C型)(7年で13問)
第23位:糖尿病(診断基準、合併症)(7年で14問)
第22位:貧血(鉄欠乏性、巨赤芽球性など)(7年で14問)
第21位:リアルタイムPCR法(原理、プライマー/プローブ)(7年で14問)
第20位:染色法(グラム染色、特殊染色)(7年で14問)★
第19位:急性期反応性蛋白(CRP、トランスサイレチンなど)(7年で15問)
第18位:脳波(睡眠段階、てんかん波形)(7年で15問)★
第17位:呼吸機能検査(フローボリューム、肺気量分画)(7年で15問)★
第16位:ABO血液型(不規則凝集、亜型、オモテウラ不一致)(7年で16問)
第15位:腫瘍マーカー(AFP, CEA, CA19-9など)(7年で16問)
第14位:脂質異常症(リポ蛋白、アポリポ蛋白、検査値)(7年で17問)
第13位:ホルモン(甲状腺、副腎皮質、下垂体)(7年で17問)
第12位:自動血球計数装置(原理、誤差要因)(7年で18問)
第11位:細胞診(パパニコロウ染色、Bethesdaシステム)(7年で18問)★
TOP10
第10位:血液凝固・線溶系(PT, APTT, 凝固因子)(7年で19問)
第9位:免疫グロブリン(IgG/A/M/E, H鎖/L鎖)(7年で19問)
第8位:寄生虫(虫卵、感染経路、中間宿主)(7年で20問)★
第7位:白血病(急性/慢性、染色体異常)(7年で21問)★
第6位:酵素(基準範囲、逸脱酵素、アイソザイム)(7年で23問)
🥉 第5位:微生物の同定・培地(7年で24問)
ワンポイント:菌名と培地の組み合わせ、グラム染色所見、主要な生化学的性状(オキシダーゼ、TSIなど)は毎年形を変えて問われる最重要知識です。
🥈 第4位:超音波検査(原理、アーチファクト、各臓器の所見)(7年で25問)★
ワンポイント:ドプラ法やアーチファクトの原理といった基礎知識と、各臓器(特に心臓・肝臓)の典型的な疾患所見を問う問題が頻出です。
👑 第1位(同率):心電図(7年で28問)★
ワンポイント:不整脈(AF, PVC, ブロック)、虚血性心疾患(ST変化)、電極の付け方など、基礎から臨床まで幅広く問われます。波形判読は避けて通れません。
👑 第1位(同率):免疫学(アレルギー、自己免疫、補体)(7年で28問)
ワンポイント:アレルギーの分類(Ⅰ〜Ⅳ型)、代表的な自己免疫疾患と対応自己抗体、補体の活性化経路(古典経路/副経路)は超頻出です。
👑 第1位(同率):臨床化学(電解質、酸塩基平衡)(7年で28問)
ワンポイント:Na, K, Cl, Caの動態と、アシドーシス/アルカローシスの血液ガスデータの解釈は、臨床現場でも必須の知識。毎年必ず問われます。
▼ 分野別の詳しい解説はこちらで網羅!
臨床検査技師国家試験過去問における、
各分野のより深い解説や、関連知識をまとめた「解説まとめ記事」もぜひご活用ください。
7年分のデータ分析から見えた「合格への最短ルート」
この7年分・1400問のデータを徹底的に分析して、私なりに気づいた「国試合格のための3つの真実」をお伝えします。
分析から分かった3つの真実
- 真実①:問われる知識は「類似・重複」している。
一見、違う問題に見えても、実は同じ知識の「聞き方」や「角度」を変えているだけの問題が非常に多いです。例えば、「Basedow病」の知識があれば解ける問題と、「TSHが低下する疾患」を問う問題は、根本的に同じ知識が問われています。TOP30のテーマの周辺知識を固めることが、応用力を身につける一番の近道です。 - 真実②:「画像問題」の対策は必須であること。
ランキングの「★」マークを見ても分かる通り、心電図、超音波、細胞診など、画像を見て判断させる問題が年々増加し、かつパターン化しています。教科書だけでなく、多くの画像に触れて「見る目」を養う訓練が合否を分けます。 - 真実③:合否を分けるのは「基本問題」であること。
奇問・難問はごく一部。合格ラインの120点を取るために本当に重要なのは、このTOP30のテーマのような、誰もが知っているべき基本的な知識を、いかに正確に、ミスなくアウトプットできるかです。
【特集】得点源になる!画像問題の傾向と対策
過去7年分の全画像問題を分析し、「心電図」「エコー」「細胞診・組織像」「尿沈渣」「微生物・寄生虫」の分野別に、読影のポイントと解法テクニックをまとめた特集記事を準備中です。
この記事をブックマークして、公開をお待ちください!
まとめ:このランキングを「勉強の地図」にしよう
今日から、このランキングの上位のテーマから一つずつ、完璧に潰していきましょう。一つ潰すごとに、あなたの合格は確実に近づいていきます。
あなたの努力が、最高の結果に結びつくことを心から応援しています!
一緒に「臨床の現場」で活躍しましょう!
【合格後の未来を考えるあなたへ】
国試の先には、最高のキャリアが待っています。就職・転職で失敗しないための「優良サイト比較記事」も、ぜひ参考にしてください。